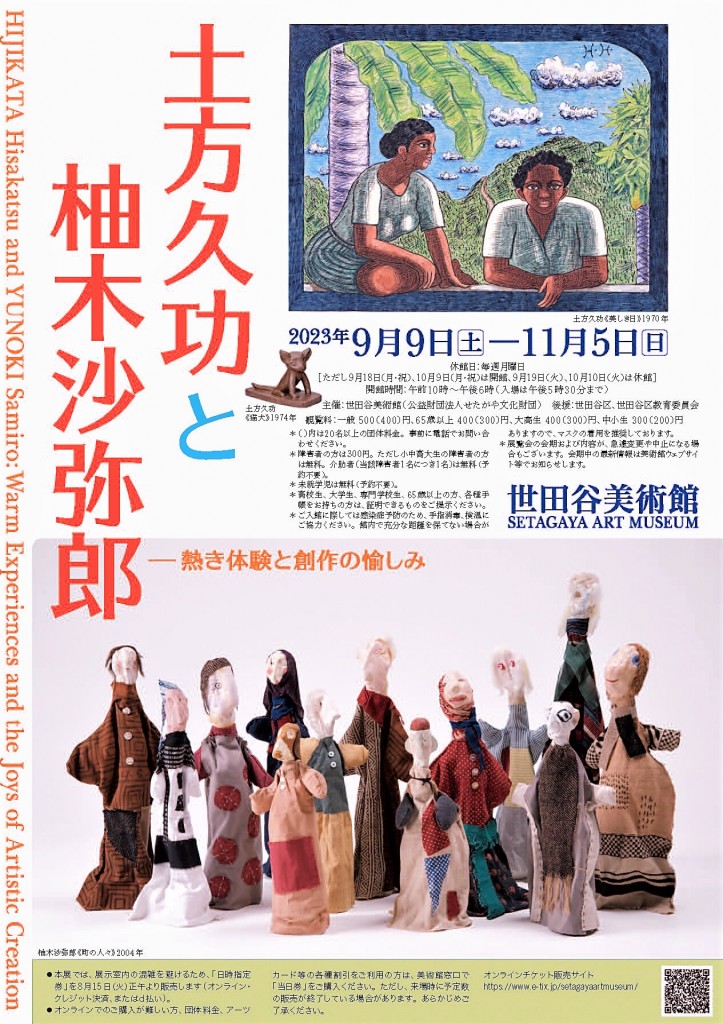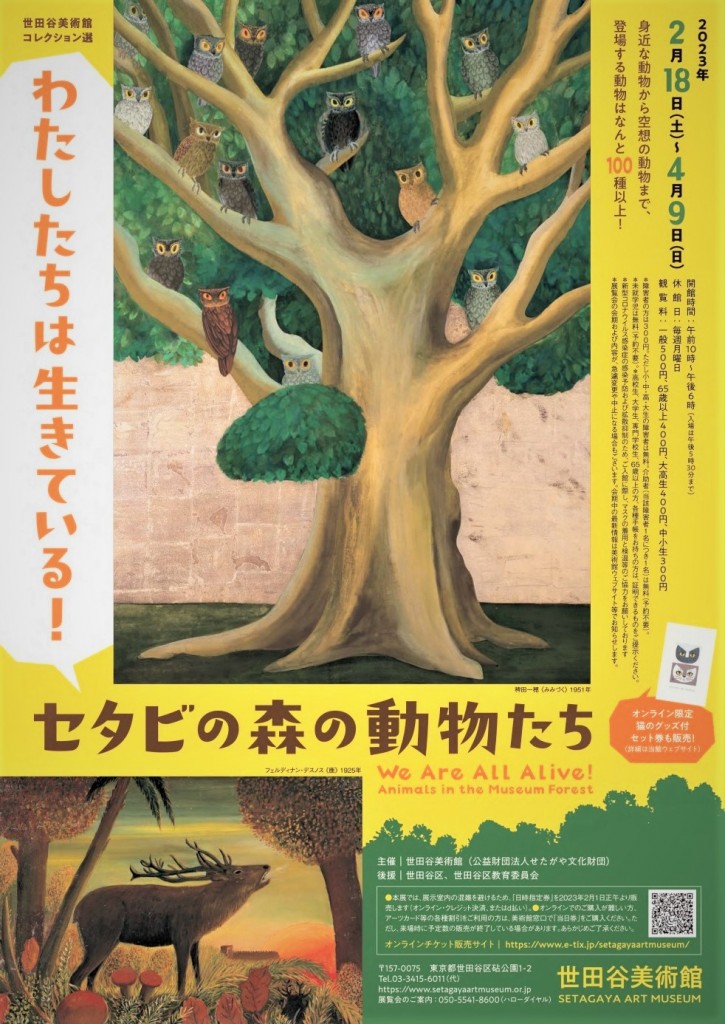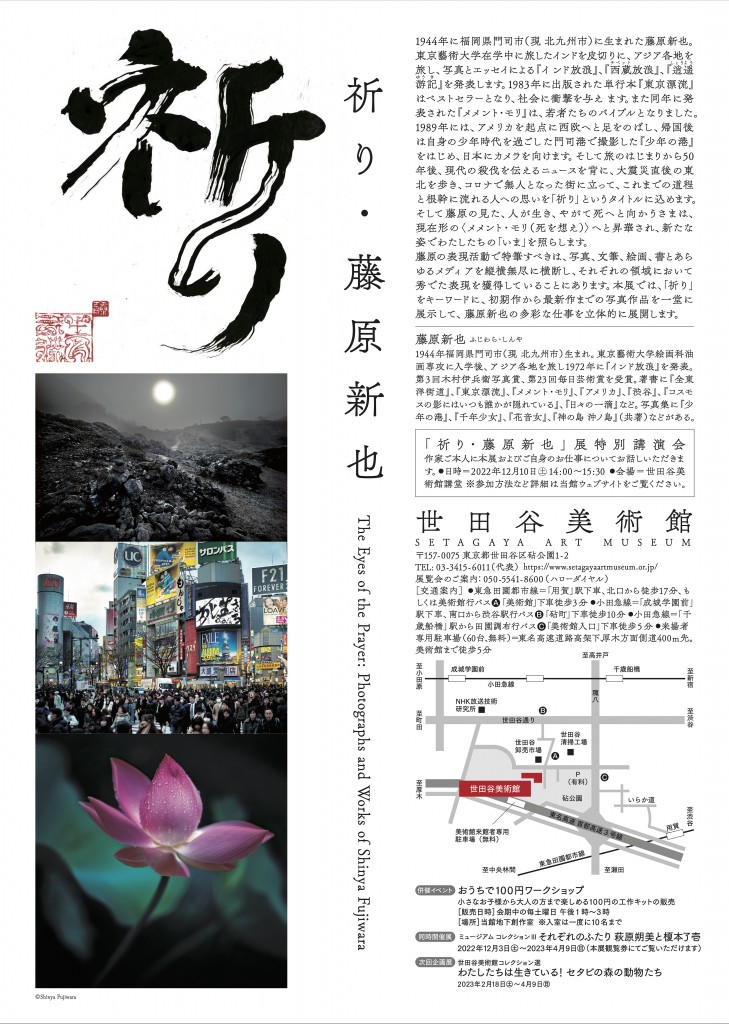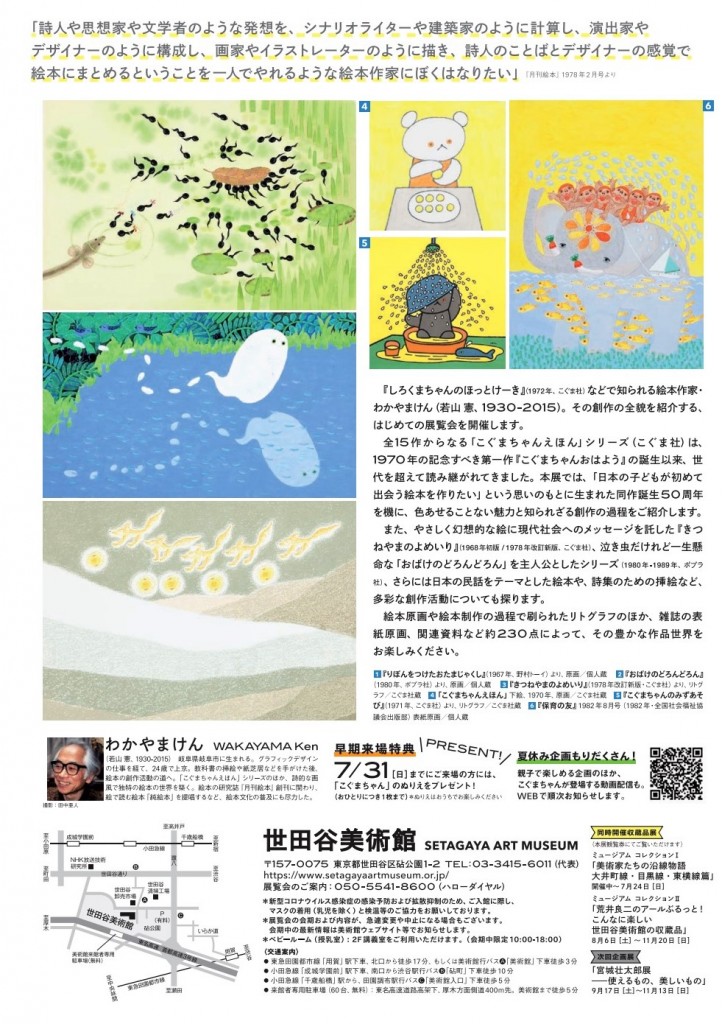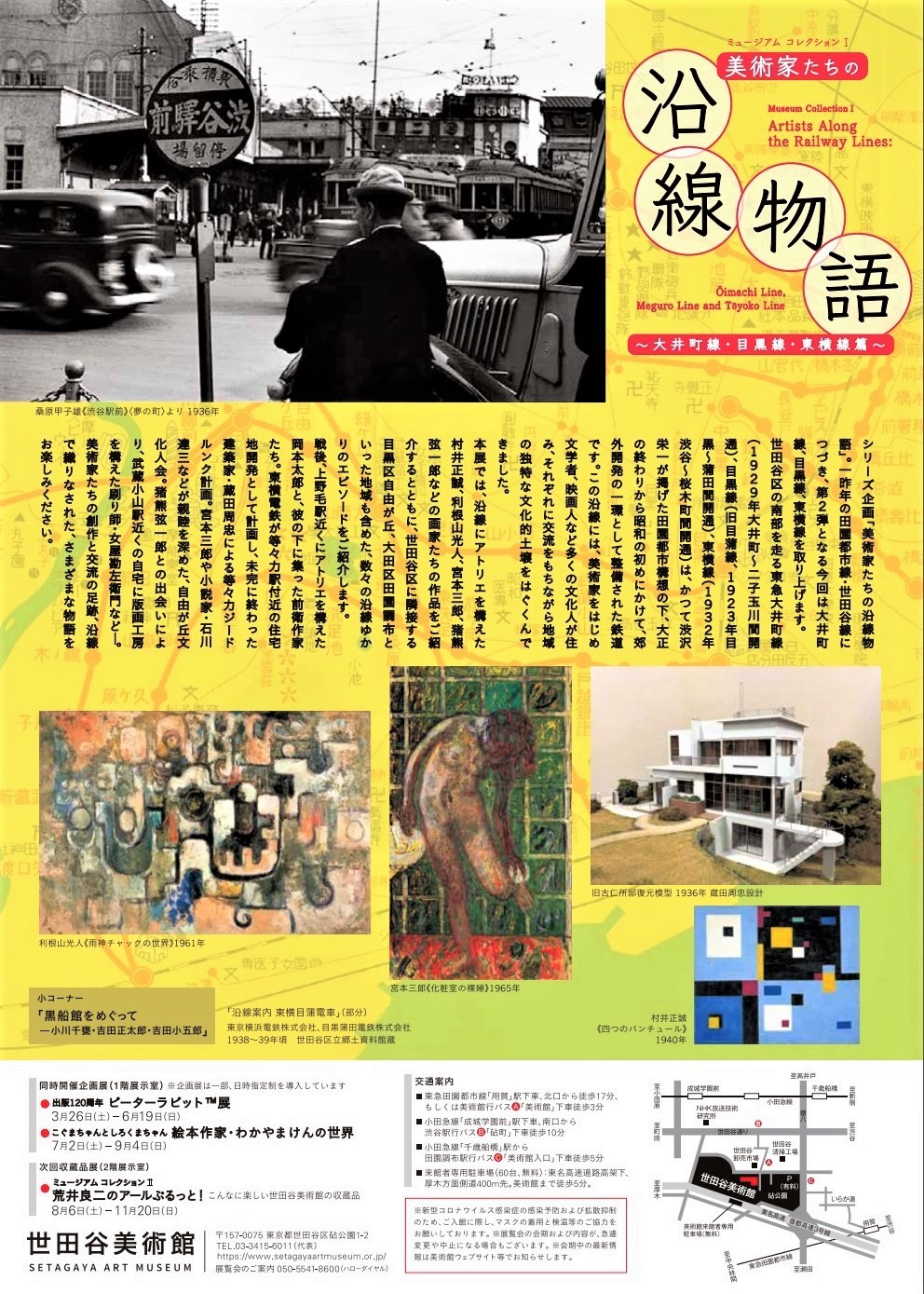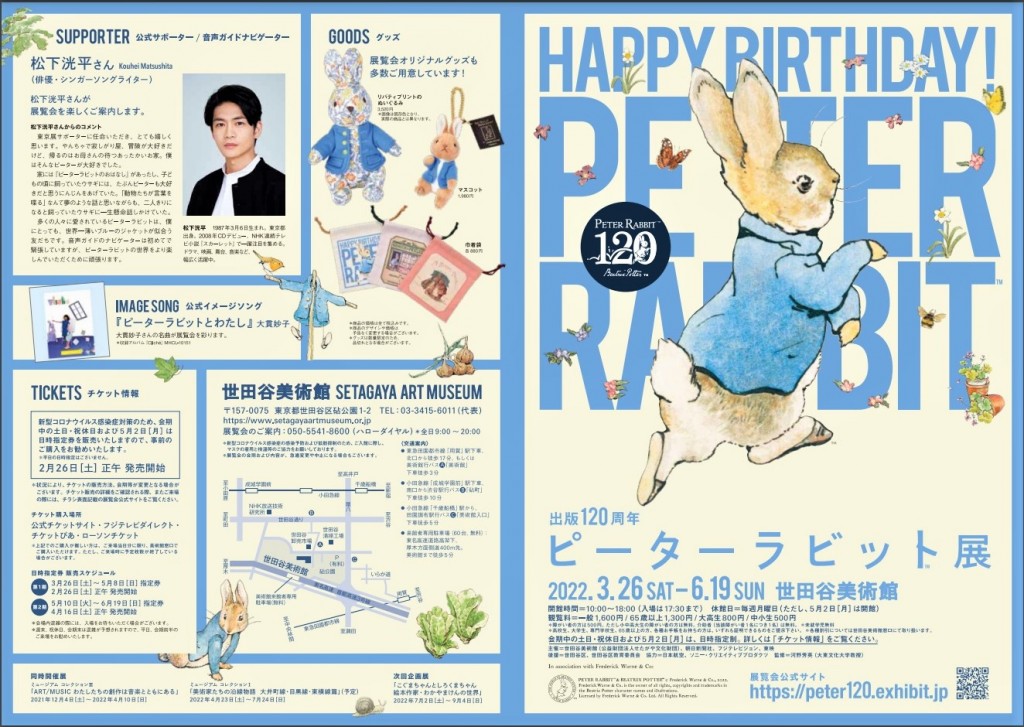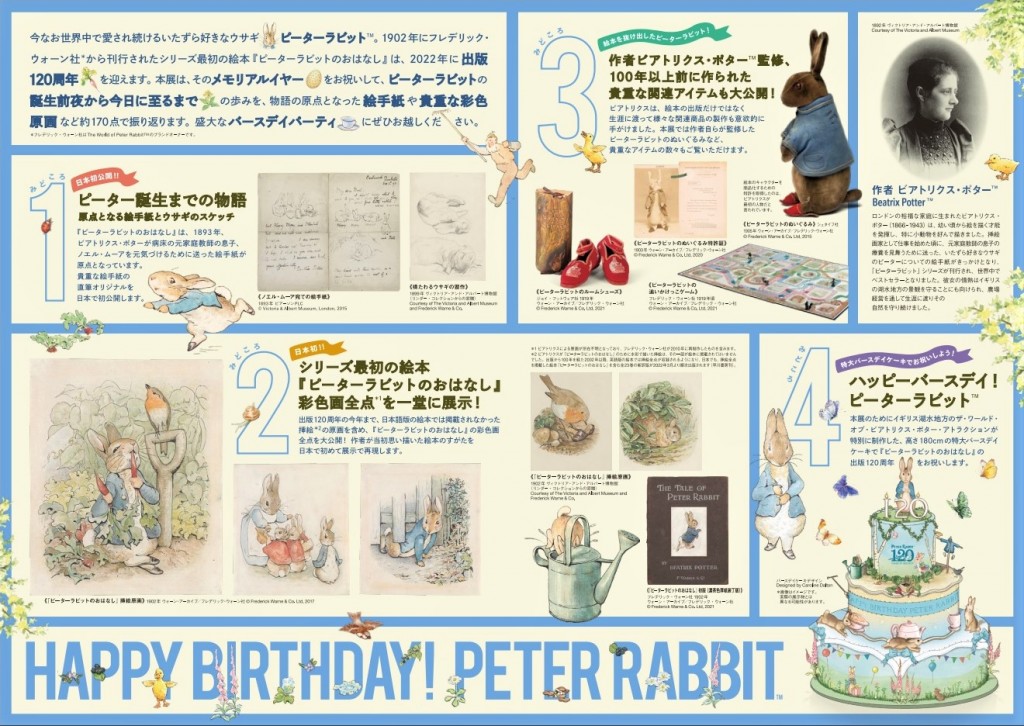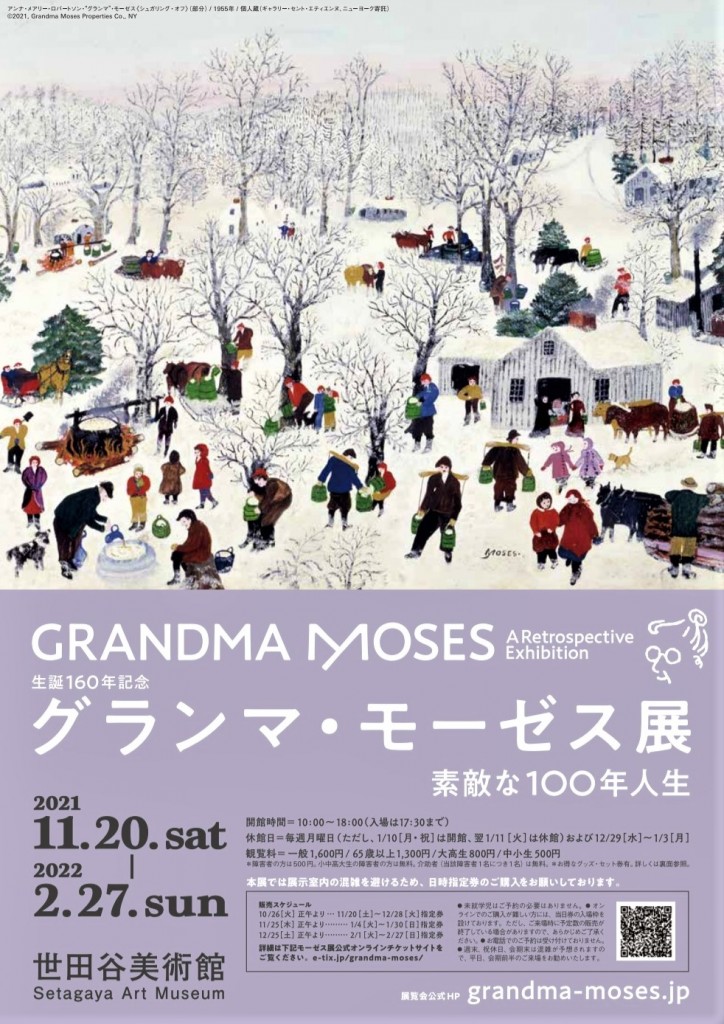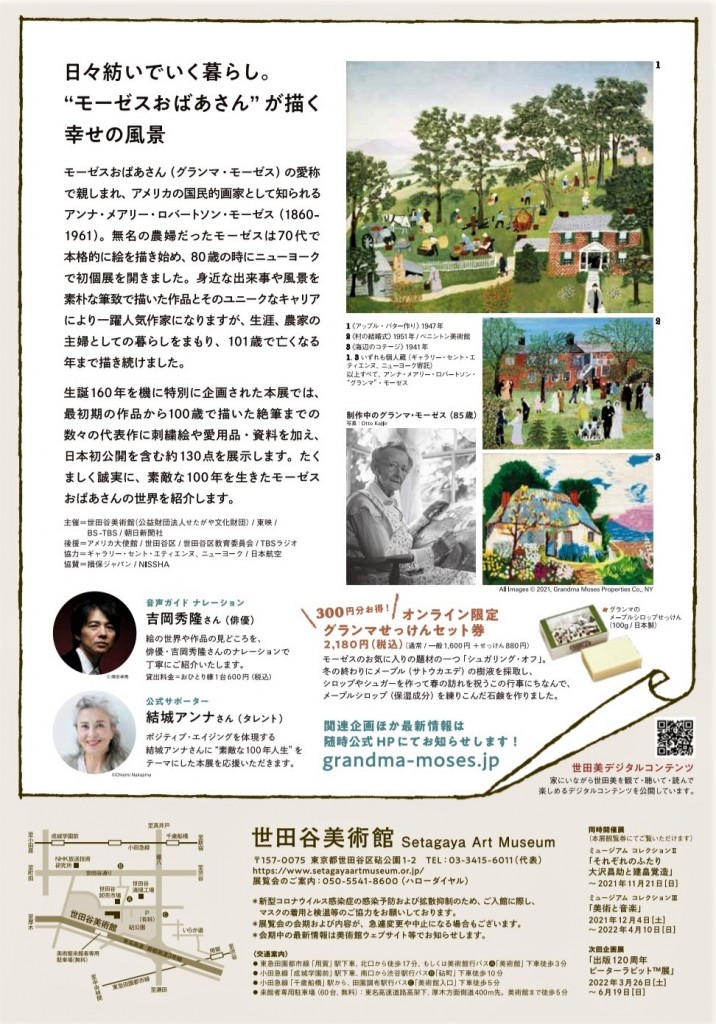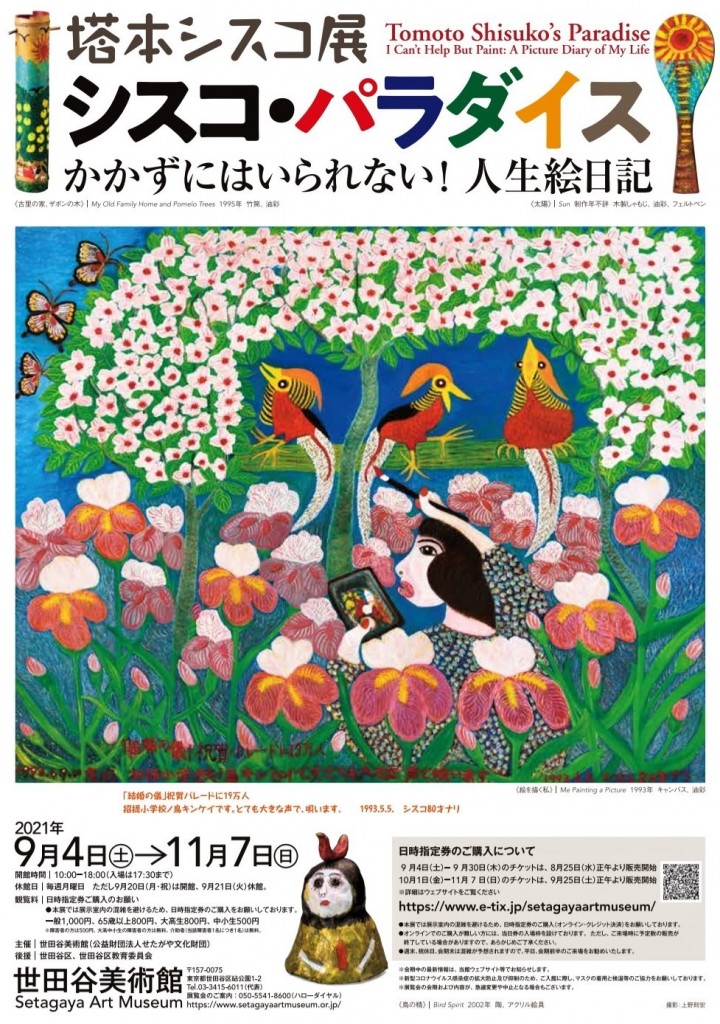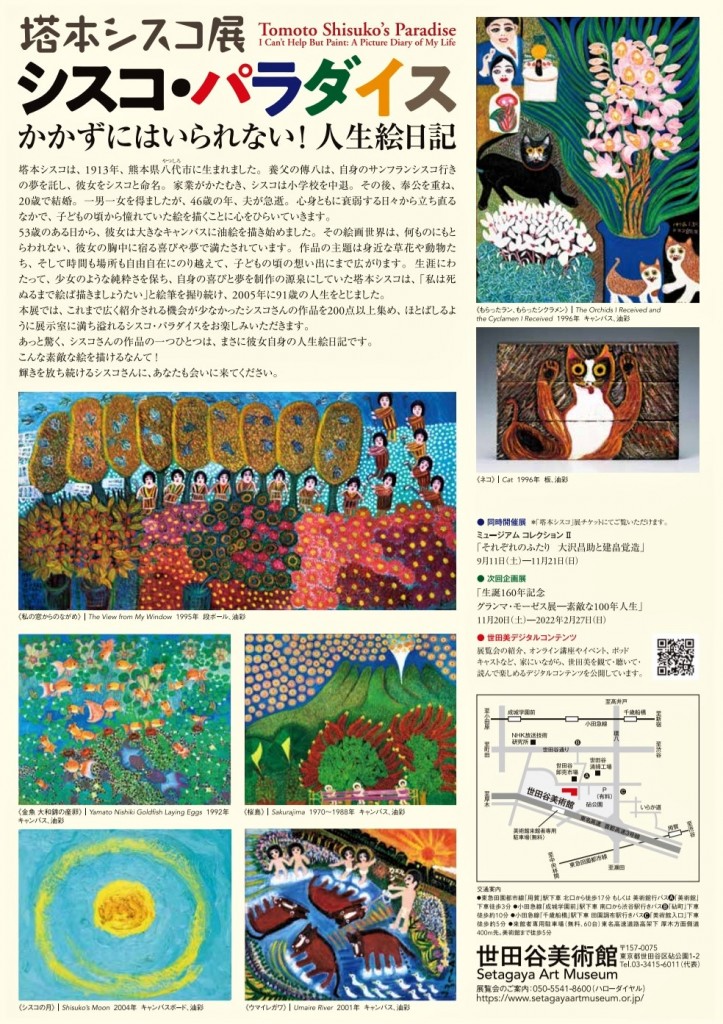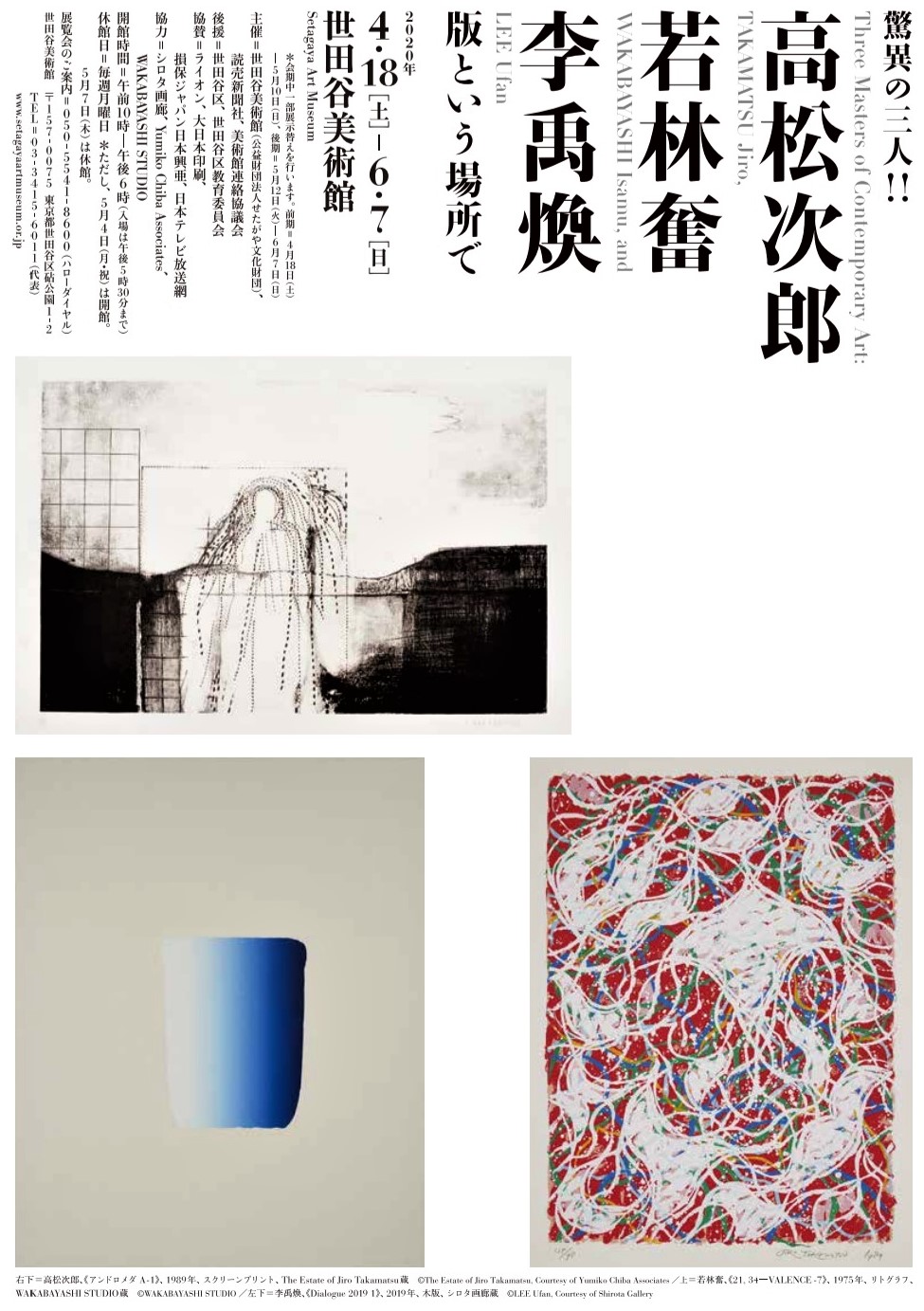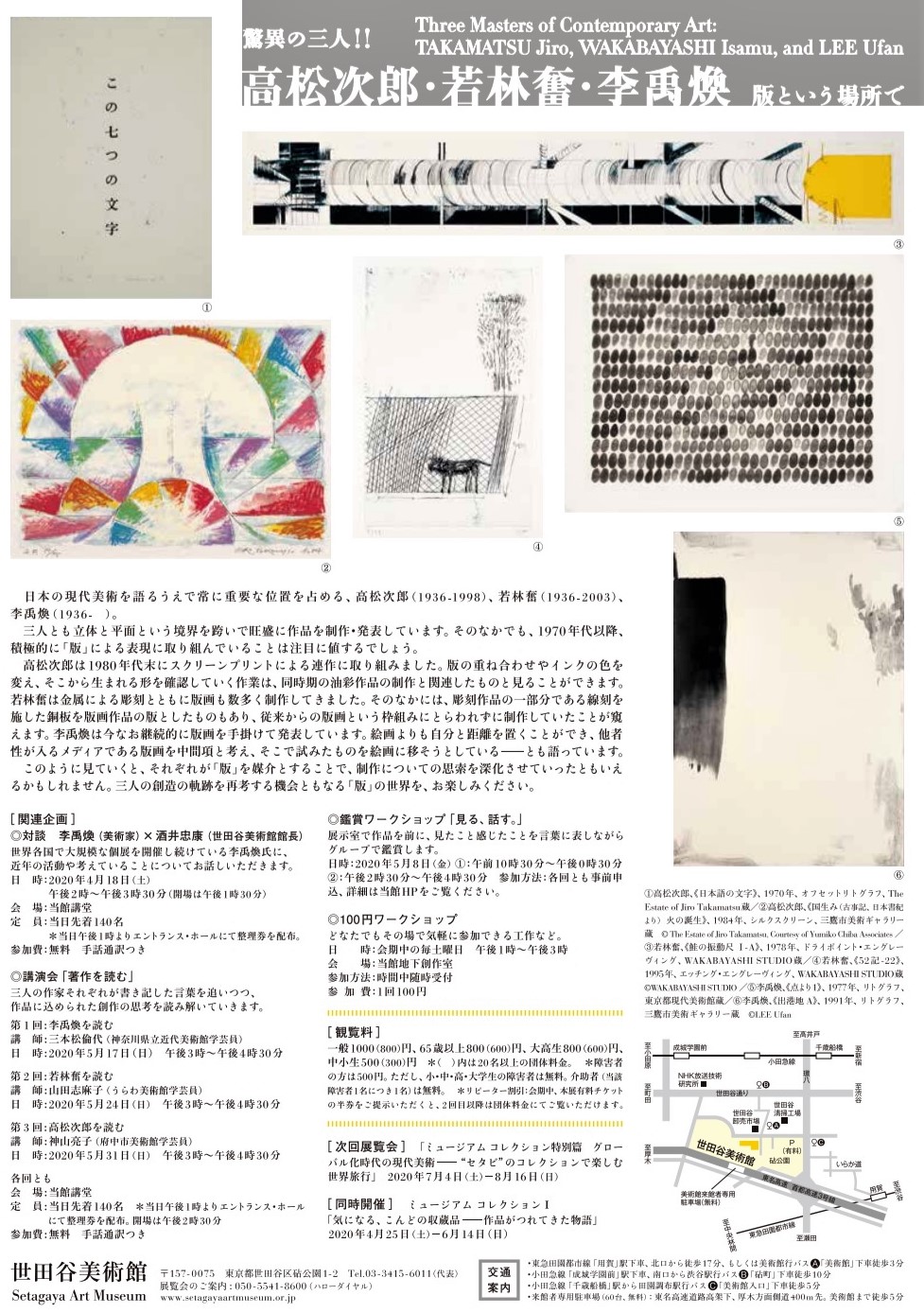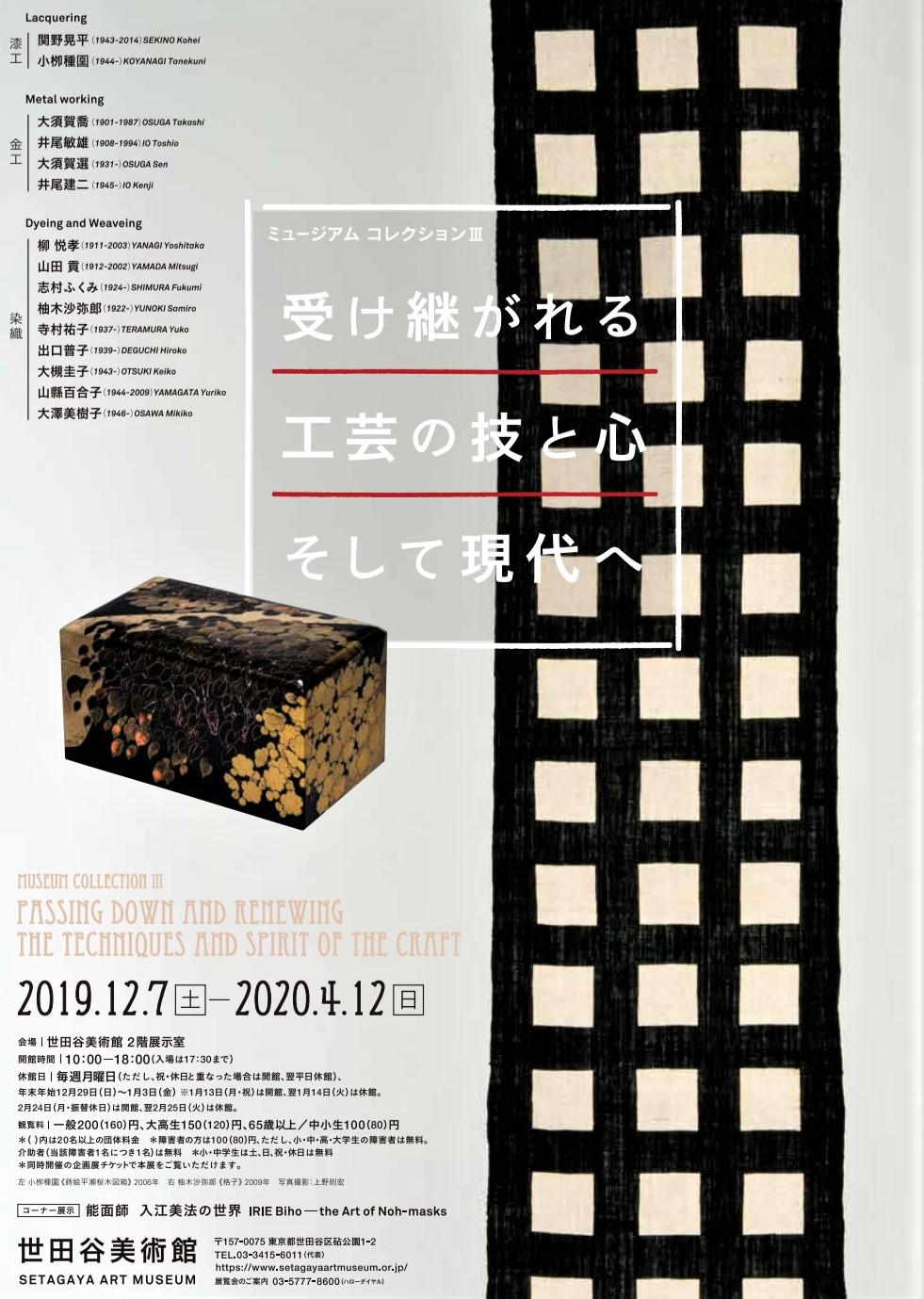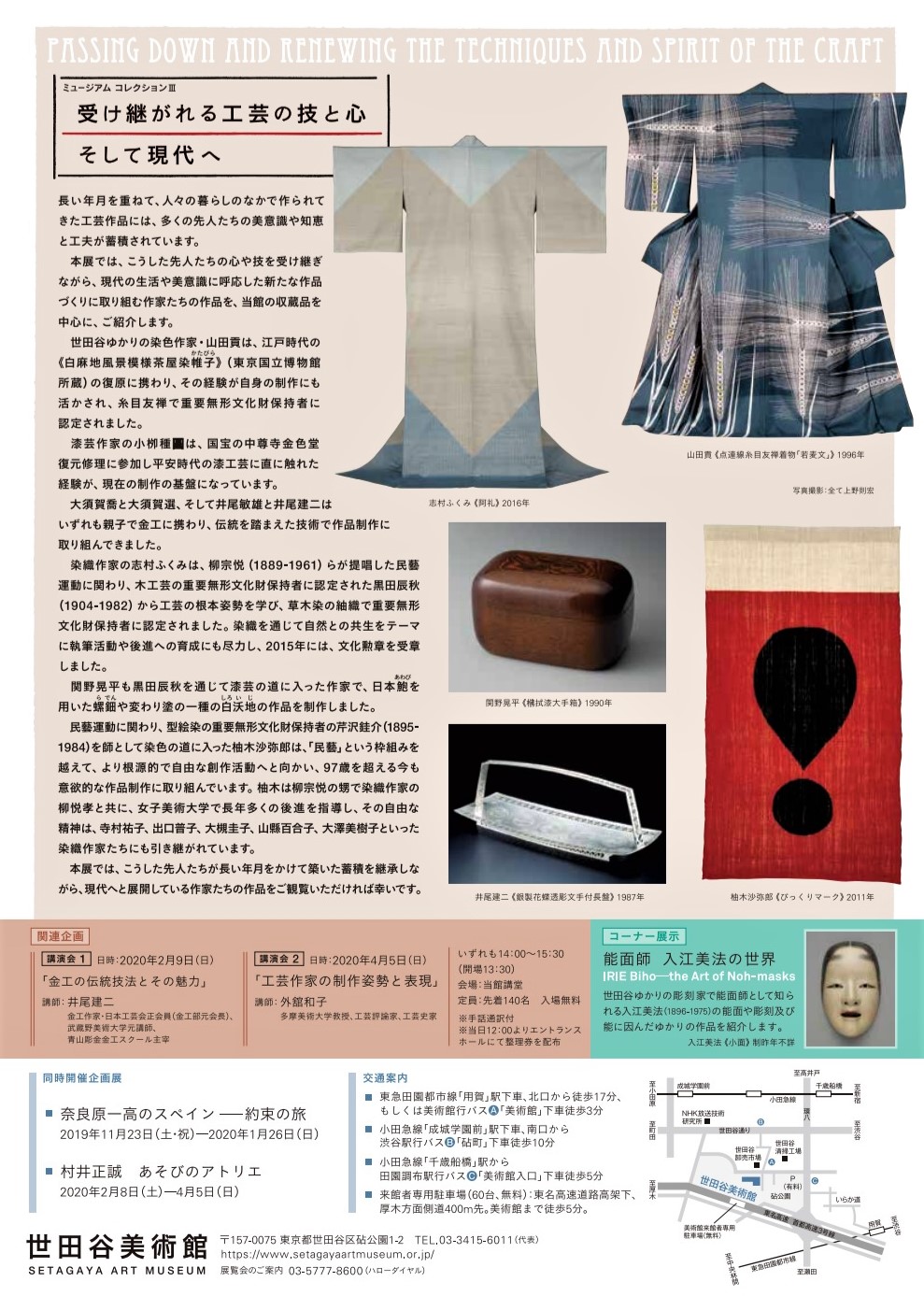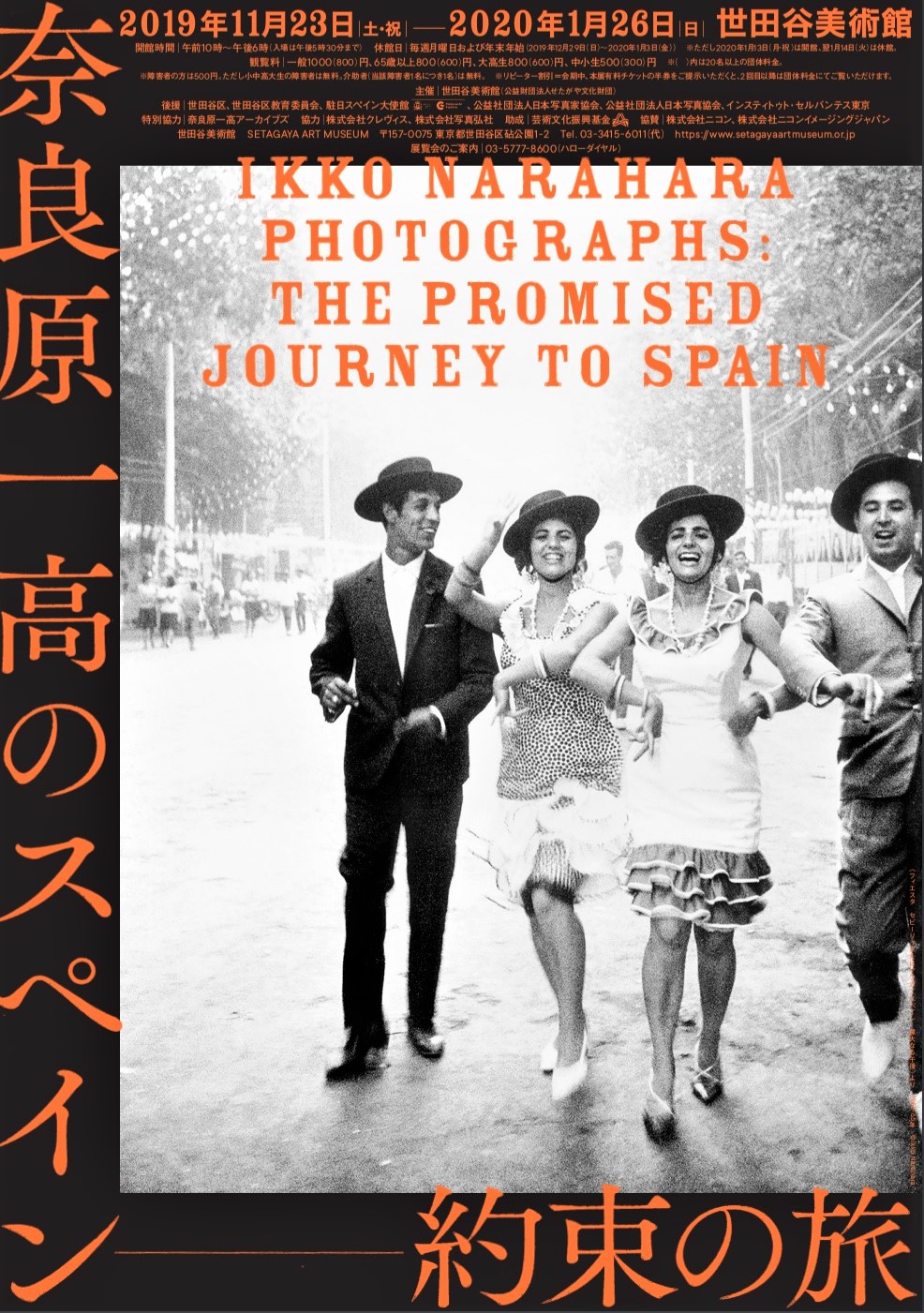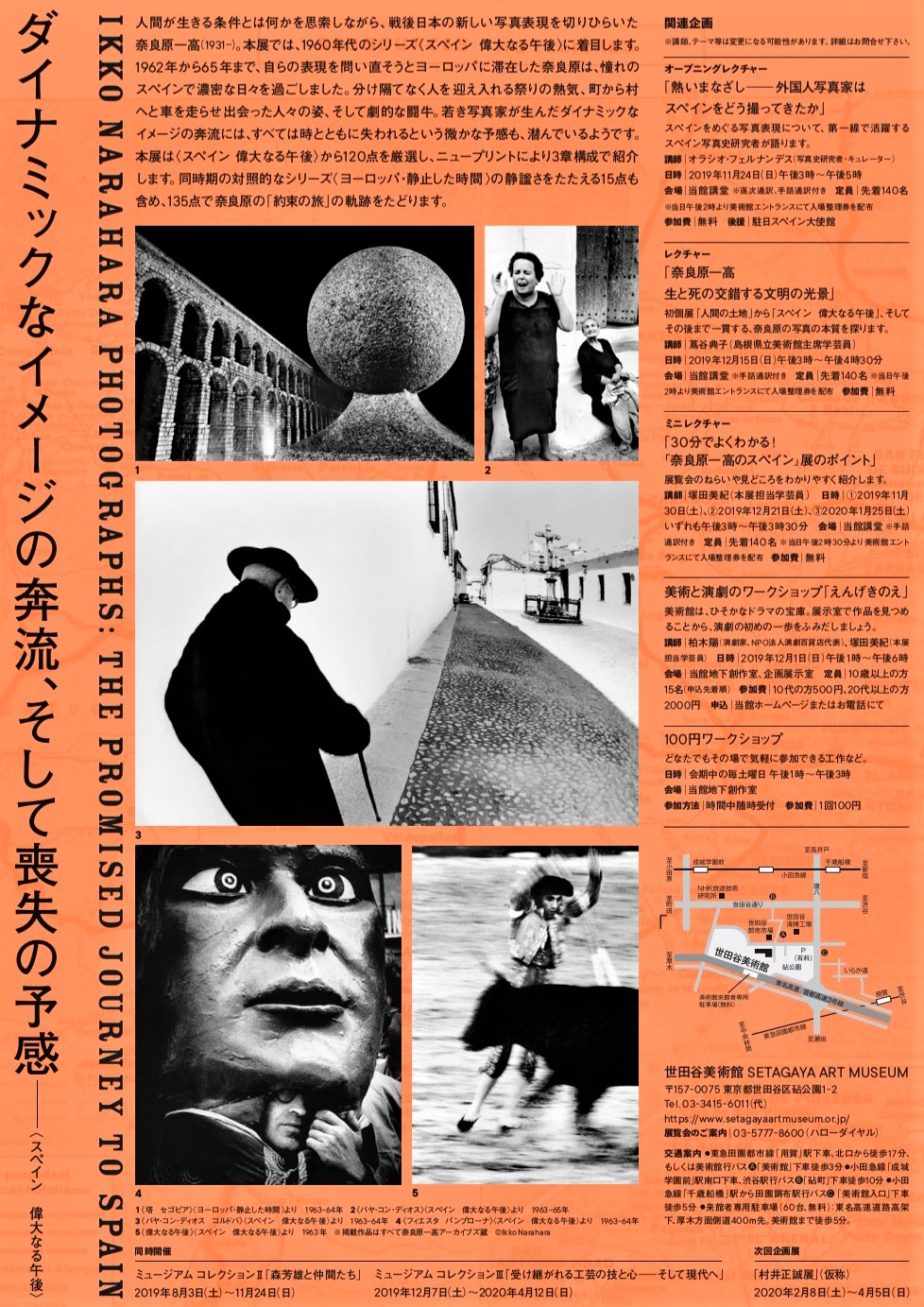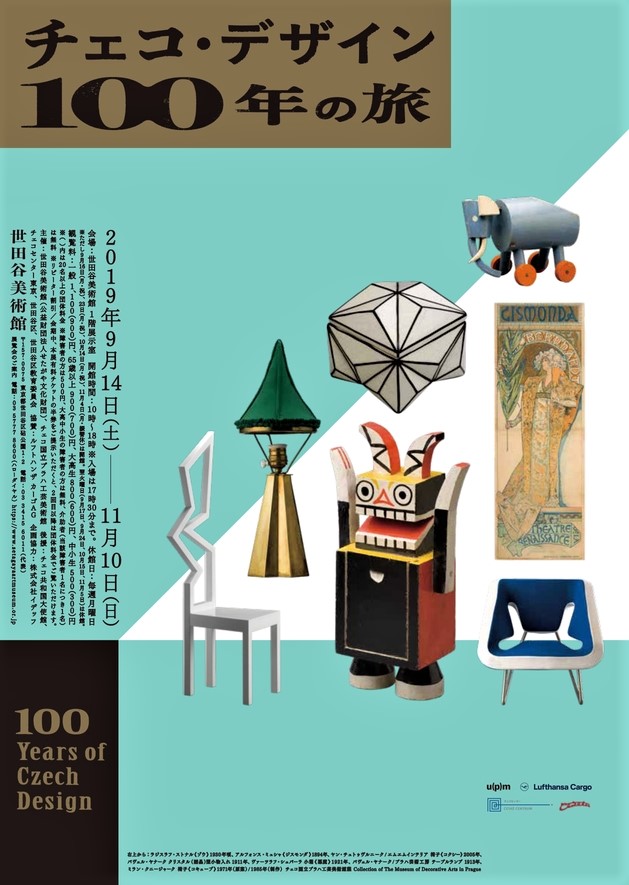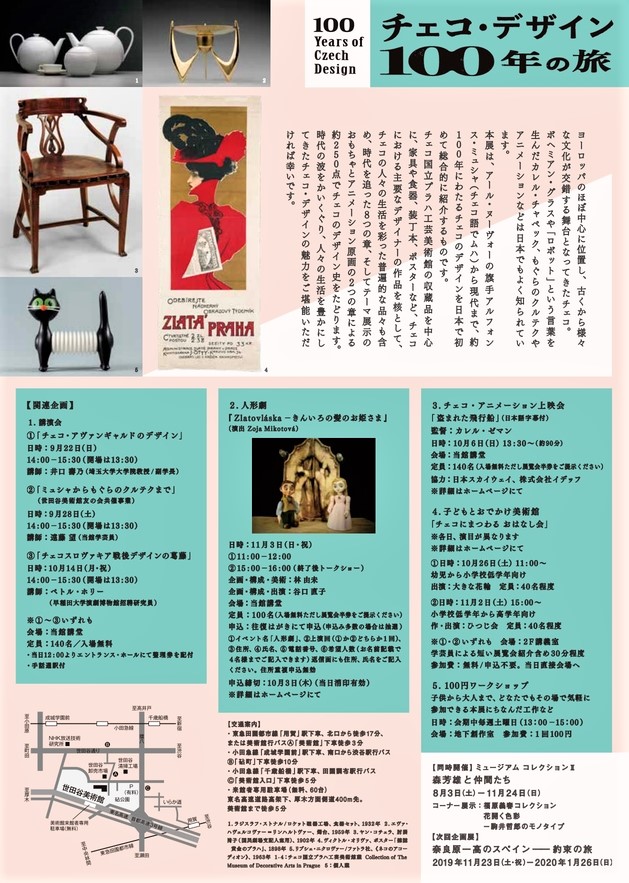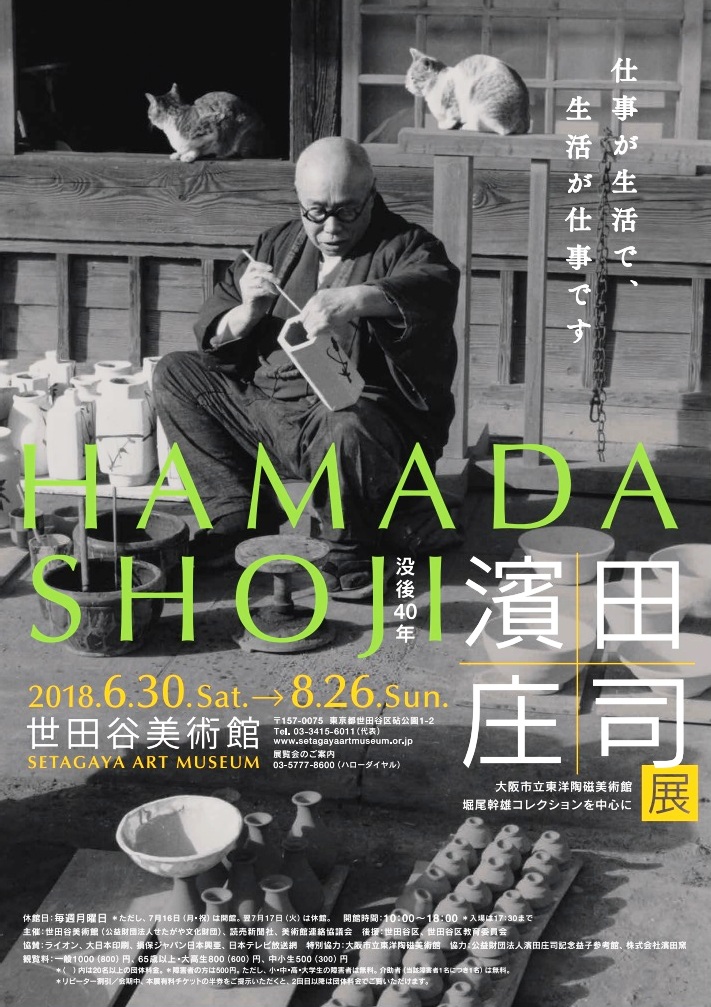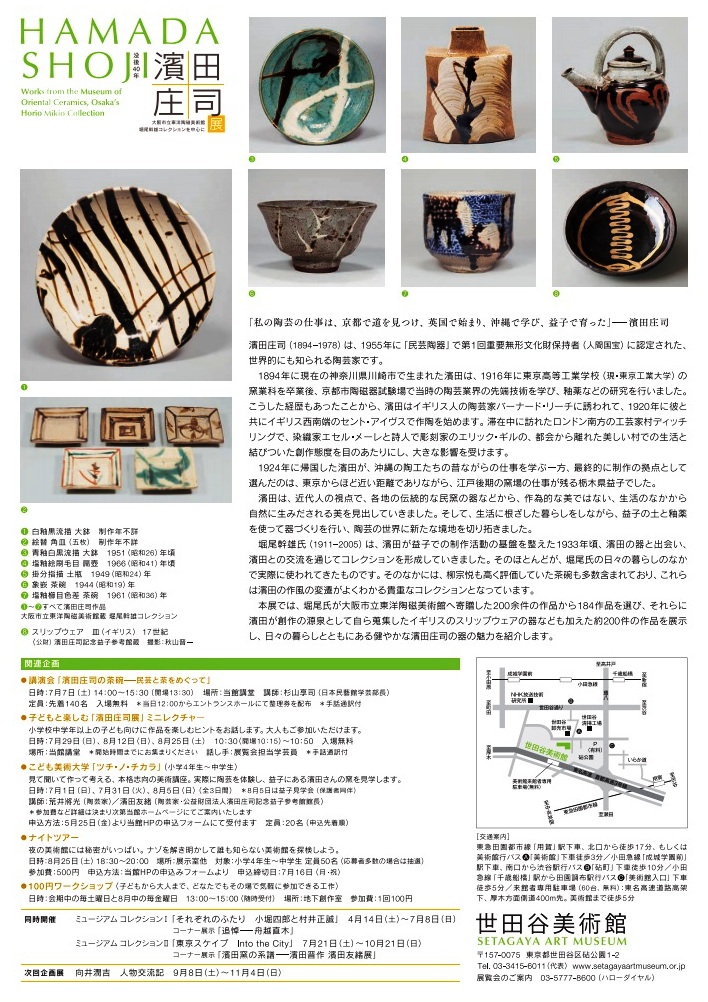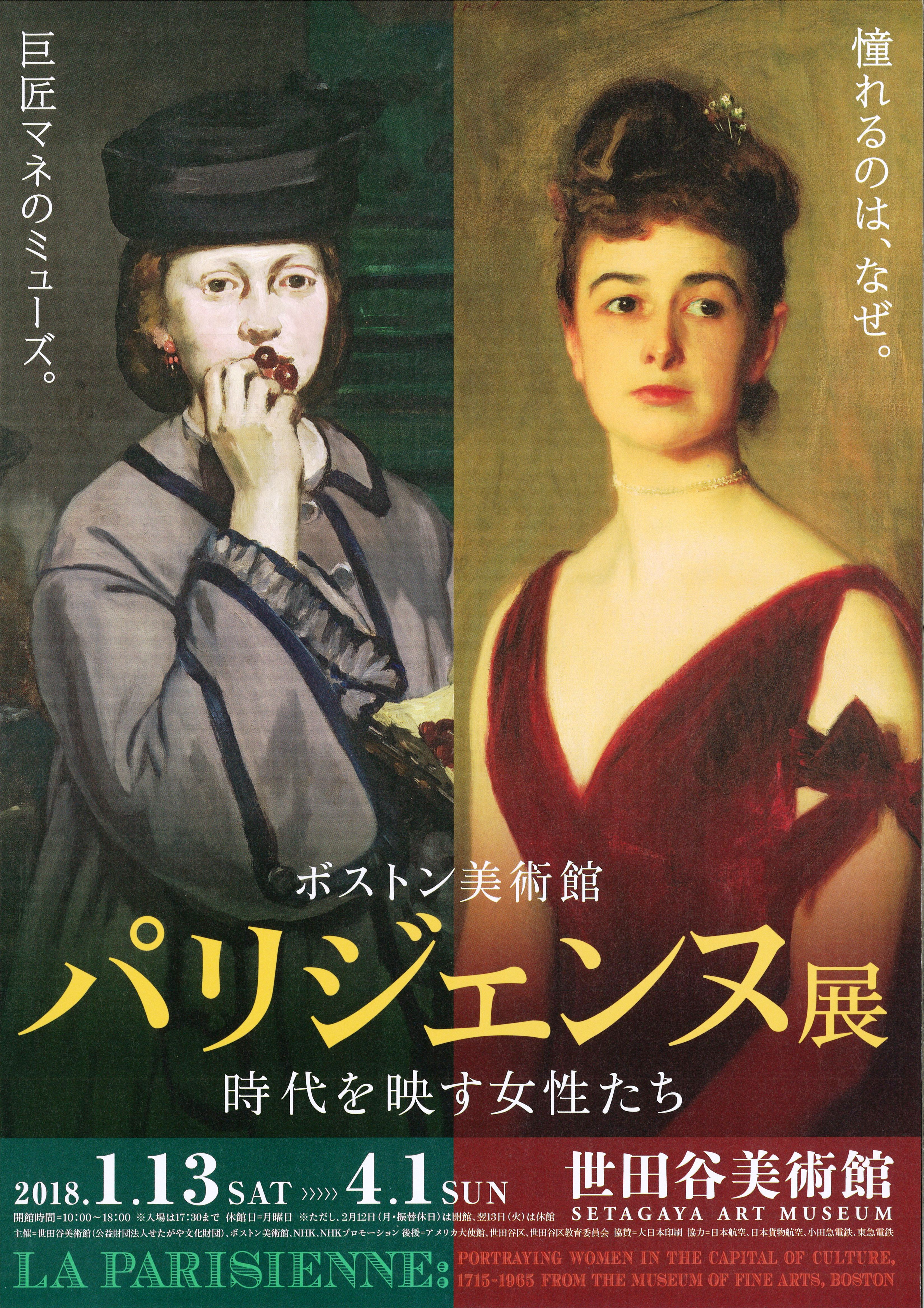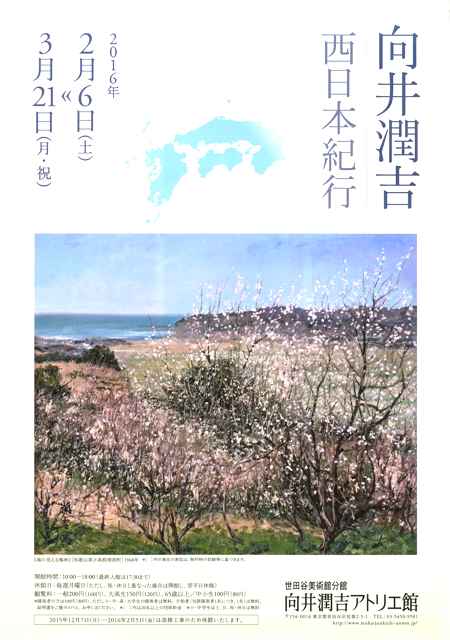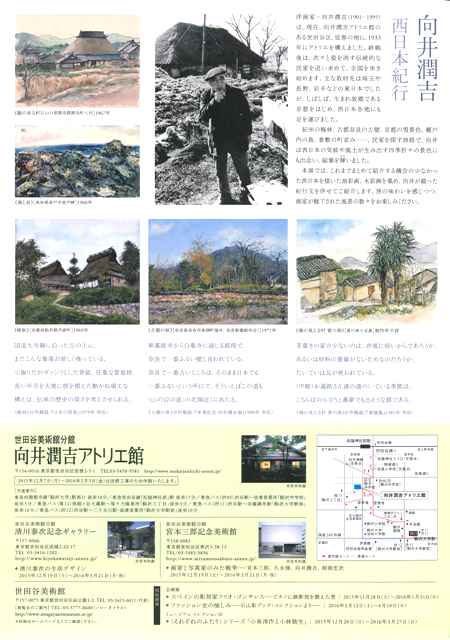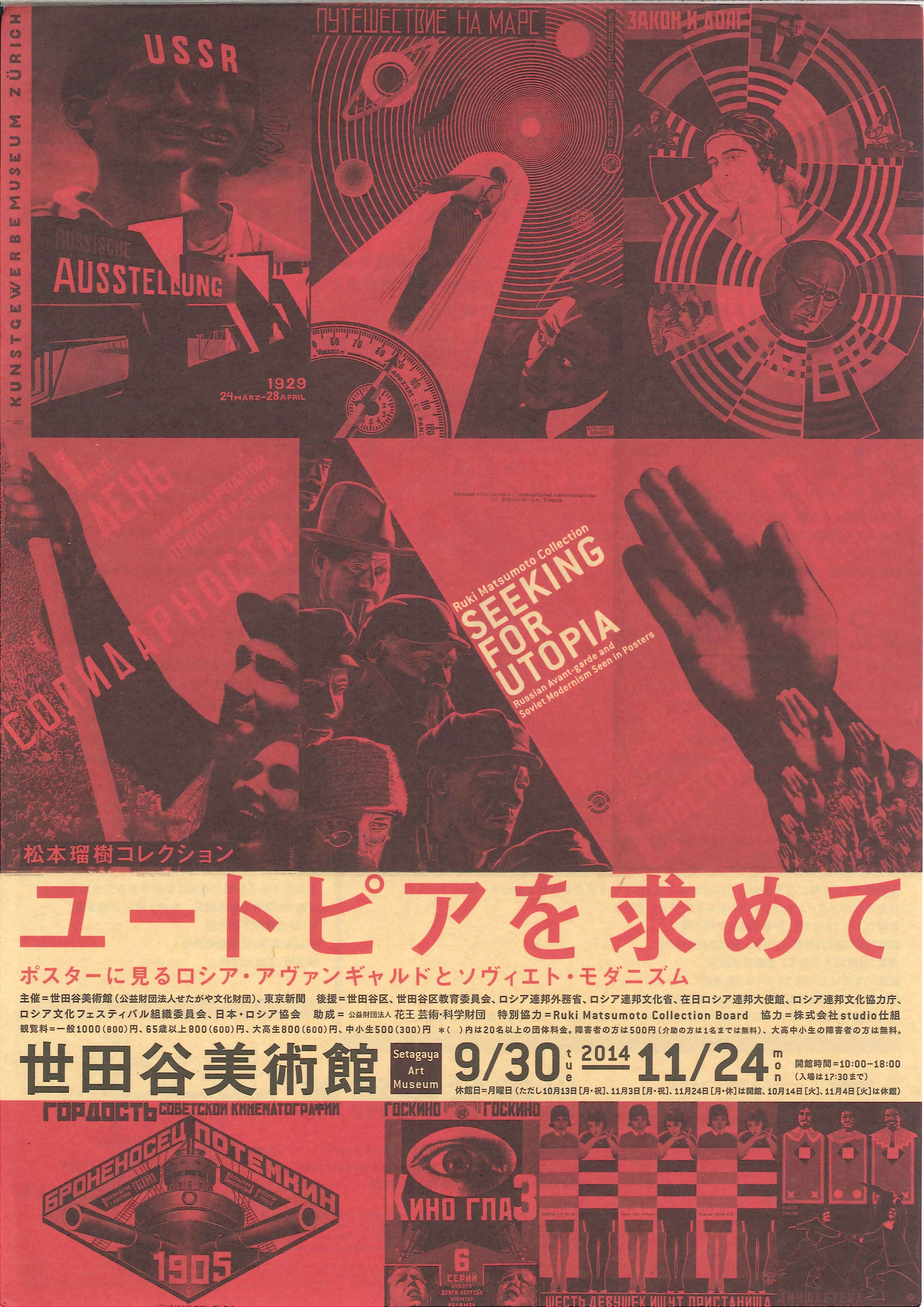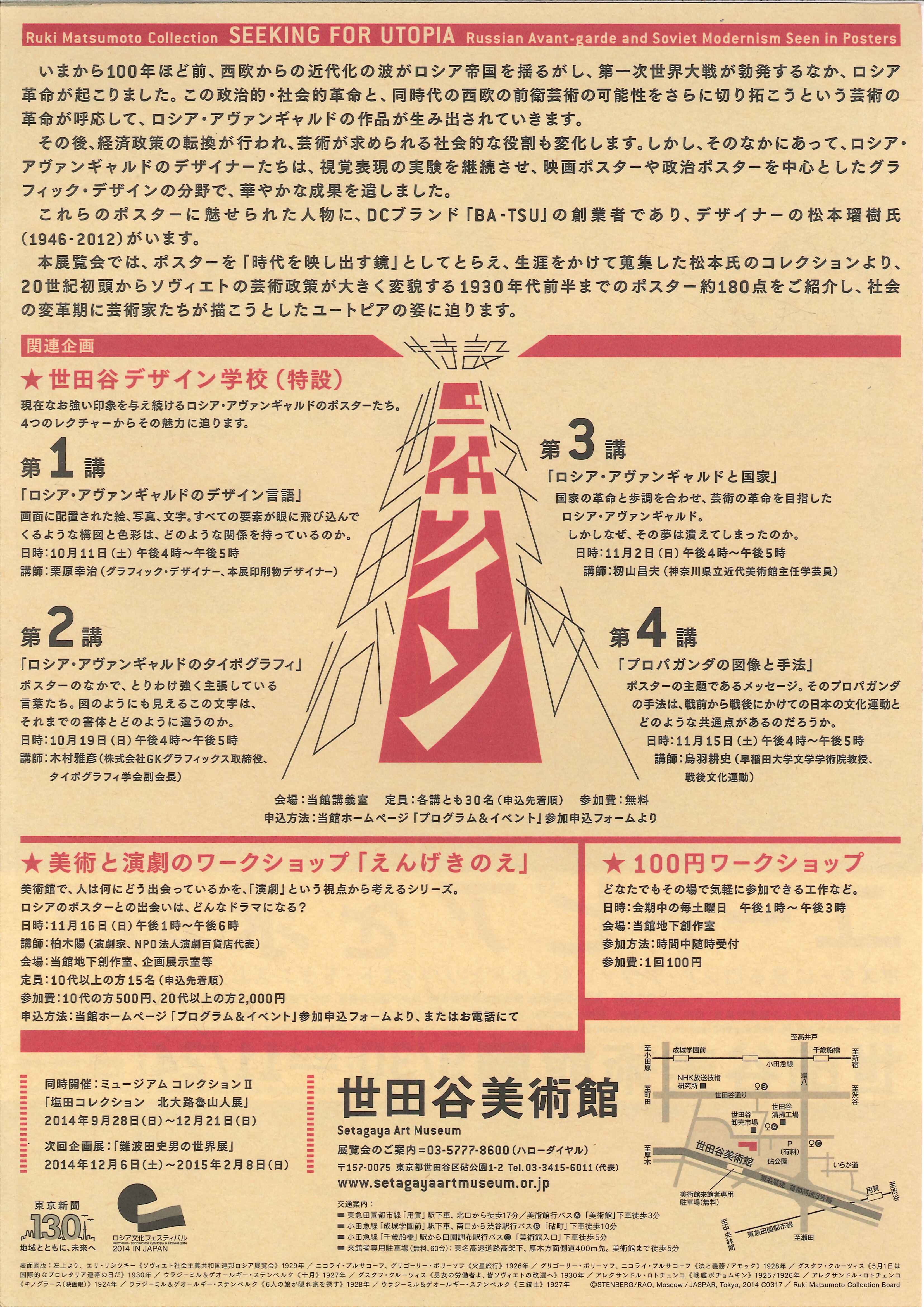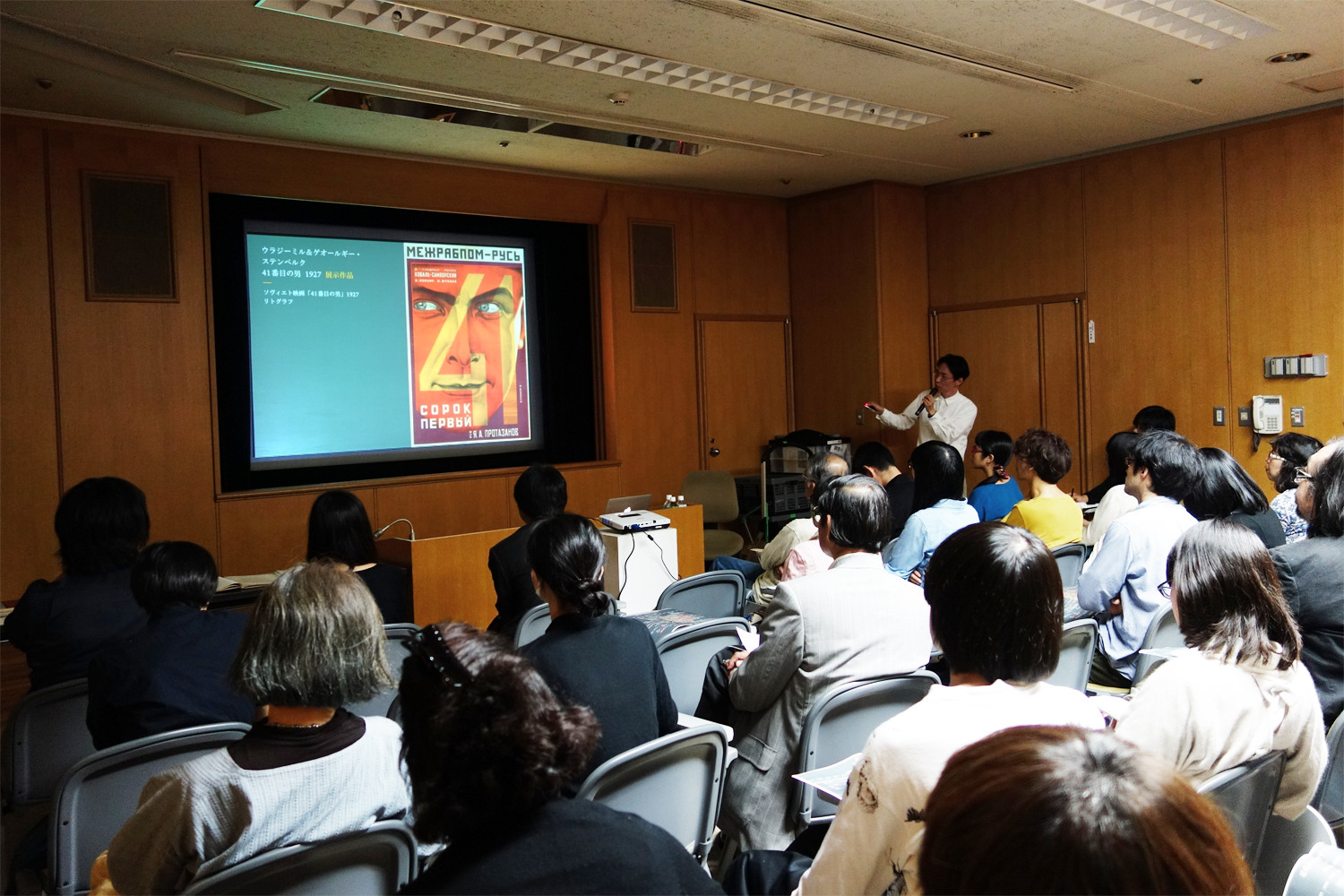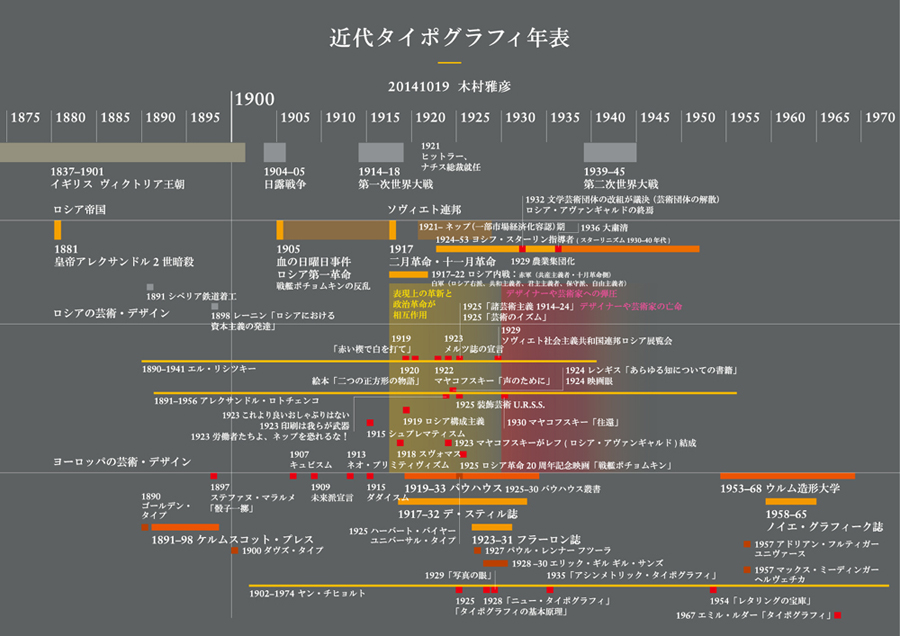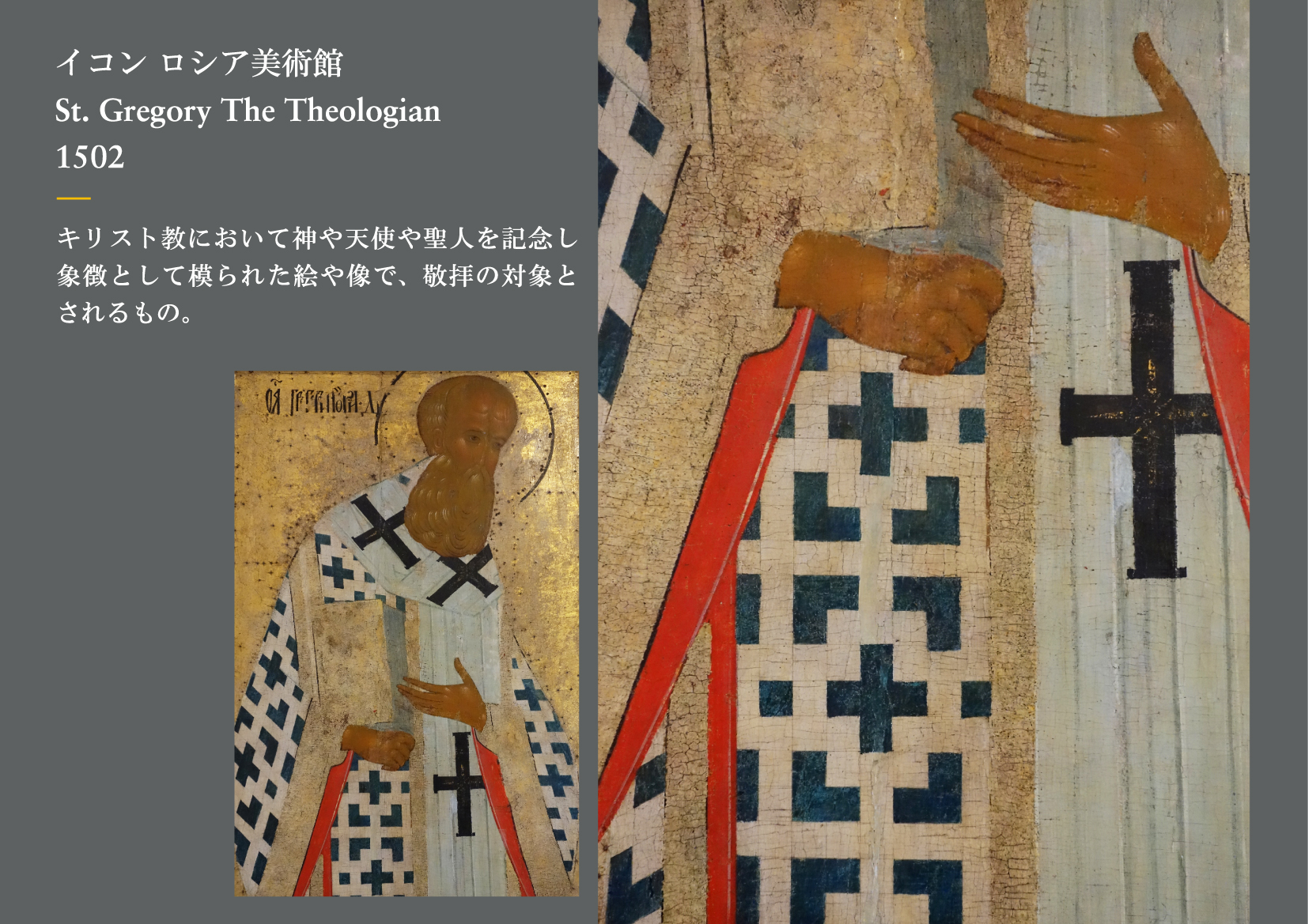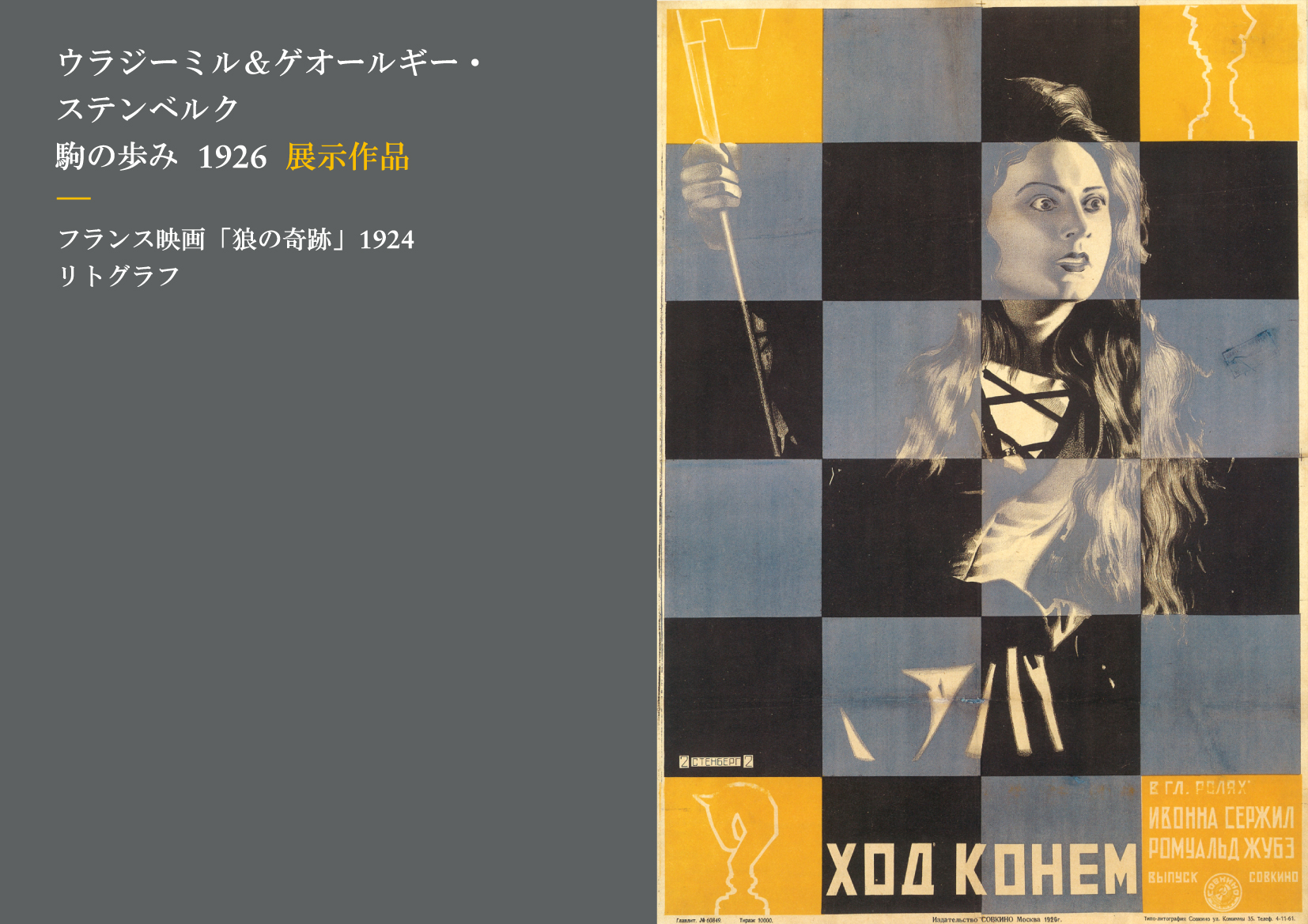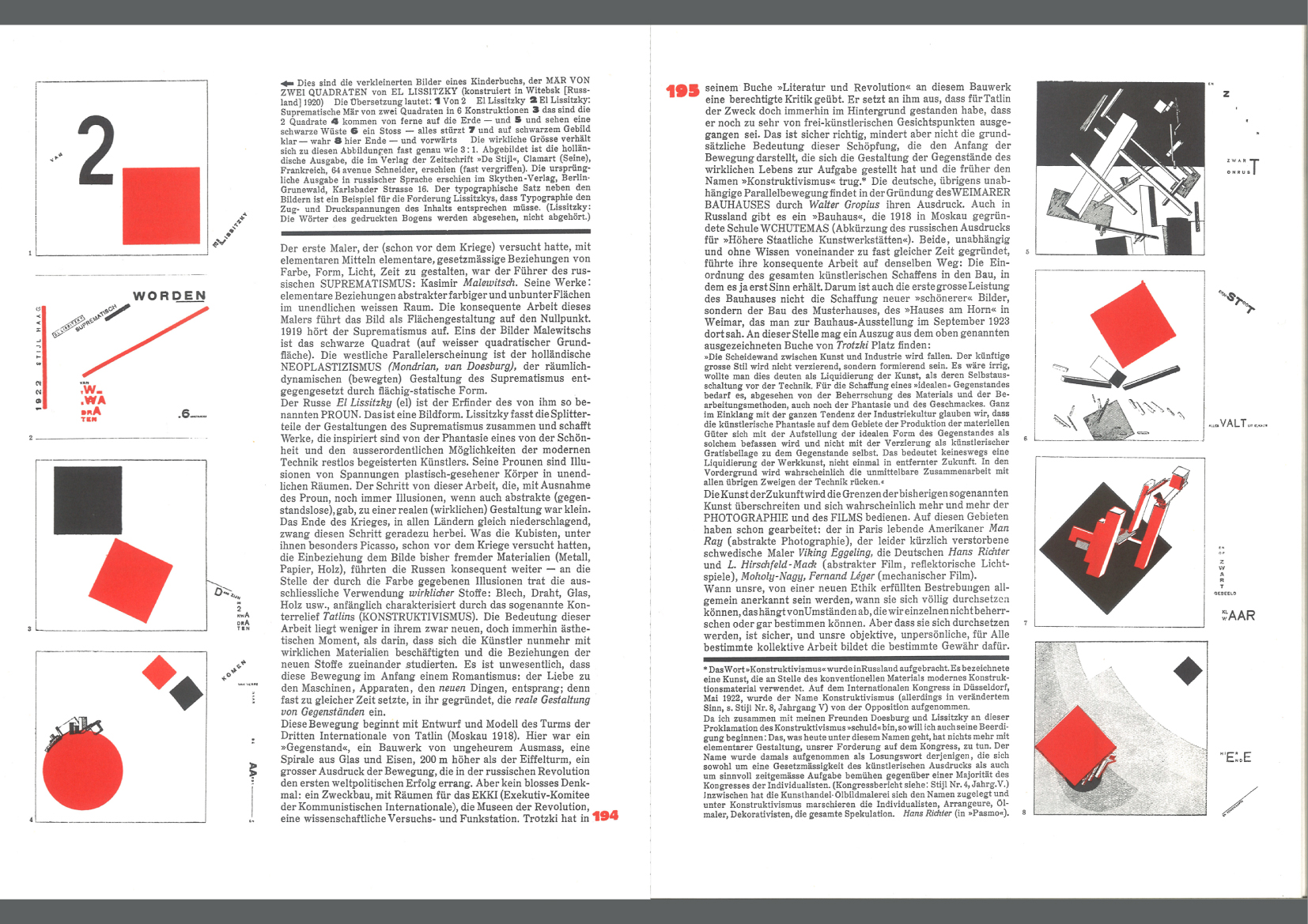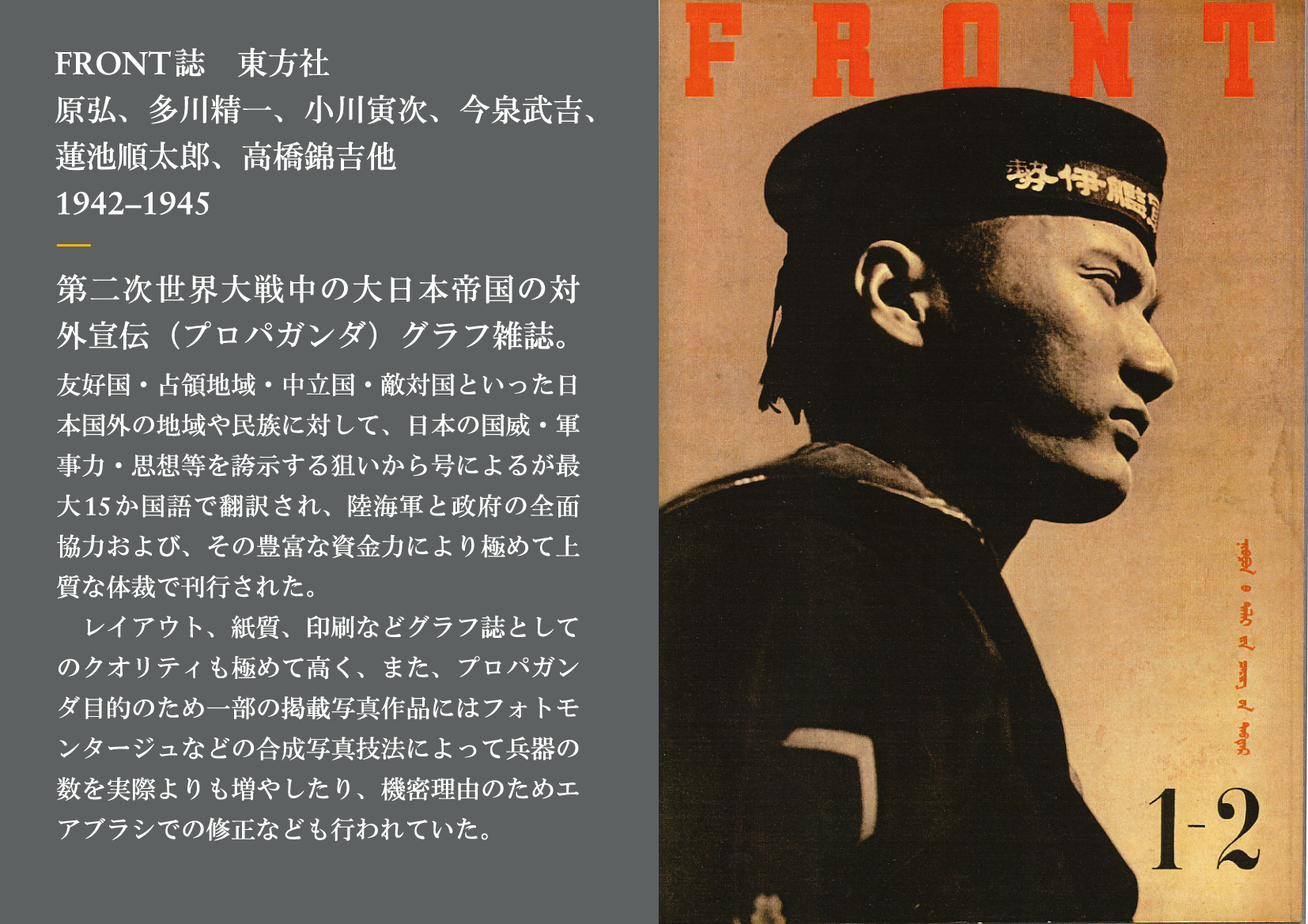世田谷美術館
企画展 民藝 MINGEI
― 美は暮らしのなかにある
会 期 2024年4月24日[水]- 6月30日[日]
会 場 世田谷美術館 1階・2階展示室
〠 157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 電 話 03-3415-6011
開館時間 10:00 - 18:00(入場は17:30まで)
休 館 日 毎週月曜日
観 覧 料 (個人)一 般 1200円 / 65歳以上 1000円 / 大高生 800円 / 中小生 500円
* チケット各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照
特別協力 日本民藝館
主 催 世田谷美術館(公益財団法人せたがや文化財団)、朝日新聞社、東映
──────────────────────────
 日々の暮らしで使われていた手仕事の品の「美」に注目した思想家・柳宗悦(1889-1961)は、無名の職人たちによる民衆的工藝を「民藝」と呼びました。
日々の暮らしで使われていた手仕事の品の「美」に注目した思想家・柳宗悦(1889-1961)は、無名の職人たちによる民衆的工藝を「民藝」と呼びました。
本展は、美しい民藝の品々を「衣・食・住」のテーマに沿って展示するほか、今も続く民藝の産地を訪ね、その作り手と、受け継がれている手仕事を紹介します。さらには現代のライフスタイルにおける民藝まで視野を広げ、その拡がりと現在、これからを展望します。
※ 土・日・祝日は多くのお客様がご来場されています。スムーズにご入場いただくには、事前のオンラインチケット購入をお勧めします。
※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。
[ 詳 細 : 世田谷美術館 感染症予防対応《ご来館の際のお願い》 本展特設ウエブサイト ]