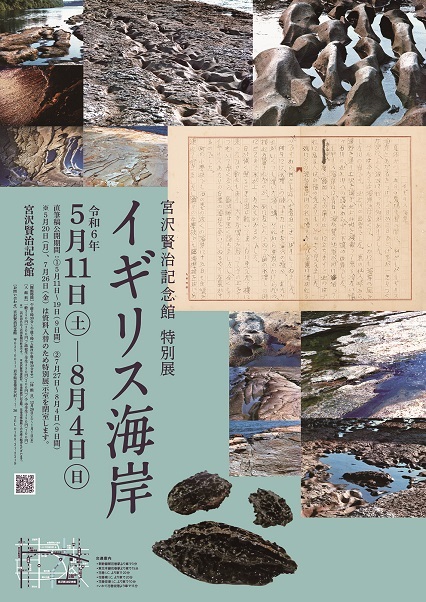草間彌生美術館
草間彌生、具象を描く
会 期 2024年4月27日[土]- 2024年9月1日[日]
会 場 草間彌生美術館
〠 162-0851 東京都新宿区弁天町107〔アクセス〕
開 館 日 木・金・土・日曜日 および 国民の祝日
休 館 日 月・火・水曜日
※展示替え期間や館内メンテナンス期間、年末年始などは休館となりますので、
事前に〔カレンダー〕で最新情報をご確認ください。
開館時間 11:00ー17:30
観 覧 料 一 般 1,100円、小中高生 600円
※ 税込金額を表示。未就学児は無料。団体割引の設定はございません。
──────────────
10代の頃の草間彌生のスケッチブックには、対象を的確に描きとめた動植物の写生が多く残されています。草間は単一モチーフの反復による抽象絵画でよく知られる作家ですが、活動初期に磨いた観察力と写生による具象的な作品表現は、彼女の創作活動の出発点であると同時に、幻視や内面のヴィジョンを具体的な形に表すものとして、その後もさまざまな変遷を遂げてきました。
本展は、1940年代から現在までに草間が制作してきた具象作品の多様な展開に着目いたします。渡米前のスケッチや日本画をはじめ、70-90年代に集中的に取り組んでいたコラージュ、1979年に着手して以降おびただしい点数を手がけている版画などには、具象的な描写が多く見られます。本展ではそれらの中に頻出する動植物や日用品といった親しみやすい身近なモチーフの作品をご紹介いたします。2000年以降に手がける近年の草間の画業を代表する絵画連作からは、自画像や不思議な人物像が大小さまざまなキャンバスに自由奔放に描かれた作品群を展覧。横顔や目といった、あるひとつの具象的なイメージが全体を埋め尽くすように繰り返し描かれることによって、オールオーヴァーな抽象絵画に限りなく近い様相を成しているのも草間作品の特色です。草間が最も好む主題のひとつであるかぼちゃモチーフからは、当館の開館を記念して制作したミラールームのインスタレーションと、大型の彫刻を展示いたします。さらに、1960年代に初めて発表したボートを用いたソフト・スカルプチュアの最新作を世界初公開いたします。
※ チケットは美術館ウェブサイトのみで販売。美術館窓口では販売しておりません〔アクセス〕
※ 入場は日時指定の完全予約・定員制(各回90分)です。下掲詳細にて十分に確認を。
※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上参観を。
[ 詳細 : 草間彌生美術館 TOP 草間彌生美術館 HOME ]











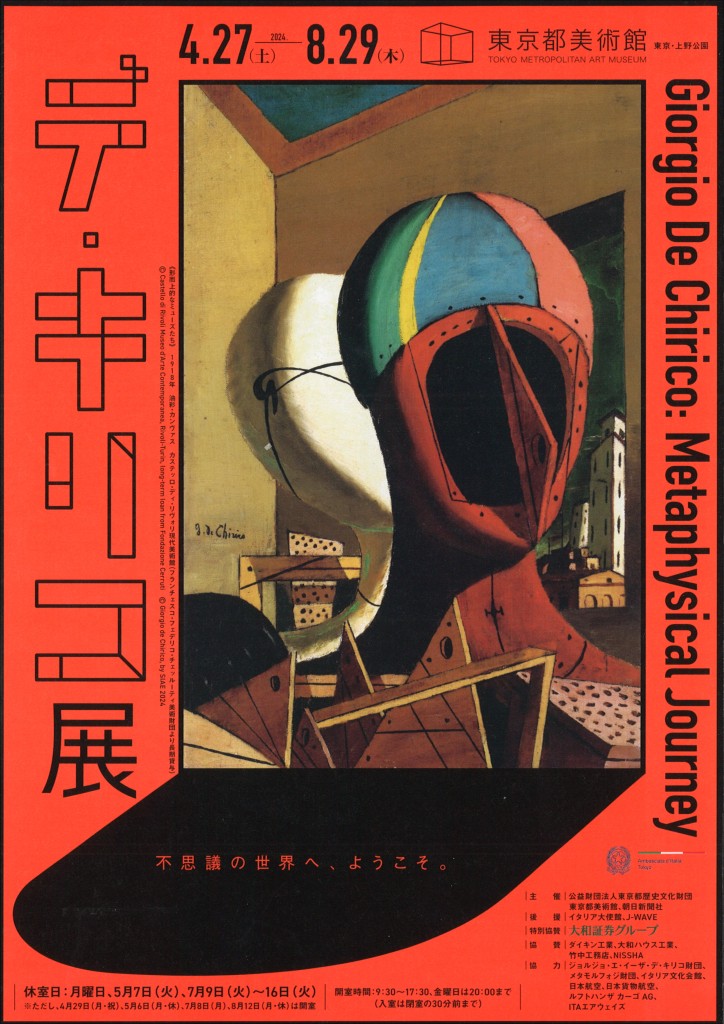

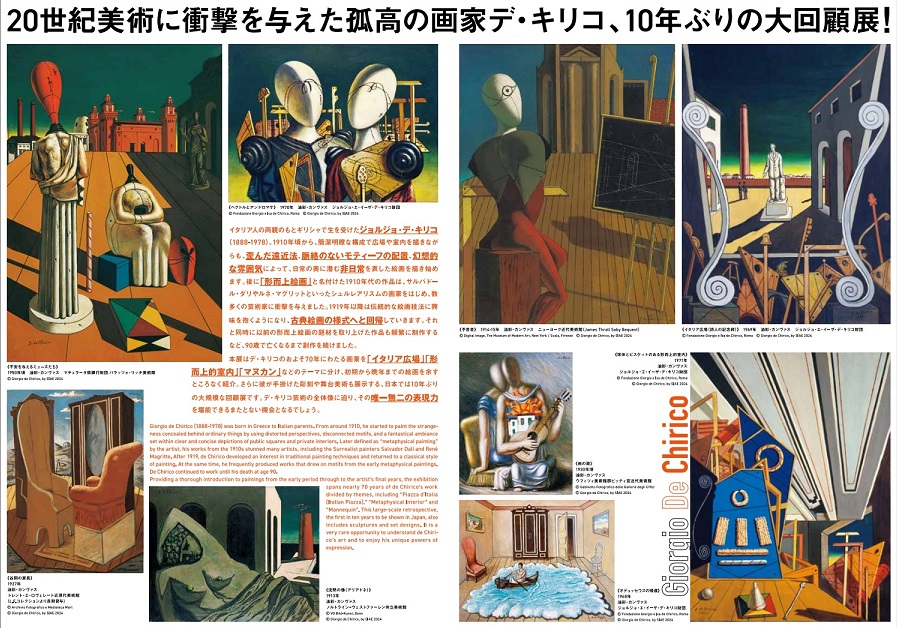













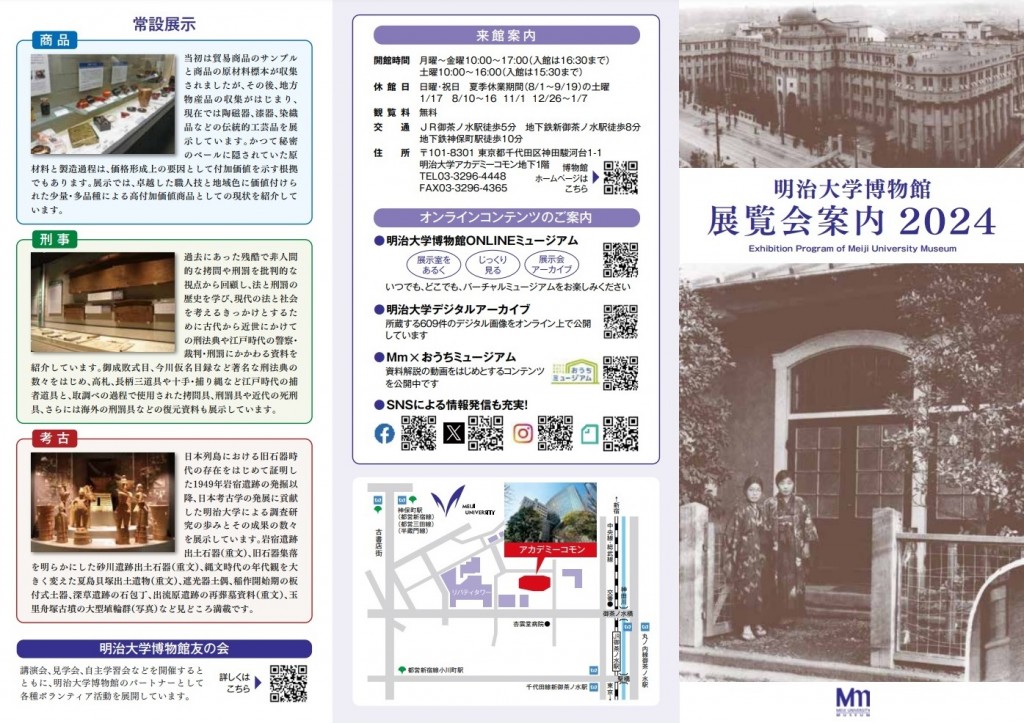
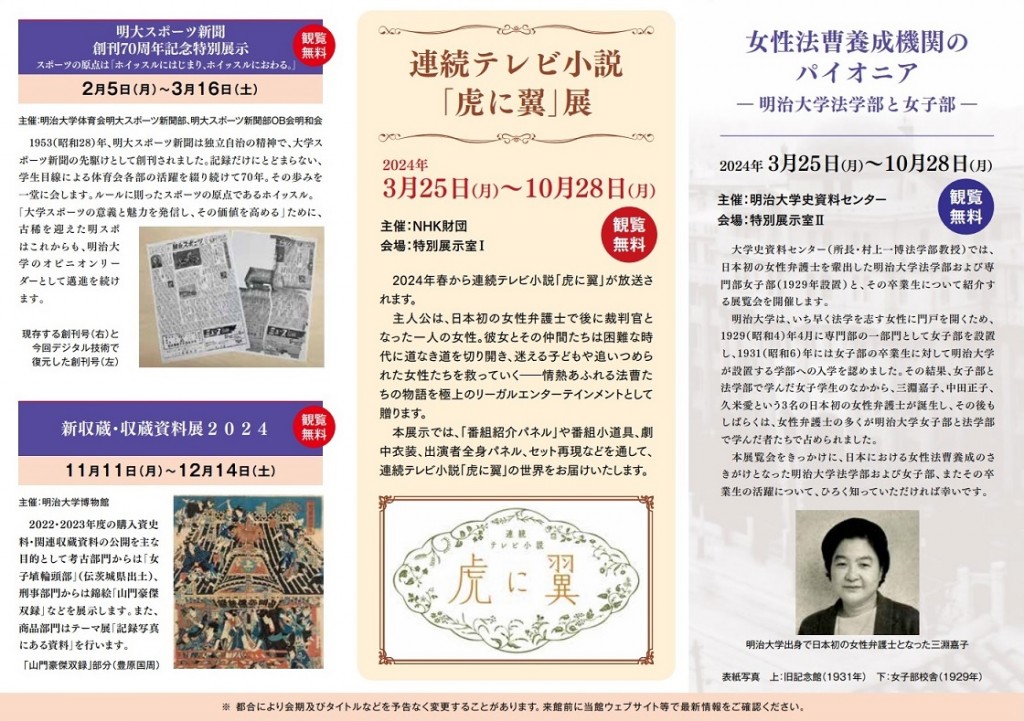




 アートスペース88
アートスペース88















 ☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆
☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆