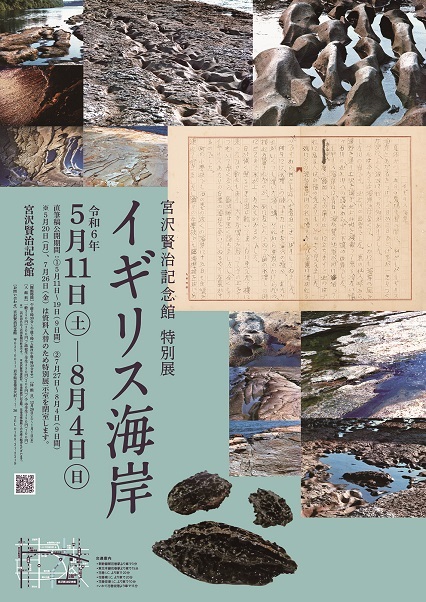大倉集古館
特別展
大成建設コレクション もうひとりのル・コルビュジエ ── 絵画をめぐって
会 期 2024年6月25日[火]- 8月12日[月・祝]
開館時間 10:00 - 17:00(入館は 16:30 まで)
* 毎週金曜日は 19:00 まで開館、入館は 18:30 まで
休 館 日 毎週月曜日
入 館 料 一 般:1,500円、 大学生・高校生:1,000円 * 学生証を提示、中学生以下:無 料
* 各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細「利用案内」参照
会 場 大倉集古館 展示室
〠 105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-3(The Okura Tokyo 前)
TEL : 03-5575-5711(代表) FAX:03-5575-5712
主 催 公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館
──────────────────────
まもなく没後60年を迎える建築家ル・コルビュジエは、20世紀を代表する建築家として知られていますが、同時に数多くの美術作品を残したアーティストでもあります。
本展では、世界有数の点数を有する大成建設のル・コルビュジエ・コレクションの中から、美術作家としての業績を紹介いたします。彼の素描やパピエ・コレがまとまって公開されるのはおよそ30年ぶりとなります。
※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。
[ 詳 細 : 大倉集古館 ] { 活版アラカルト 過去ログまとめ }


















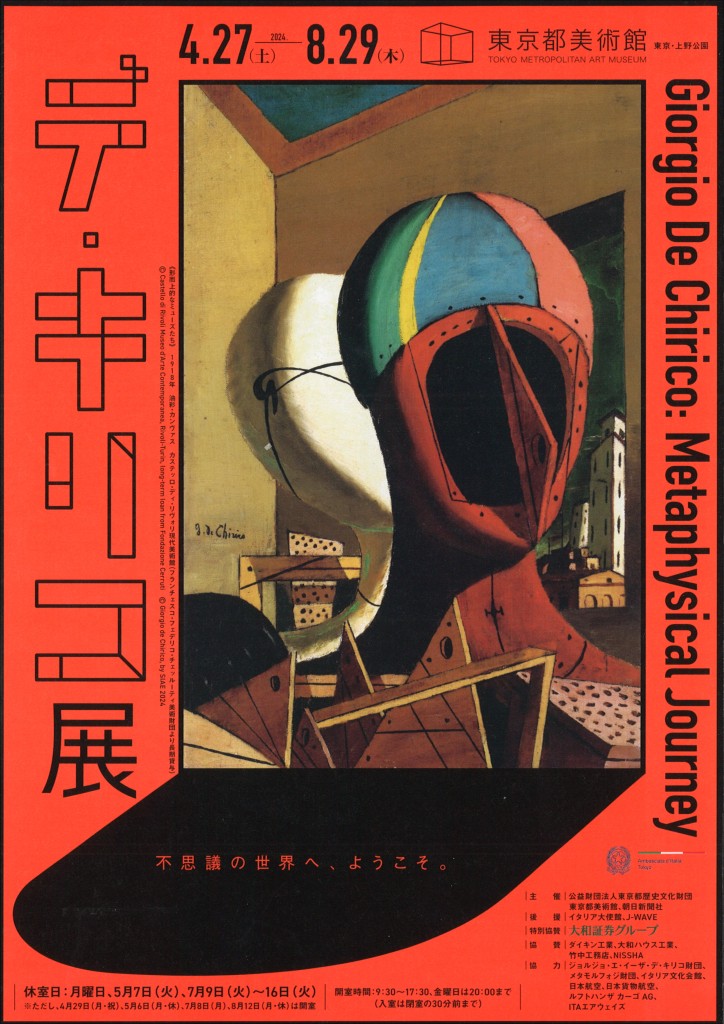

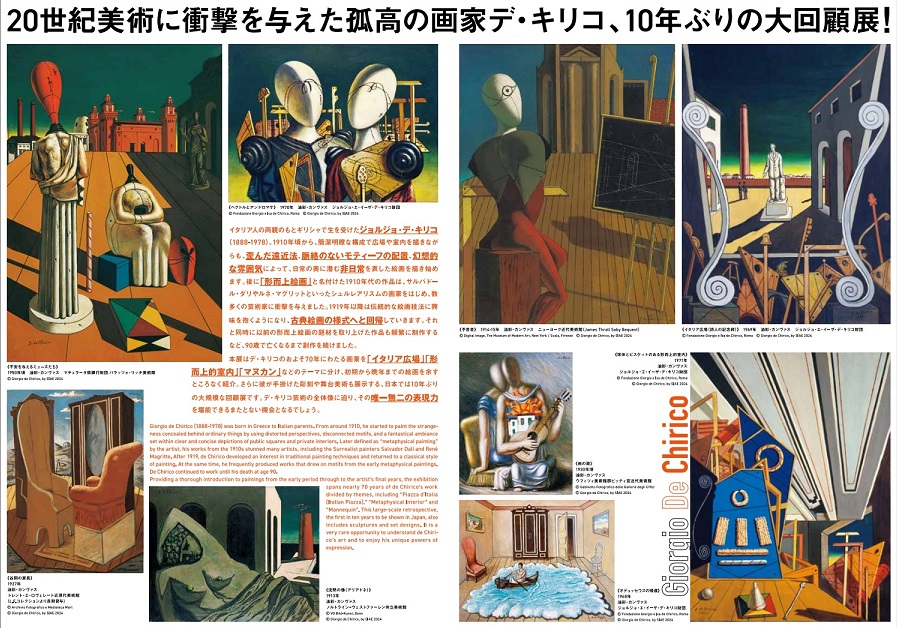













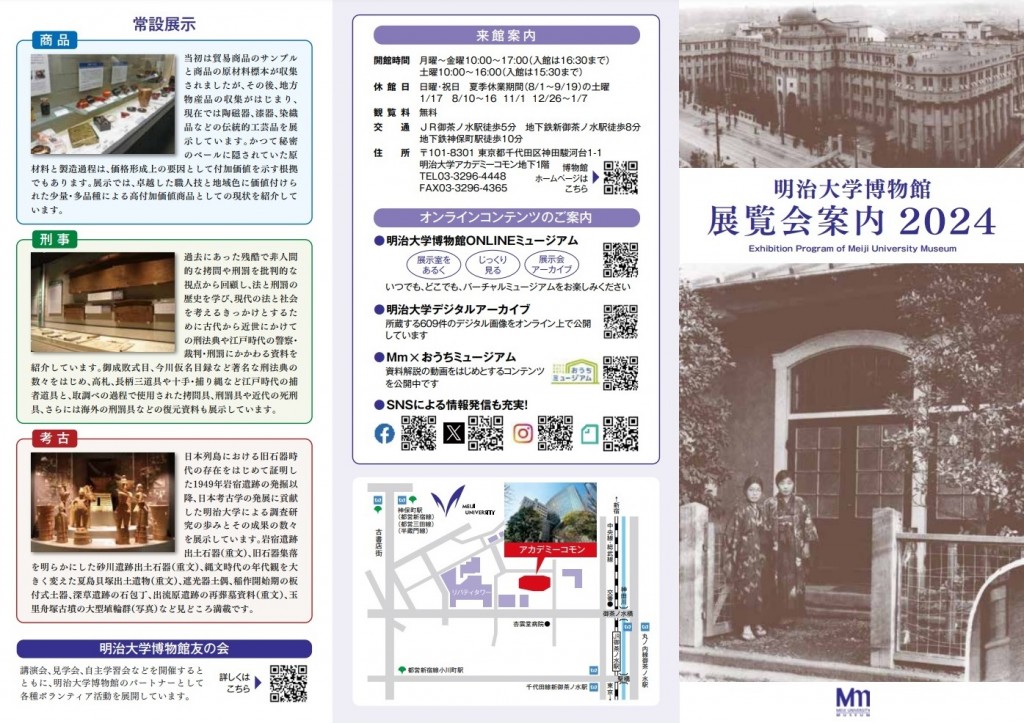
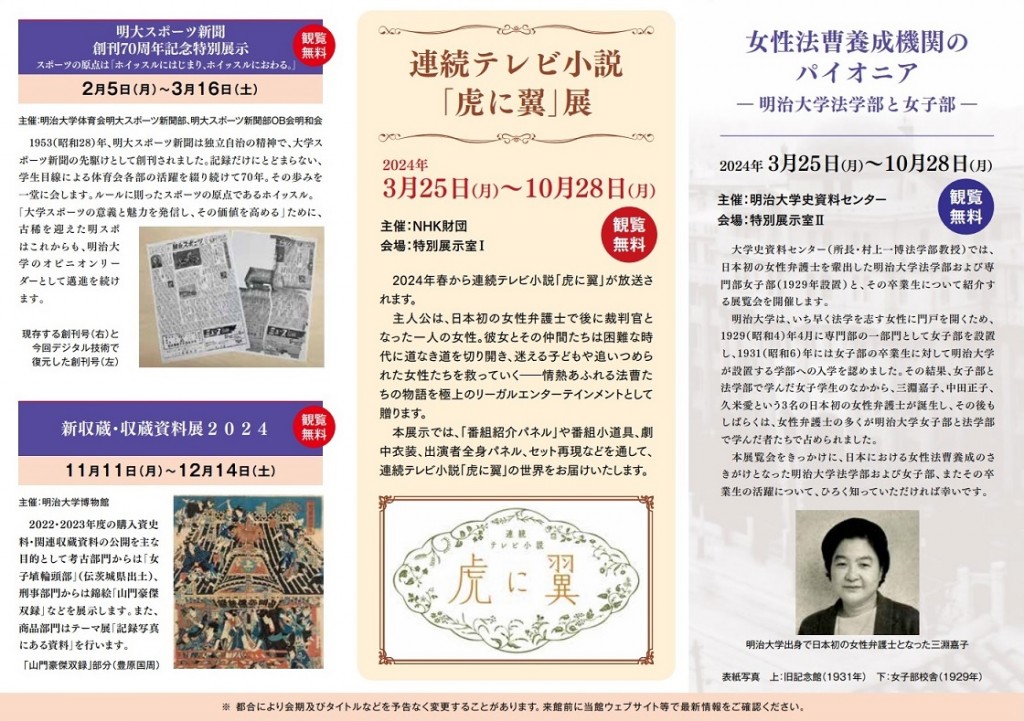




 アートスペース88
アートスペース88













 ☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆
☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆