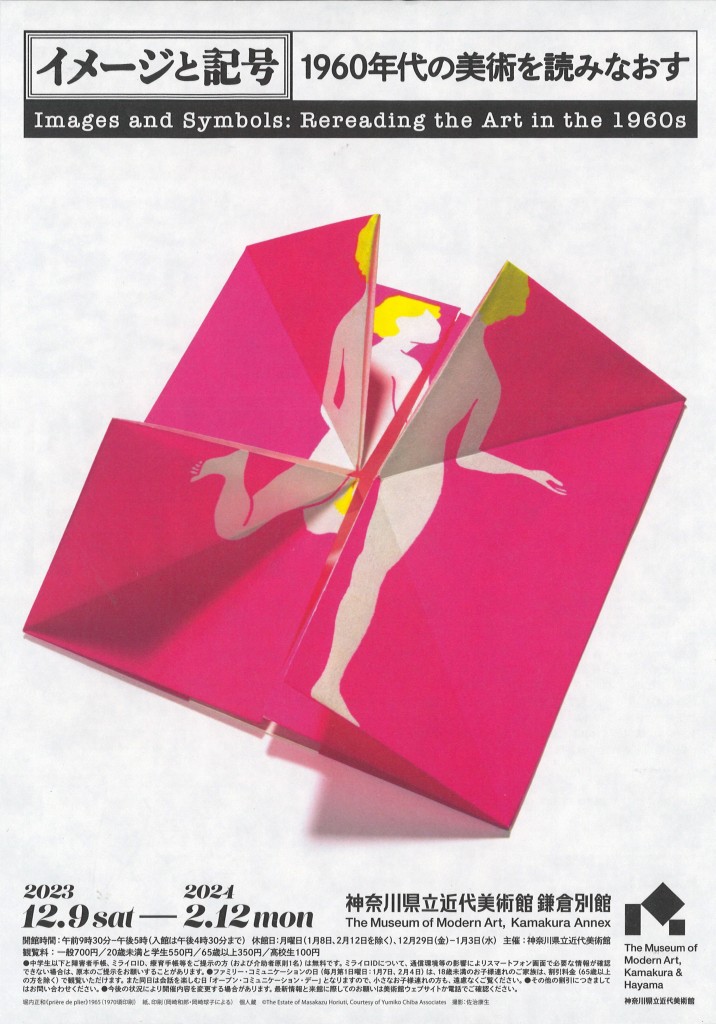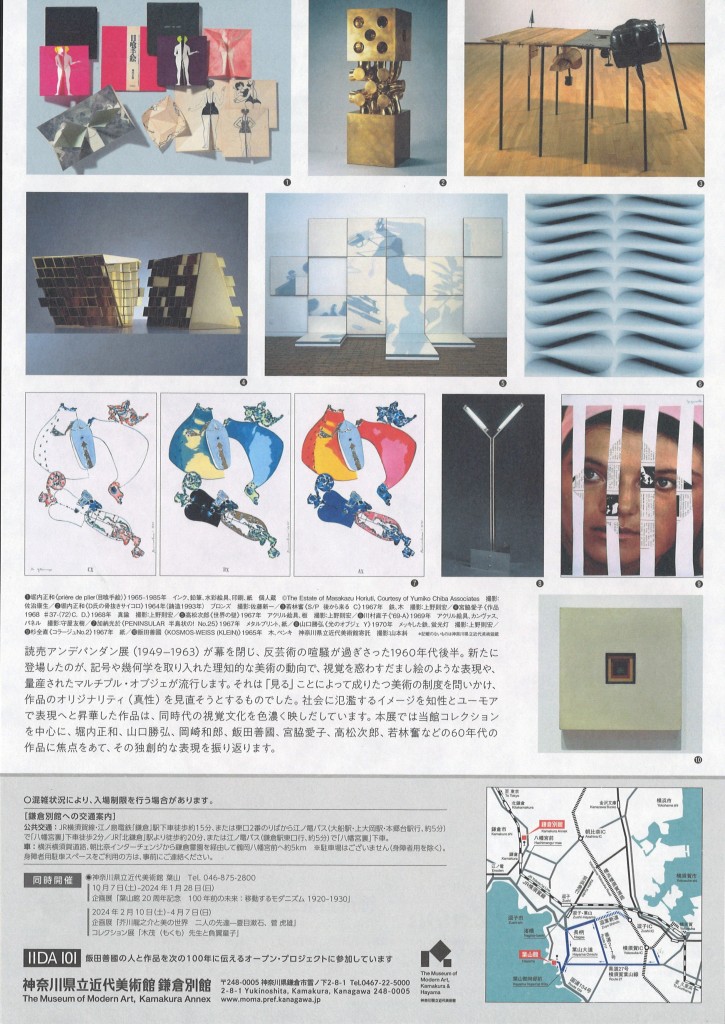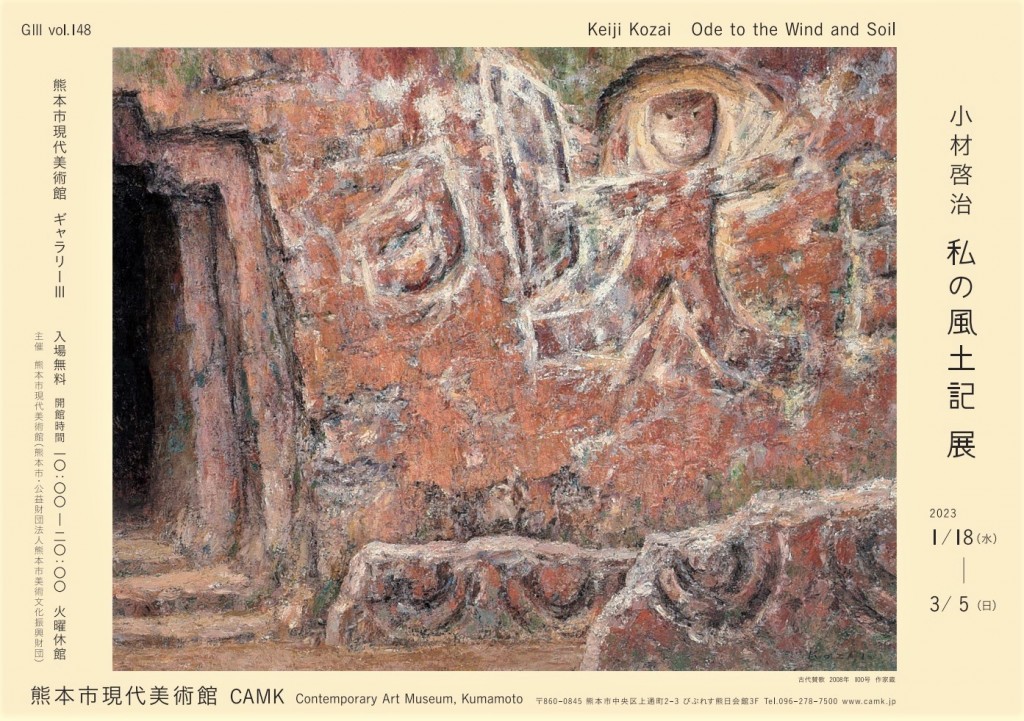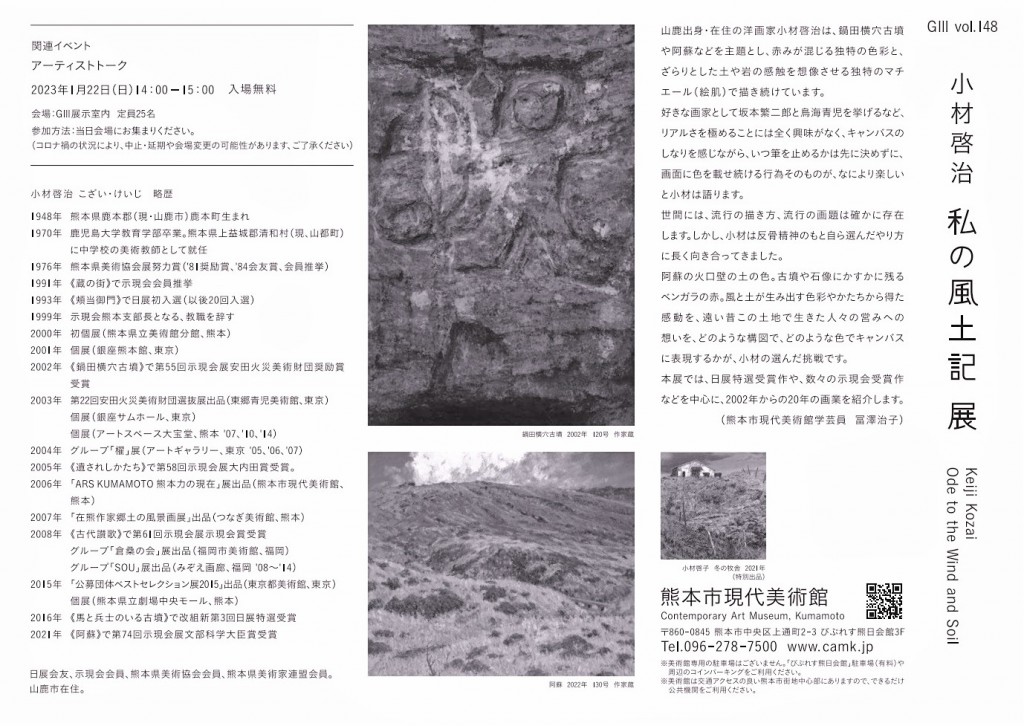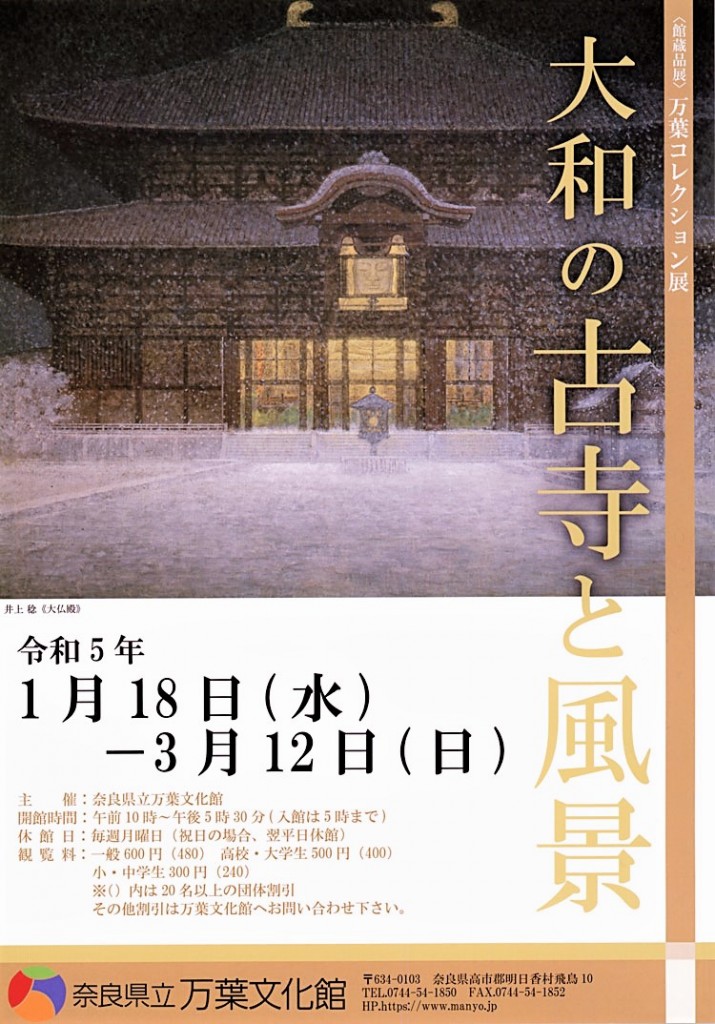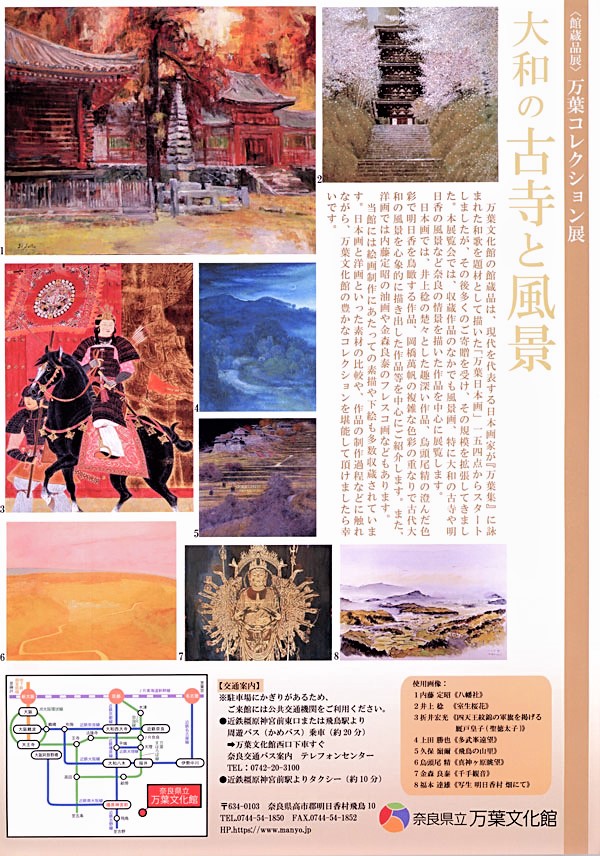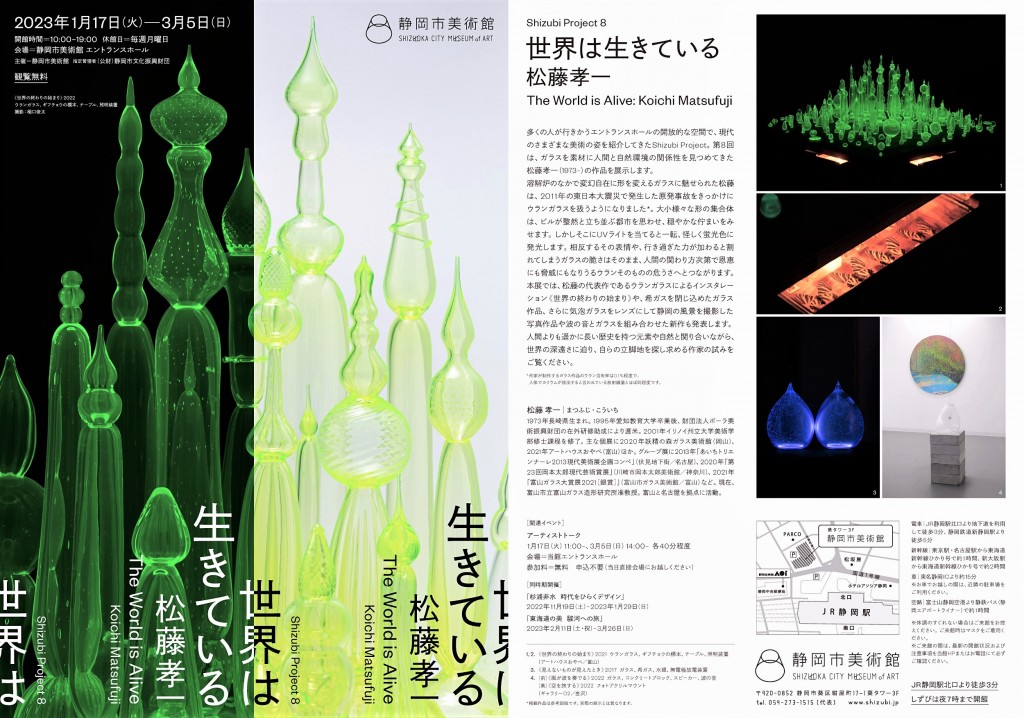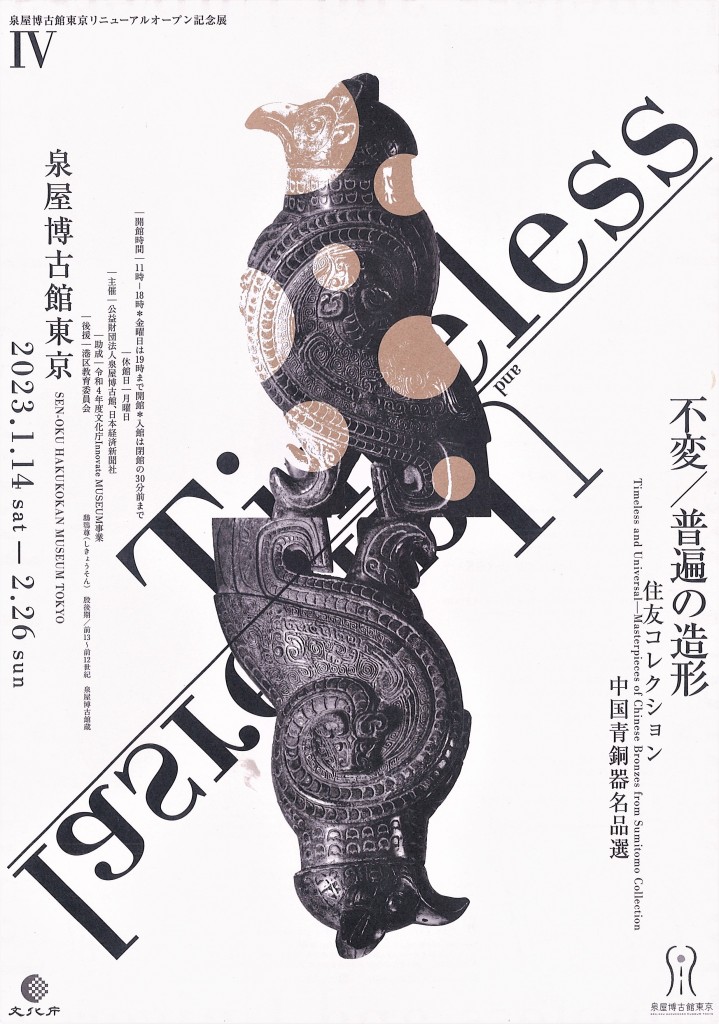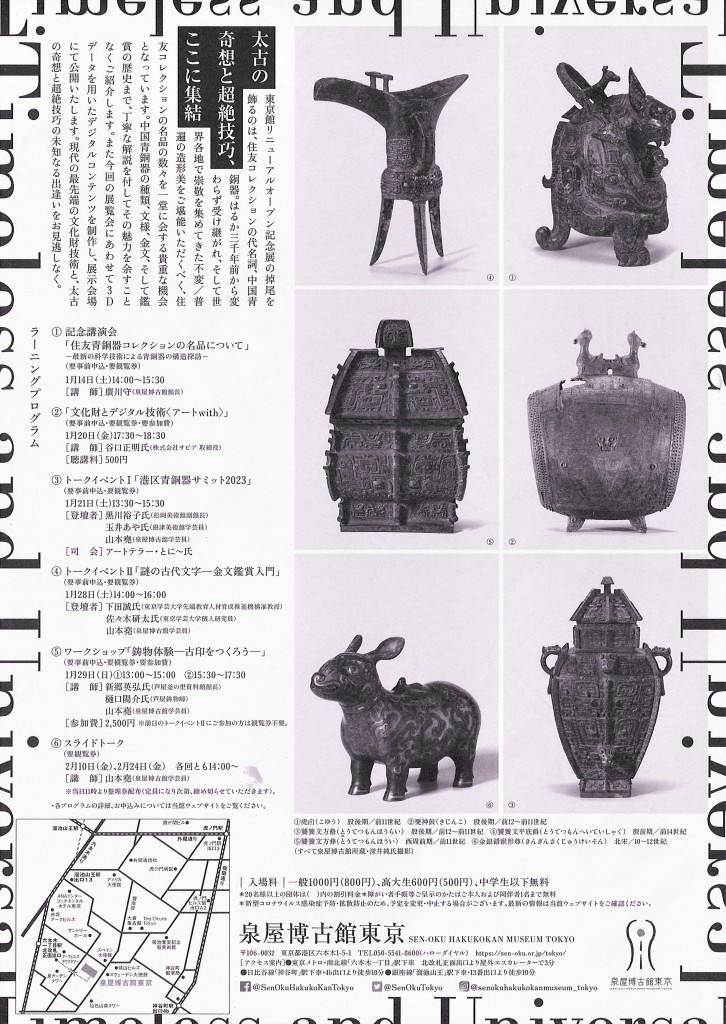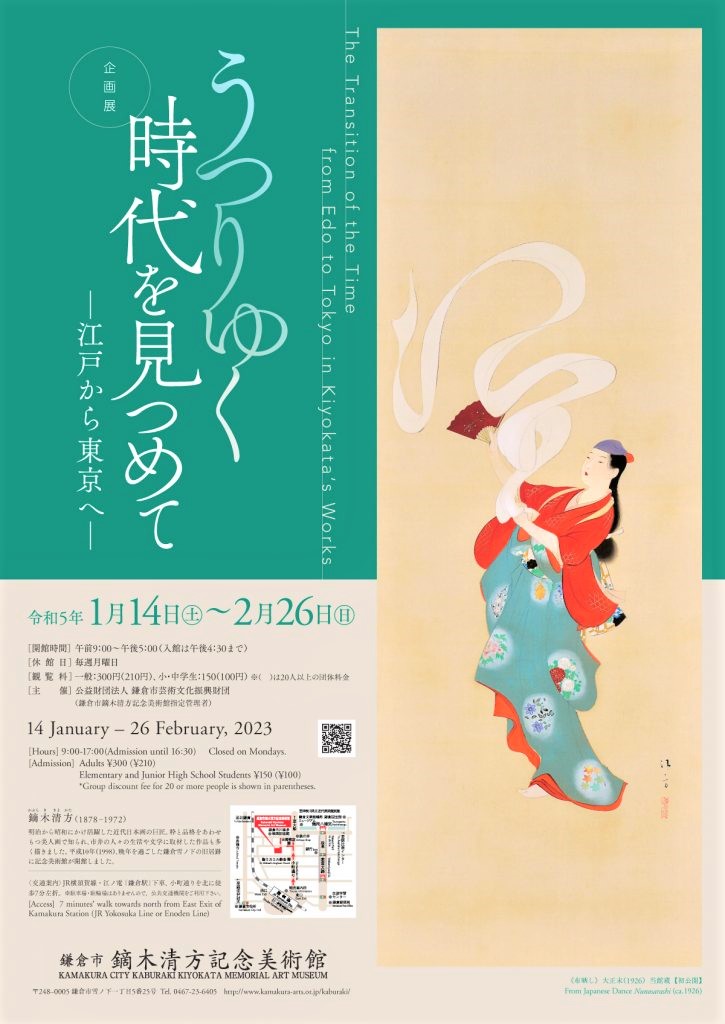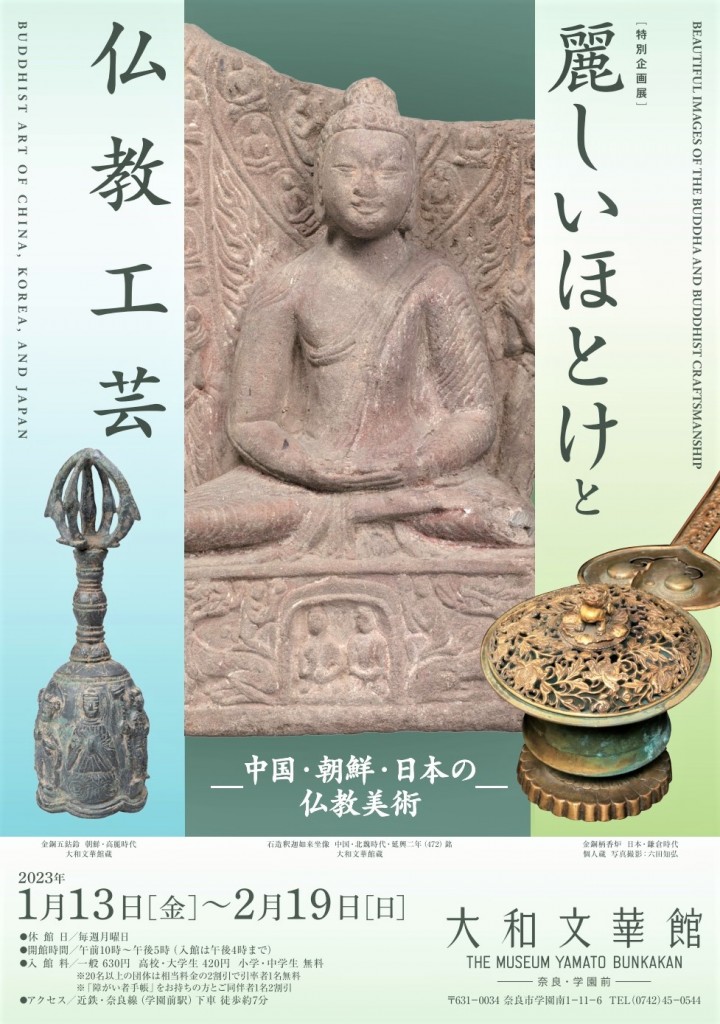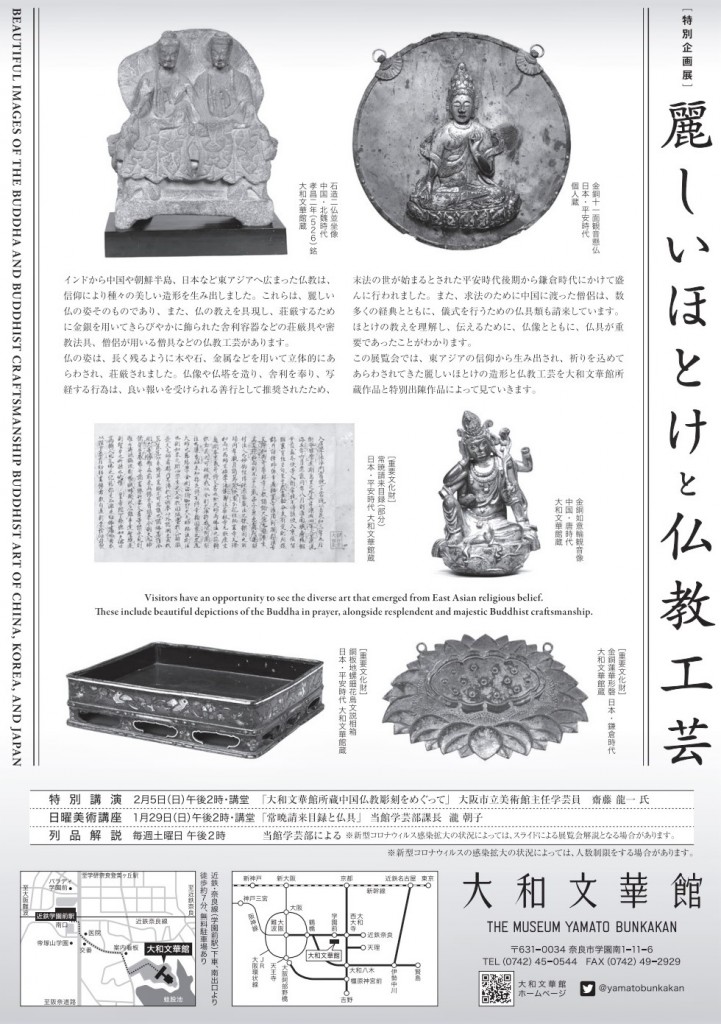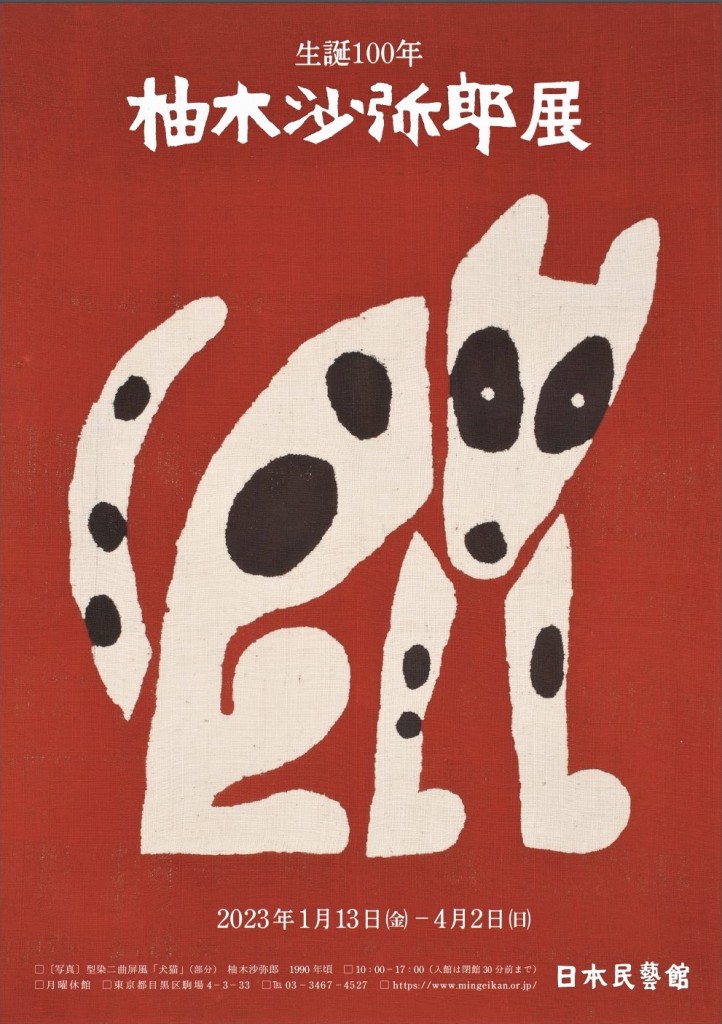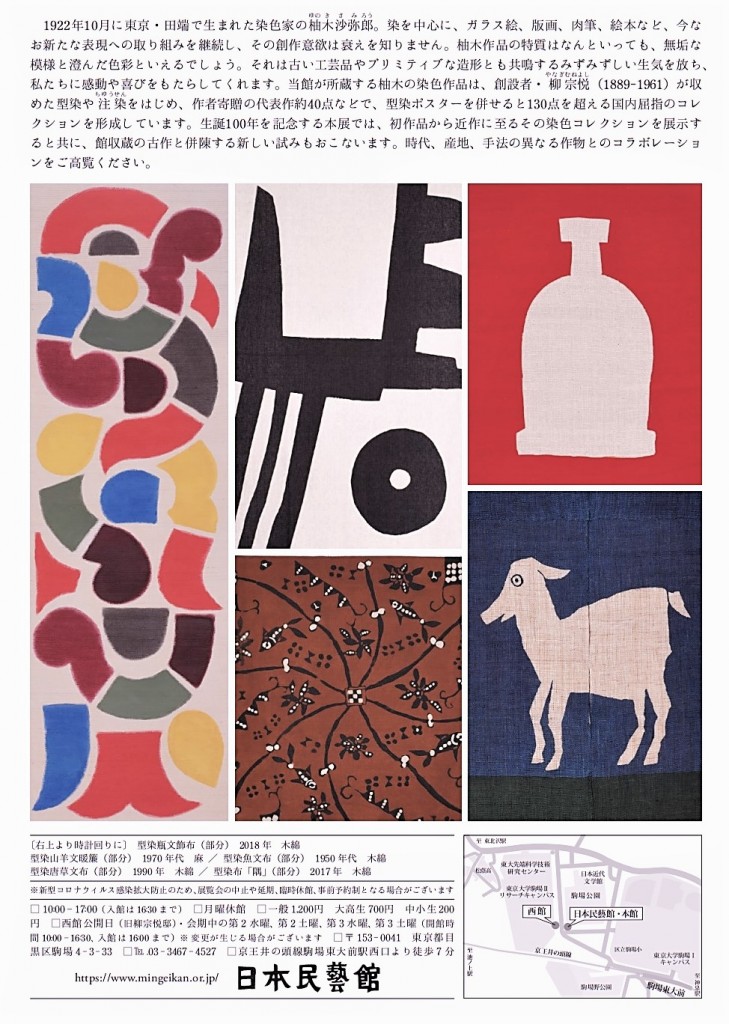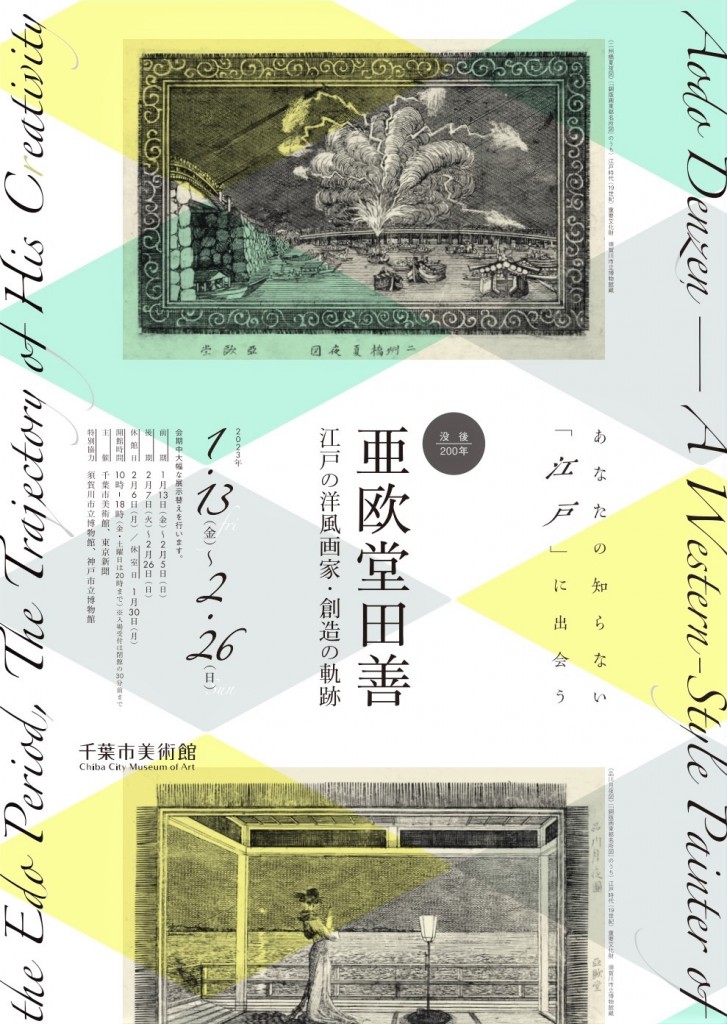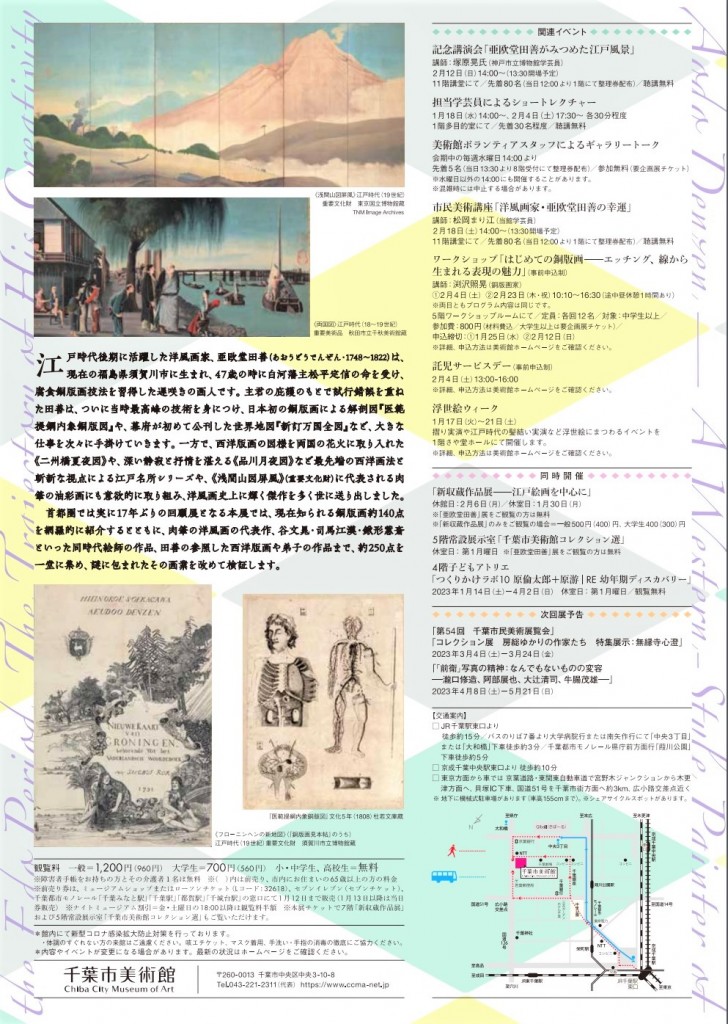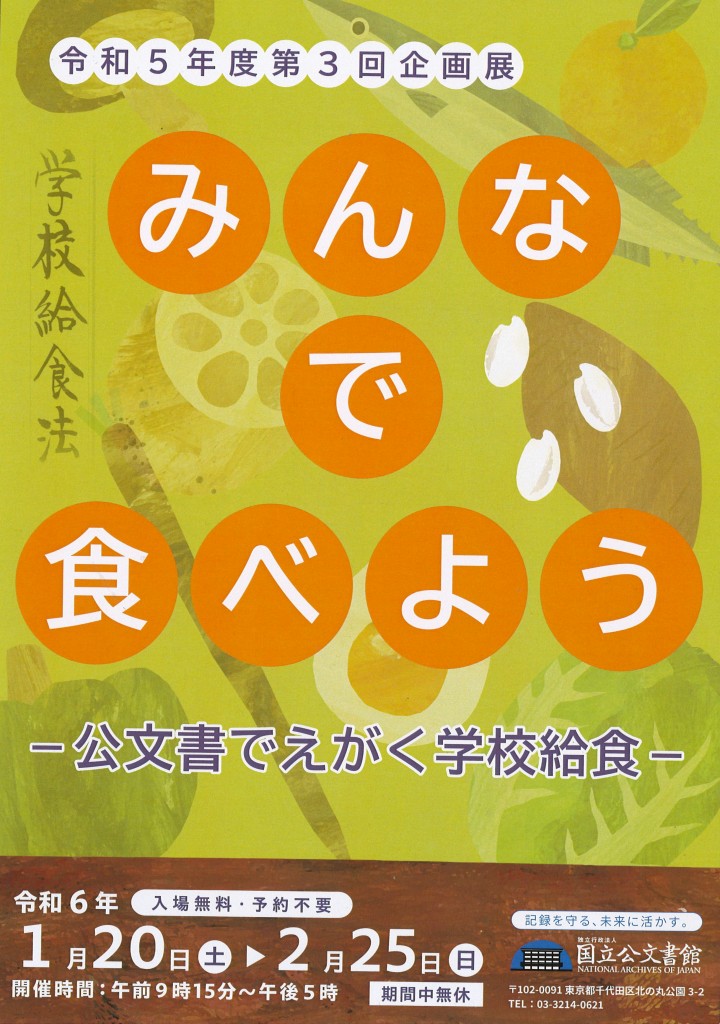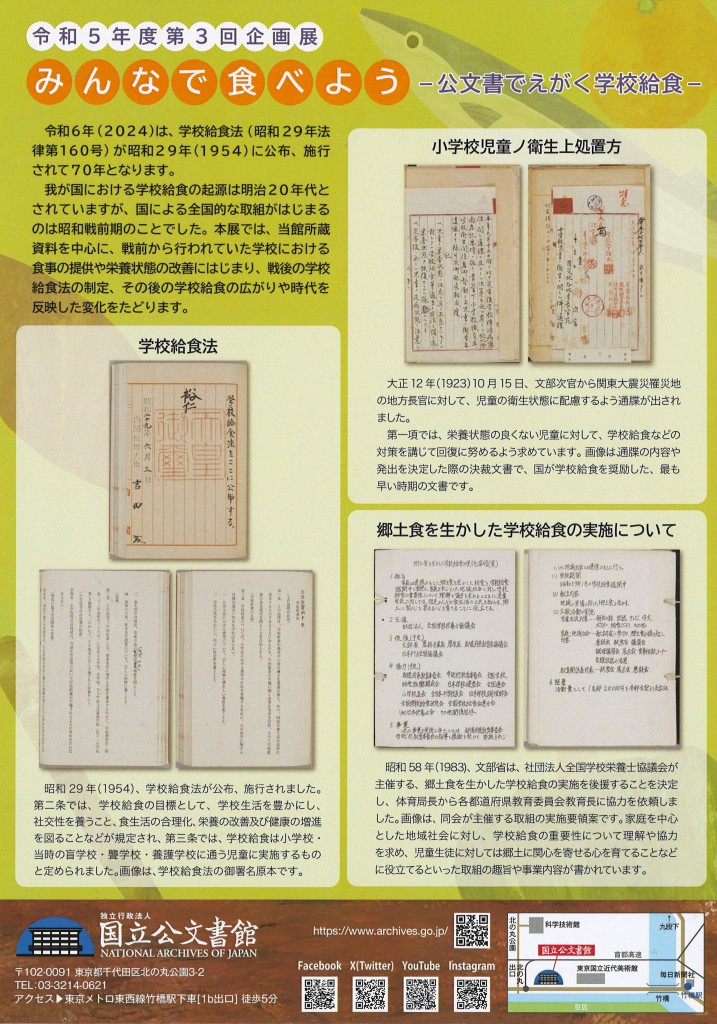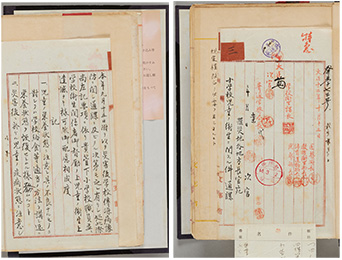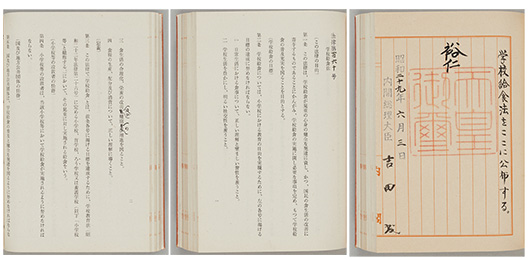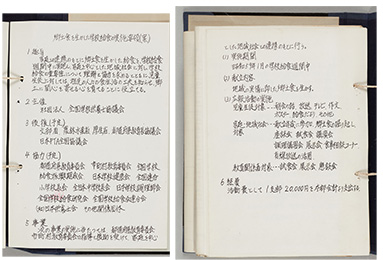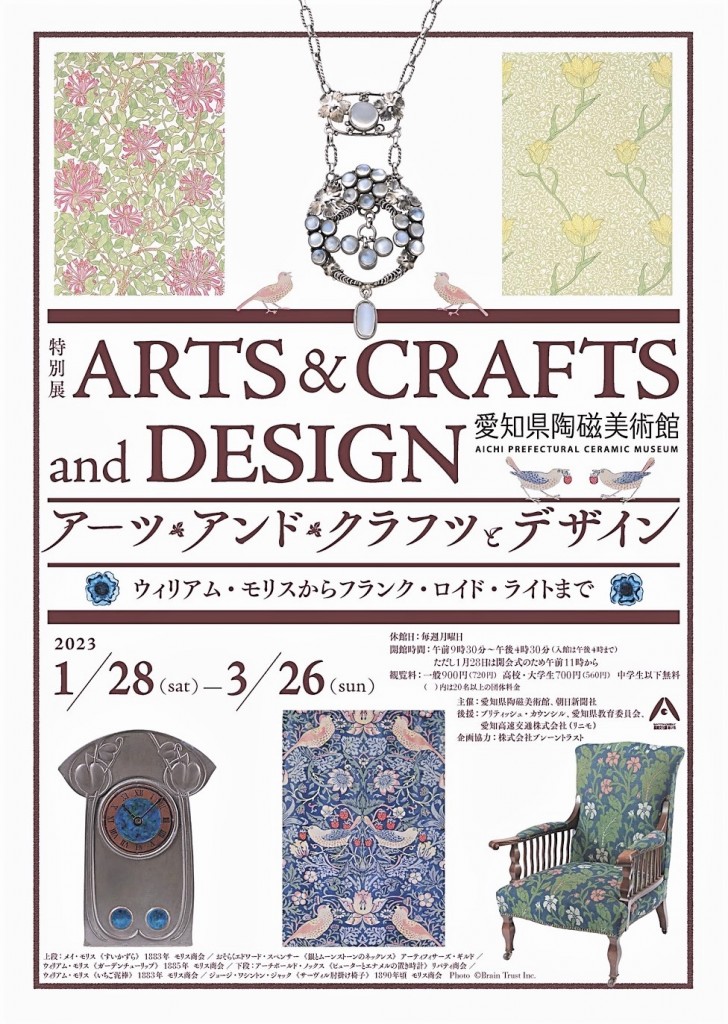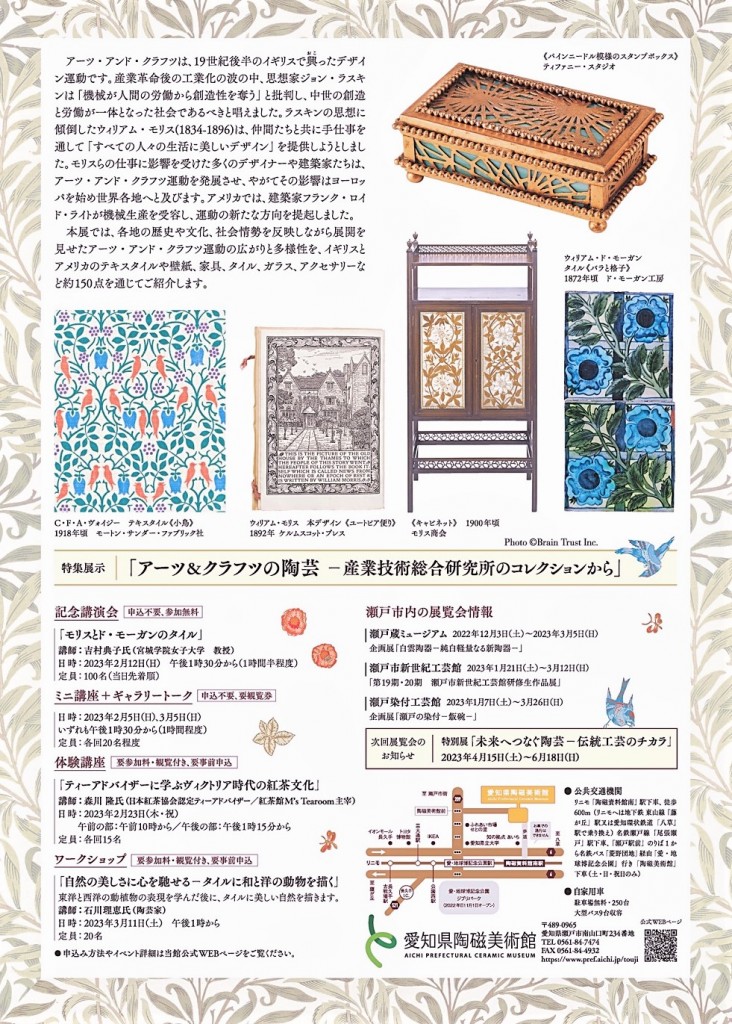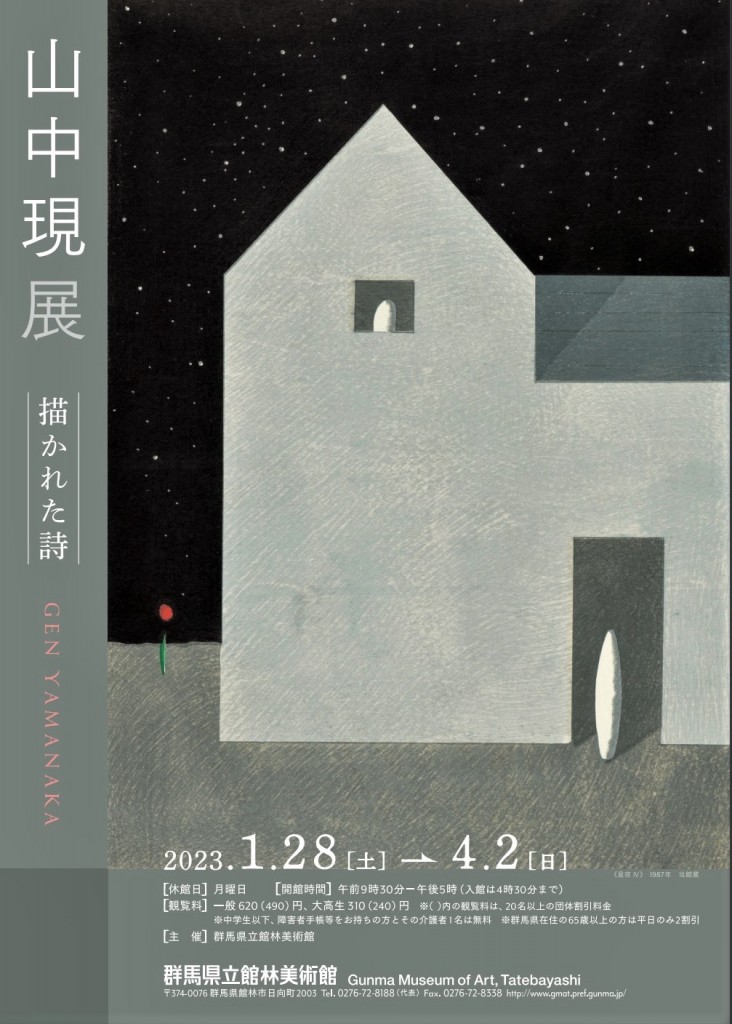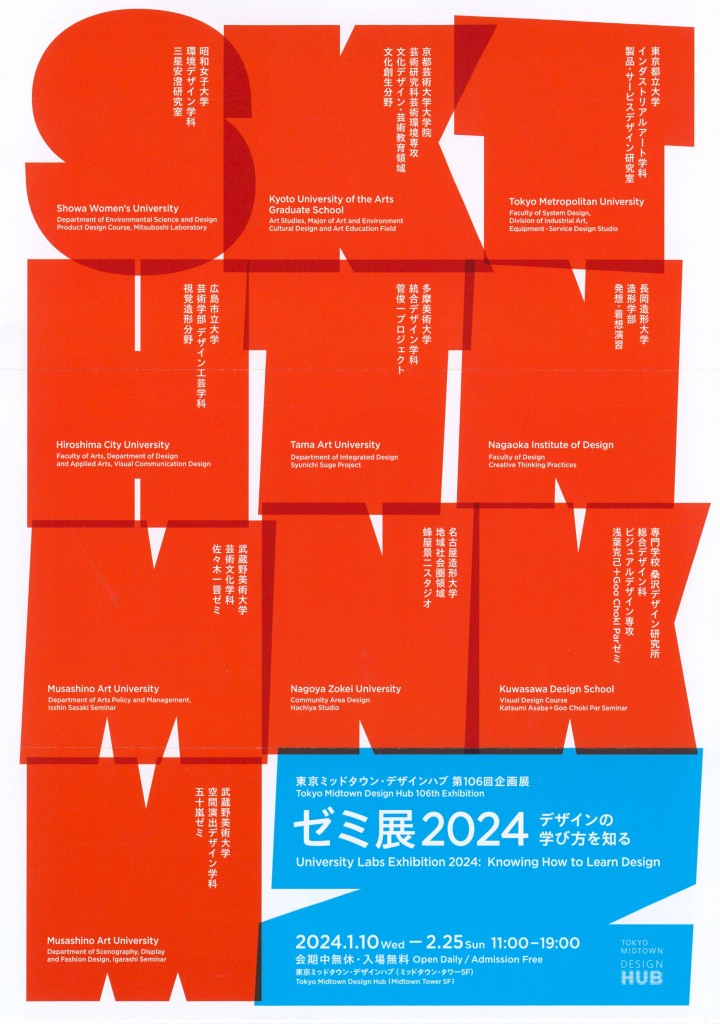書道博物館
東京国立博物館/台東区立書道博物館 連携企画20周年
王羲之と蘭亭序
会 期 2023年1月31日[火]- 4月23日[日]
会期中、一部展示替えがあります。
前 期 1月31日[火]- 3月12日[日]
後 期 3月14日[火]- 4月23日[日]
会 場 台東区立書道博物館
110-0003 台東区根岸2丁目10番4号 電話 03-3872-2645
観 覧 料 一 般・大学生 500円、 高、中、小学生 250円
開館時間 午前9時30分-午後4時30分(入館は4時まで)
休 館 日 月曜日
主 催 (公財)台東区芸術文化財団
────────────────────
魏晋時代は書が芸術として自覚され、多<の能書が輩出しました。なかでも東晋時代に活躍した王羲之(303-361)は、その最晩年に伝統の束縛から離れ、普遍的な美しさを備えた先進的な書法を獲得し、のちに 書聖 と崇められています。
永和9年(353)3月3日、王羲之は会稽山陰(浙江省紹興市)の 蘭亭 に、名士を招いて 流觴曲水 (りゅうしょう きょくすい)の雅宴を催し、宴で詠まれた詩集の序文を揮毫しました。これが世に名高い「 蘭亭序 」です。人生への深い洞察を吐露した 蘭亭序 は、詩酒に興じた序文の草稿でしたが、王羲之も認める最高傑作となりました。
王義之の書をこよな<愛した唐太宗は、苦心惨憺の末に入手した 蘭亭序 を、崩御に際して副葬させました。そのため 蘭亭序 の真跡は現存しませんが、太宗が作らせた模本や拓本によって、王羲之の書法は後世に受け継がれました。
このたび20周年を迎える連携企画では、原点に回帰して、改めて王羲之と蘭亭序に焦点を当てます。両館の展示を通して、王羲之書法 や 蘭亭文化 のひろがりなど、文人たちの憧れの世界を存分にご堪能ください。
※ 新型感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上観覧を。
[ 詳 細 : 台東区立書道博物館 ] [ 詳 細 : 東京国立博物館 東洋館 第8室 ]
[ 参 考:花筏 朗文堂 ― 好日録011 吃驚仰天 中国西游記Ⅰ]
[ 参 考:花筏【新・文字百景】004 願真卿生誕1300年祭|真筆が伝承しない王羲之の書 ]

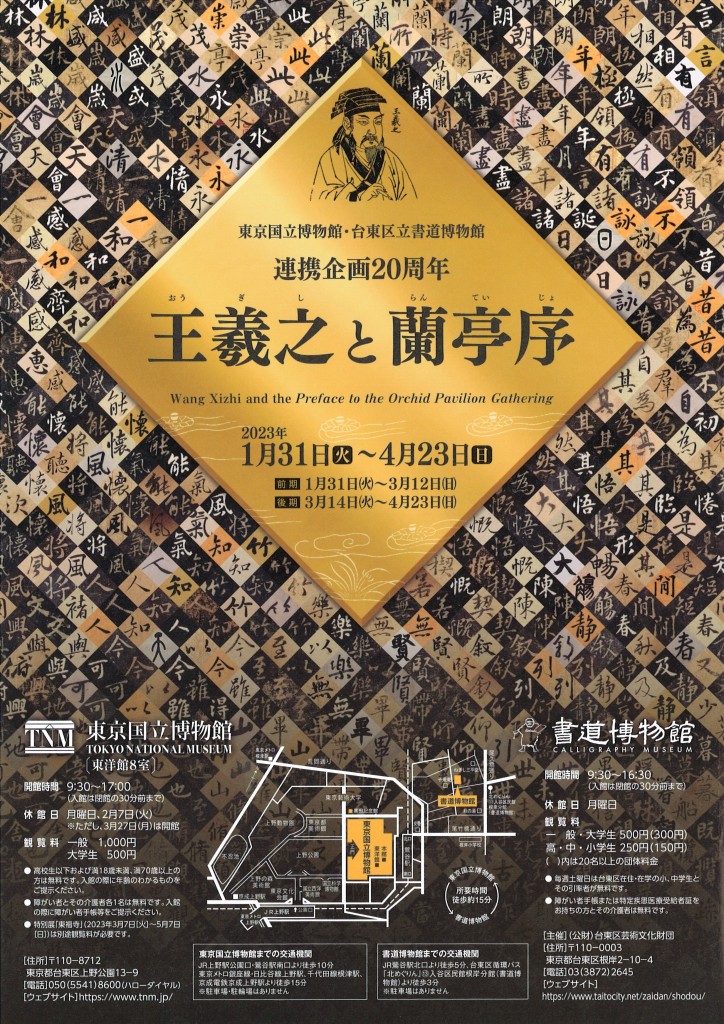
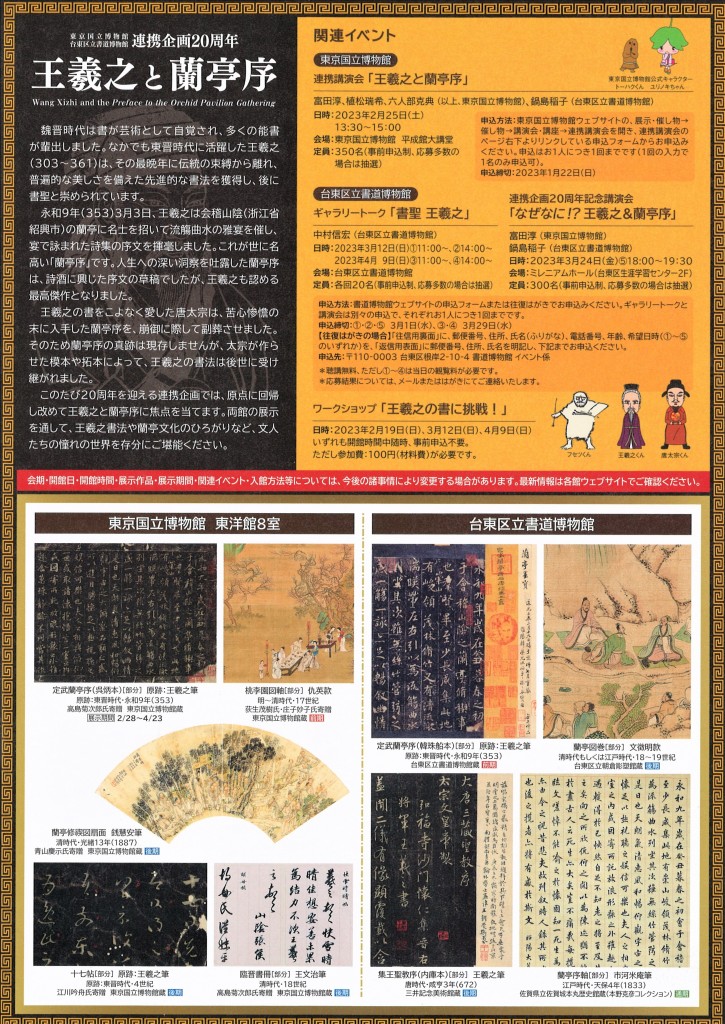
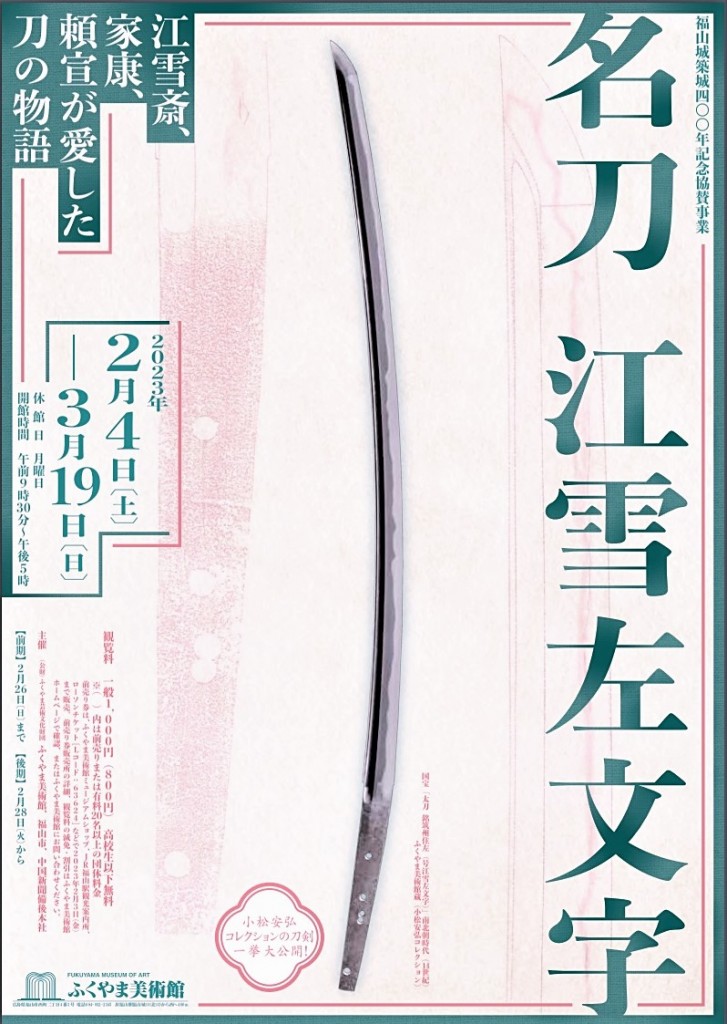
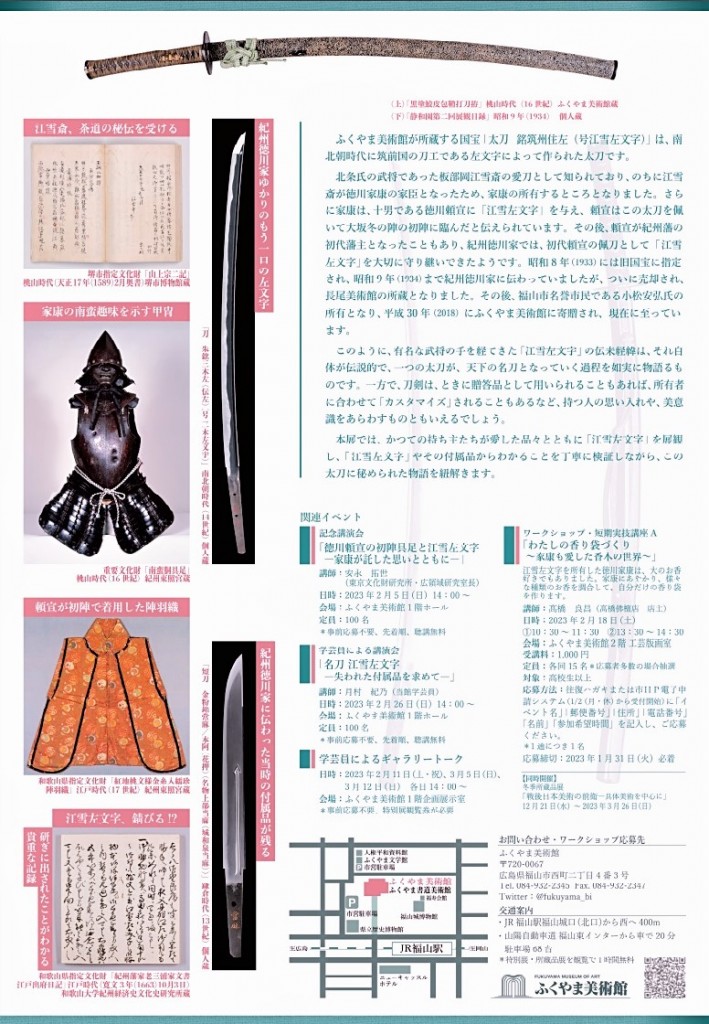
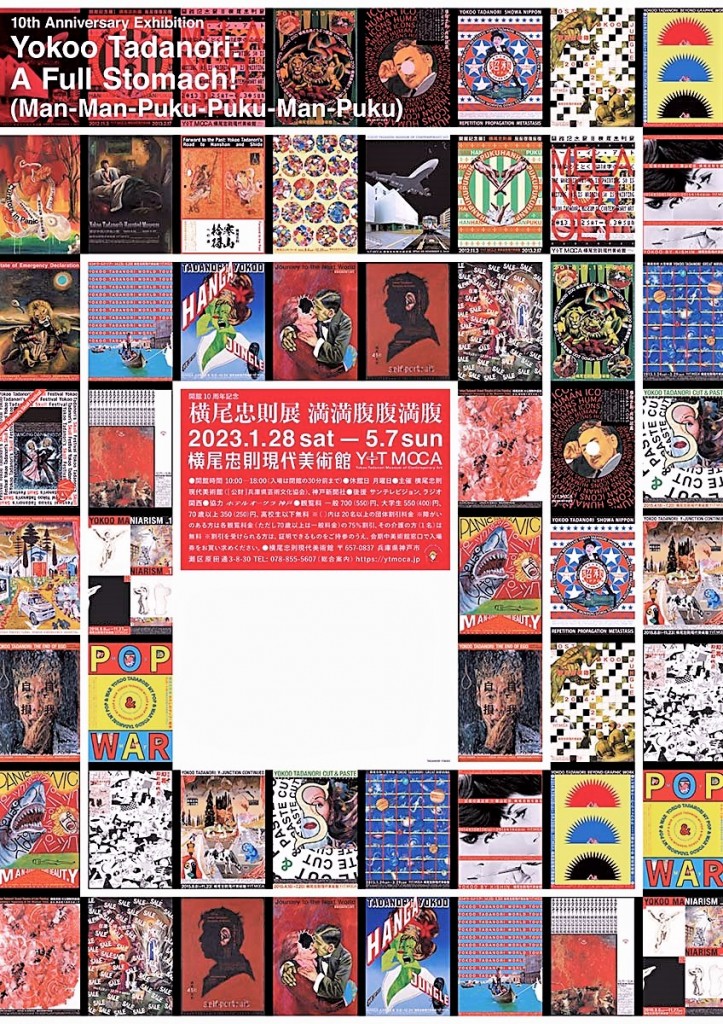
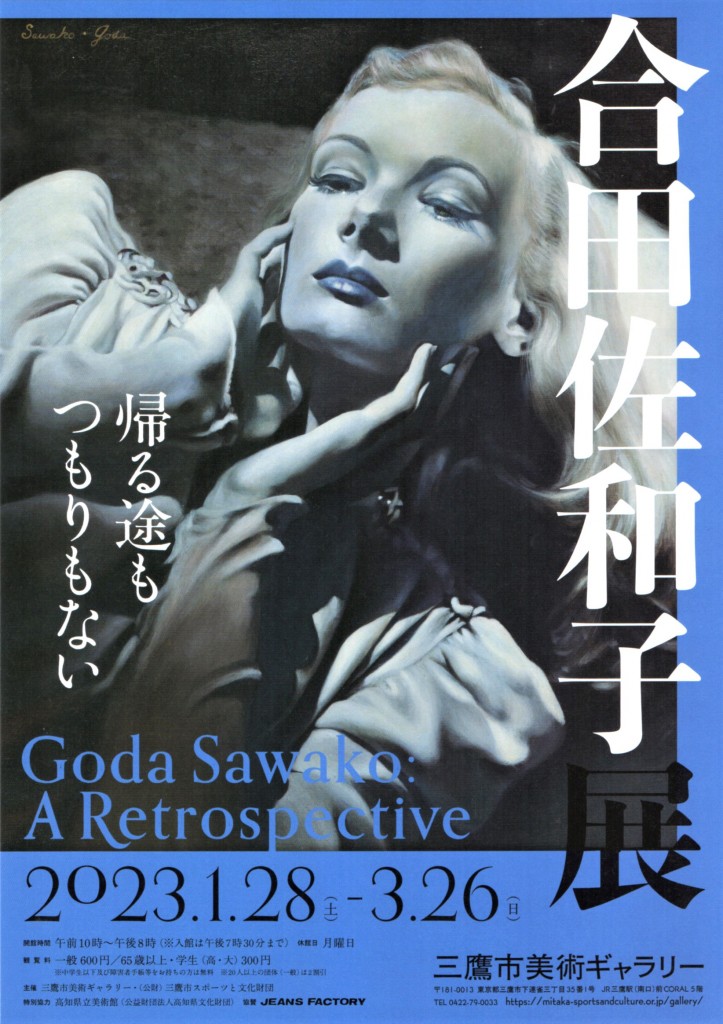
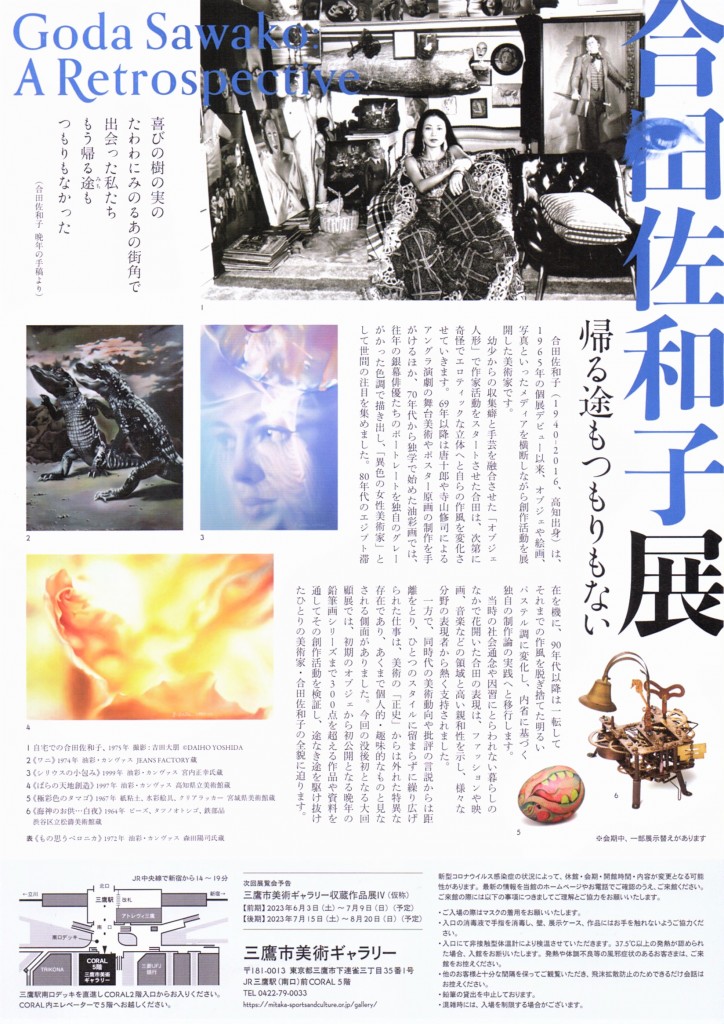


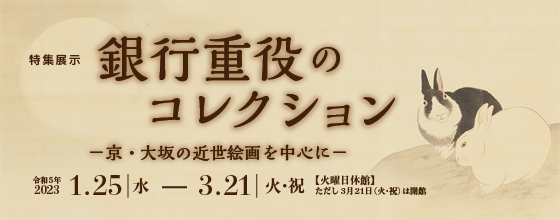
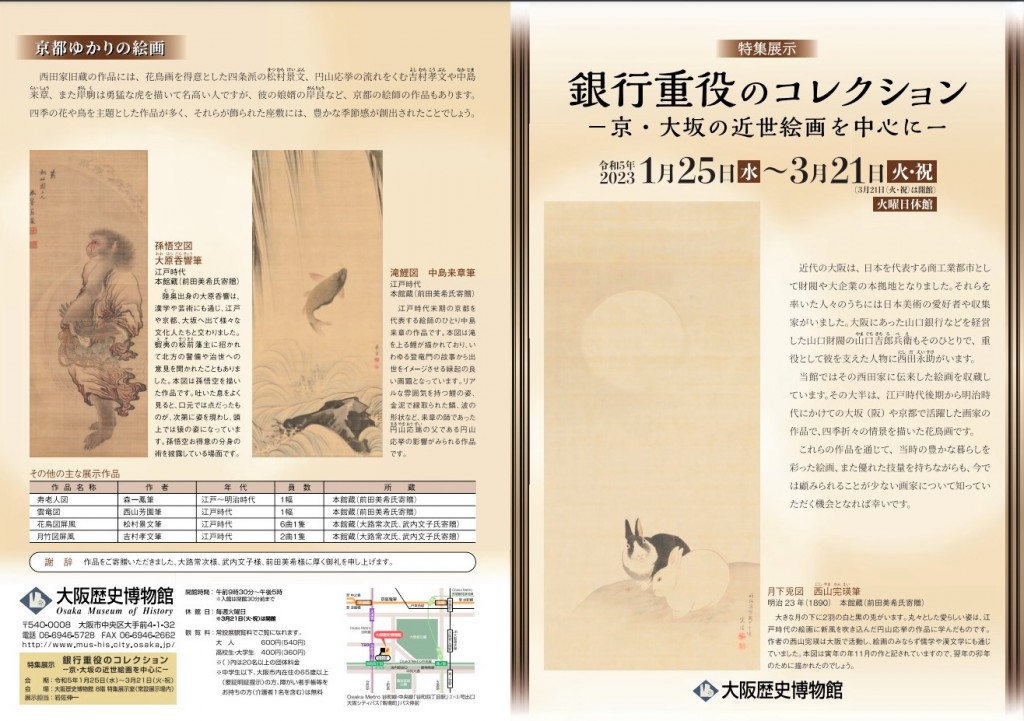
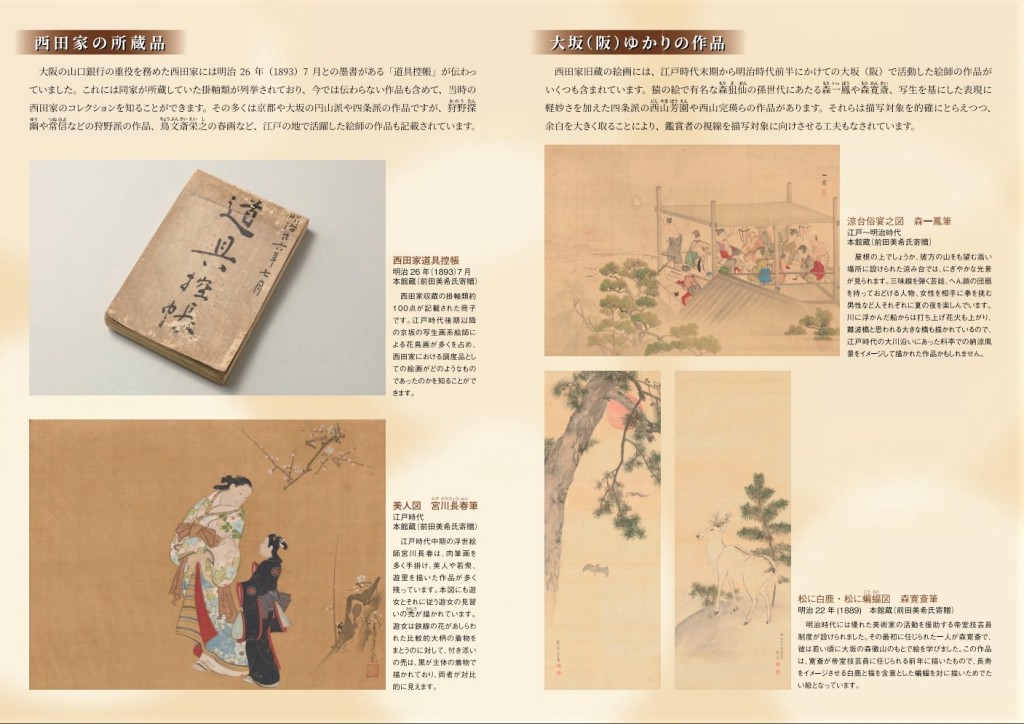
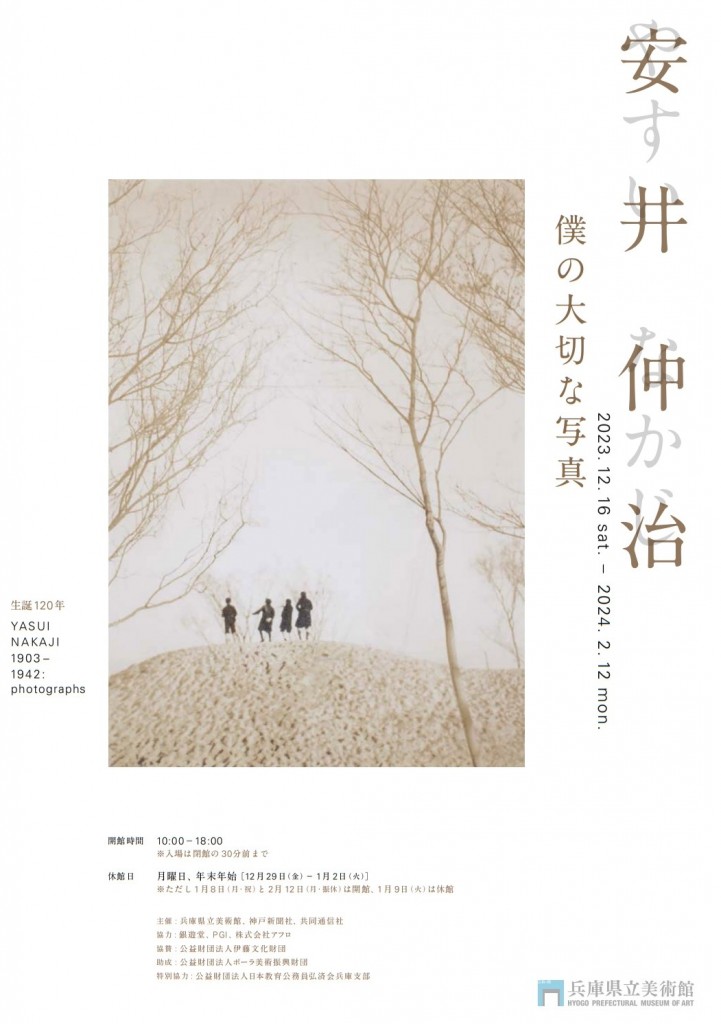
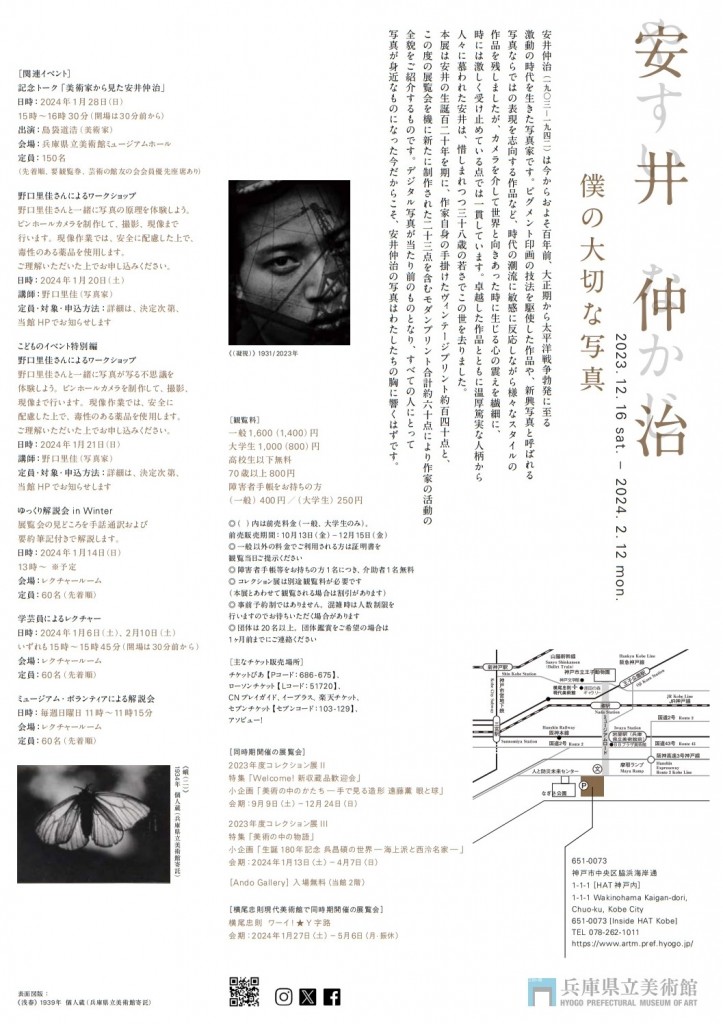

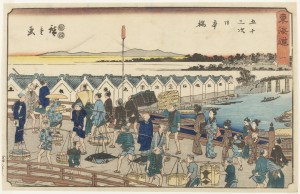
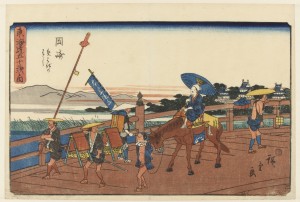

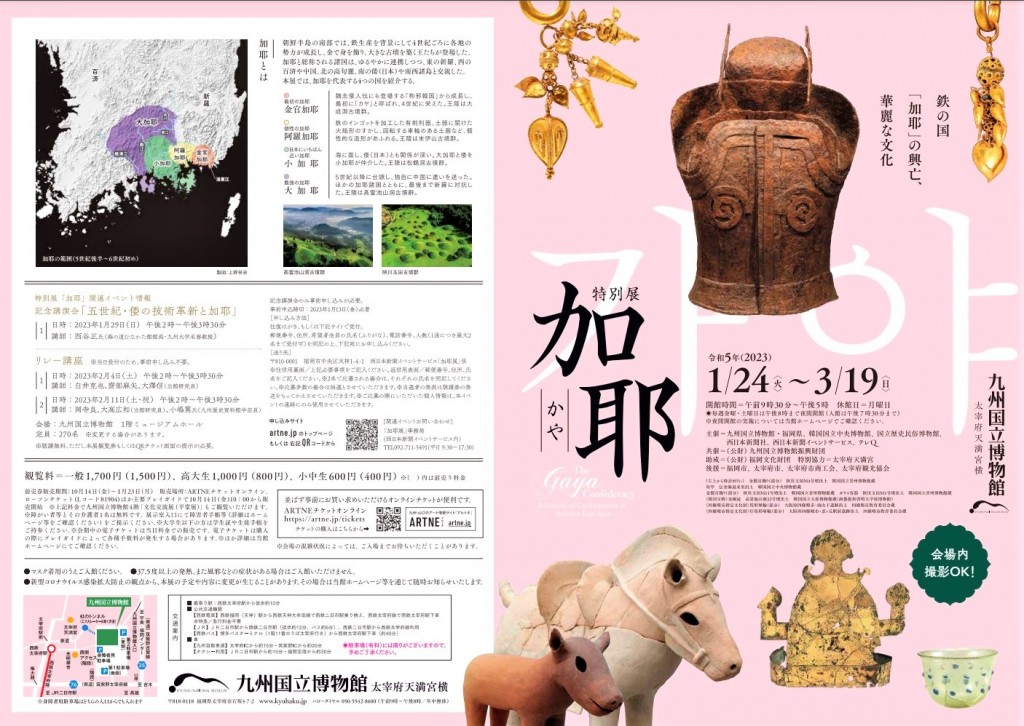

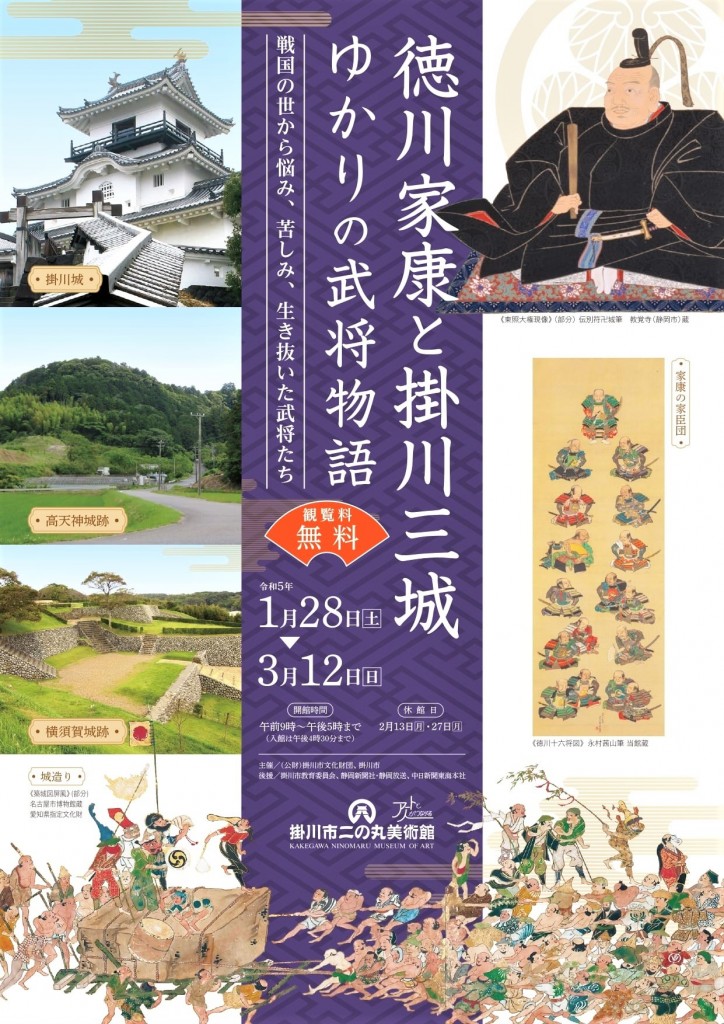
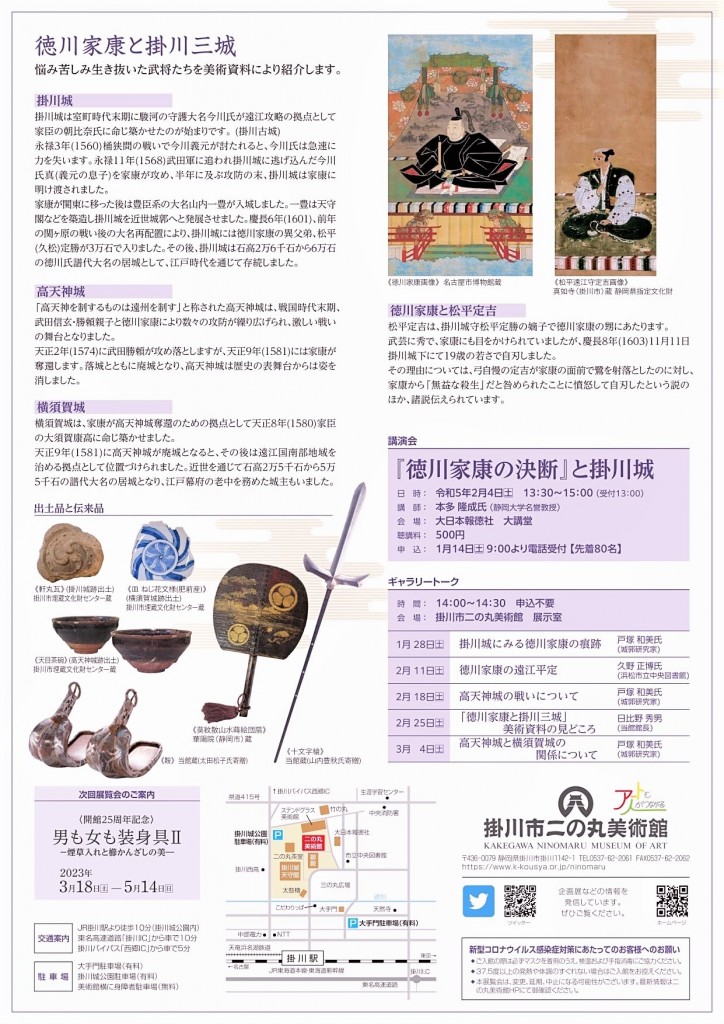
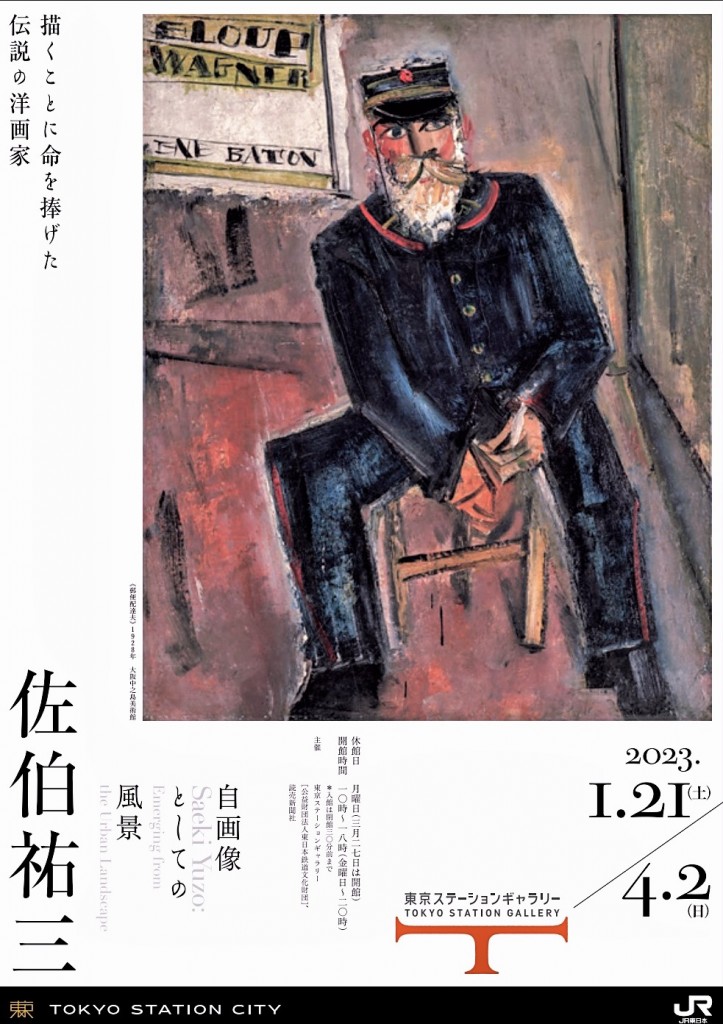
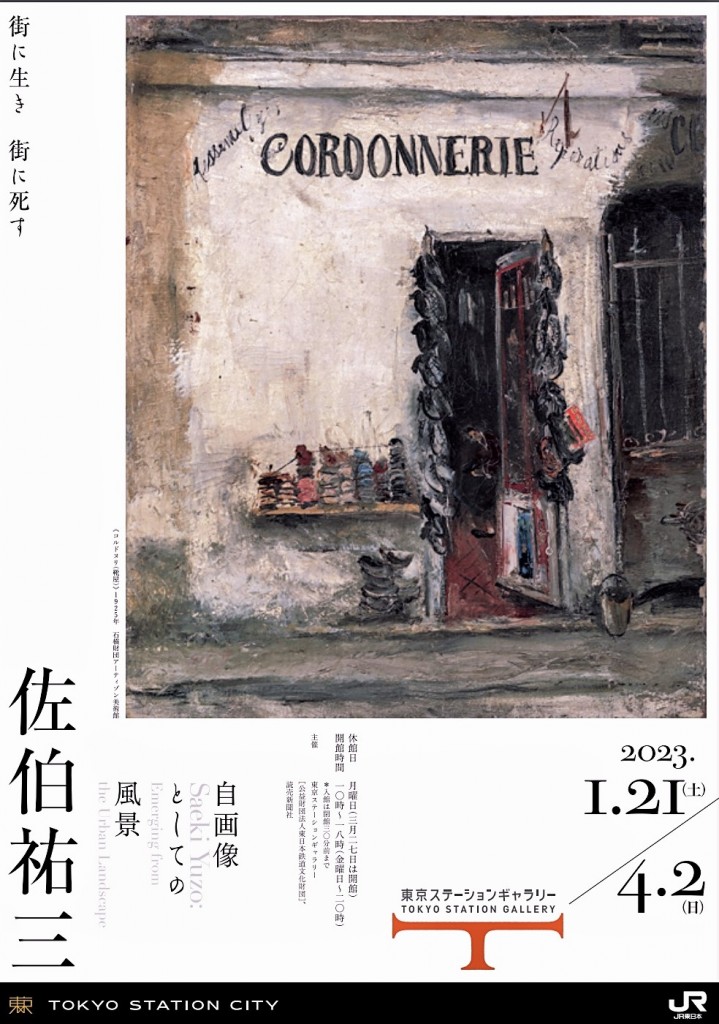
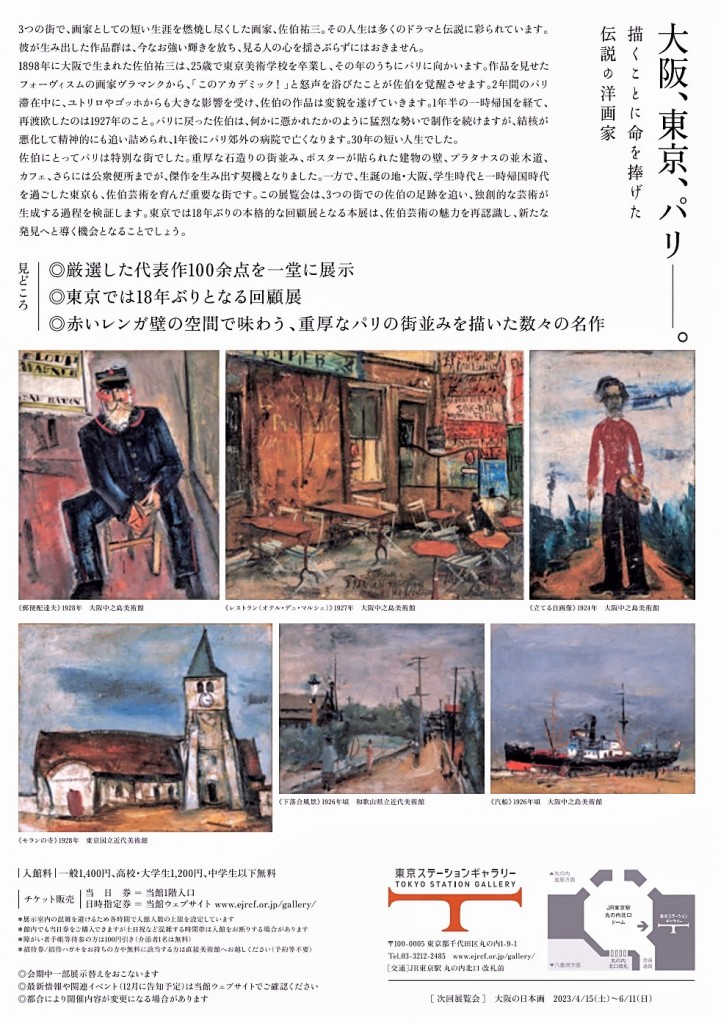
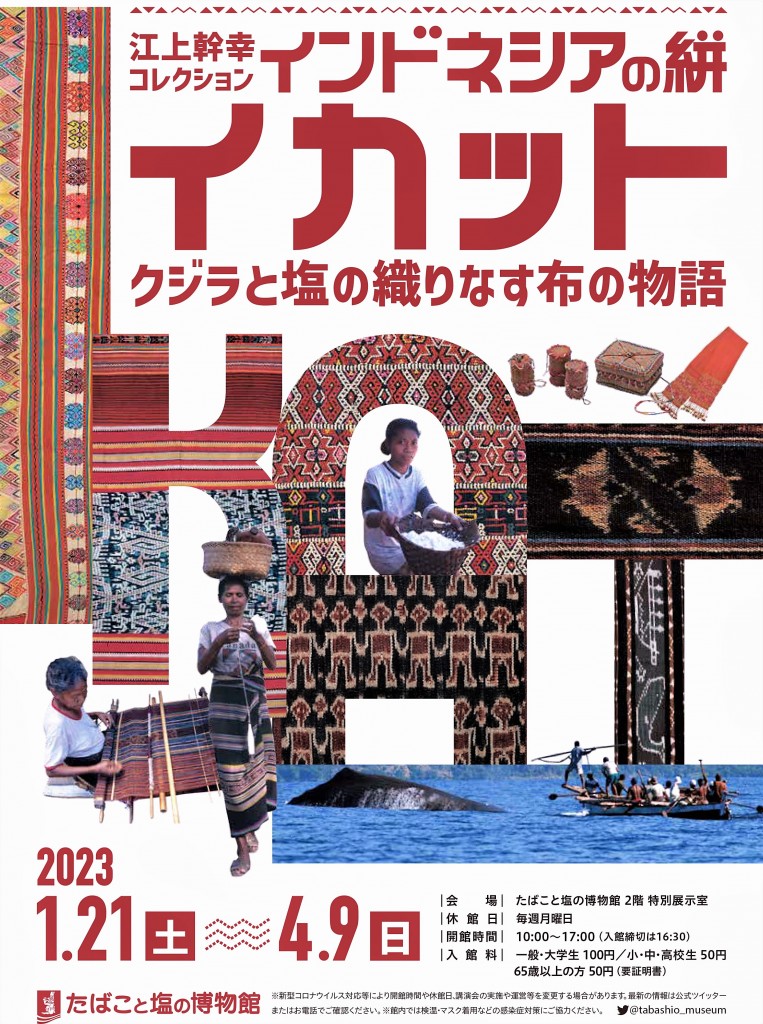
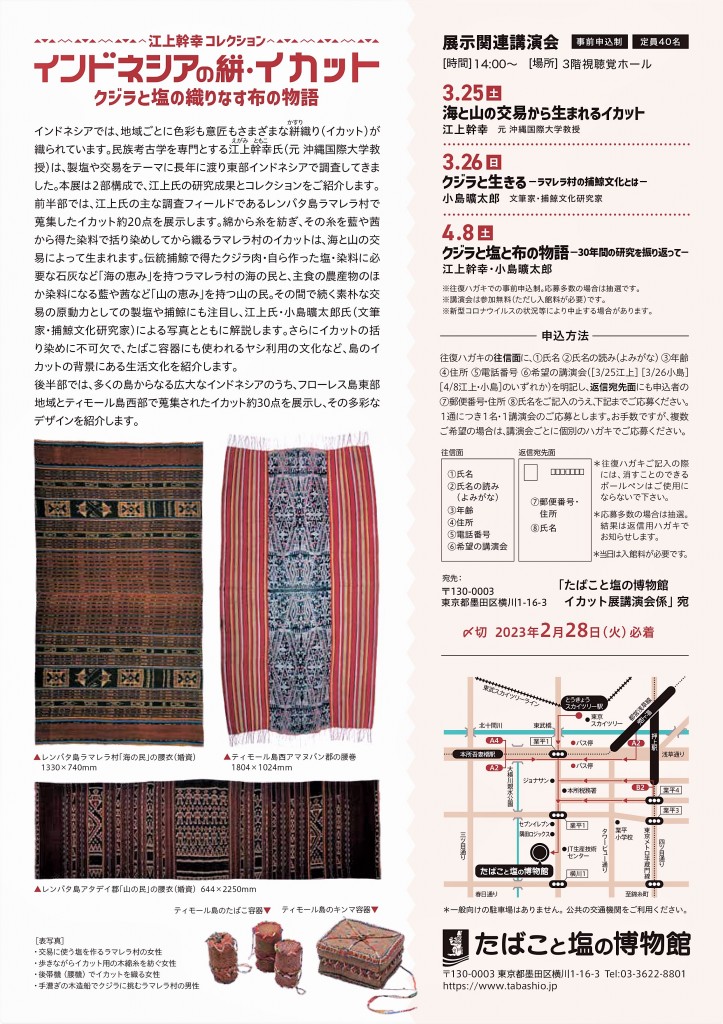



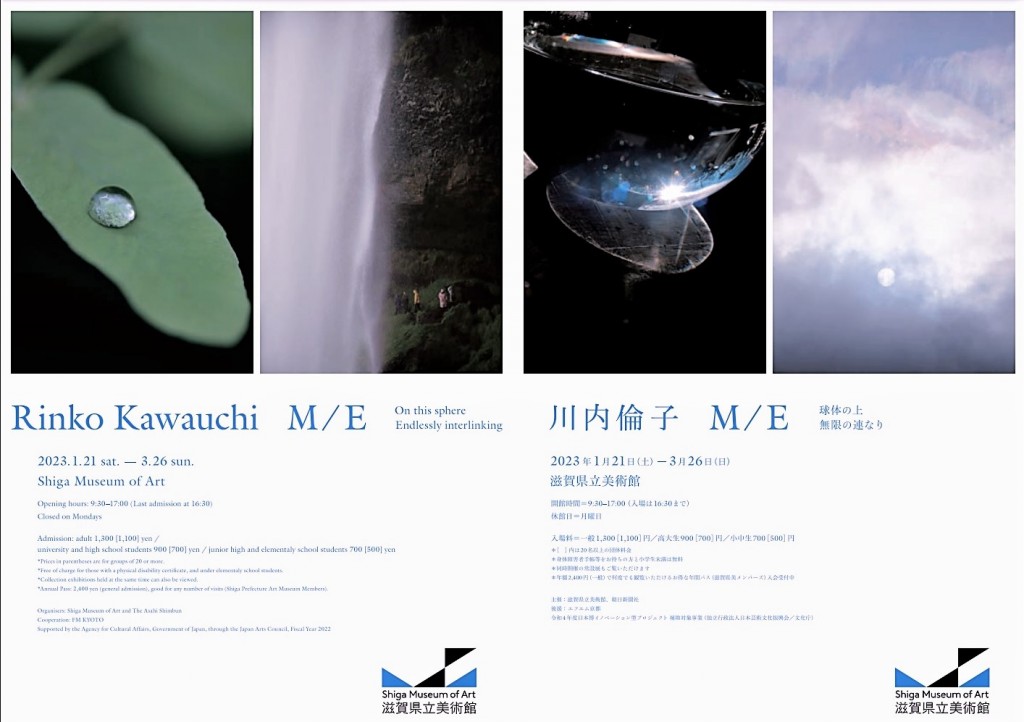

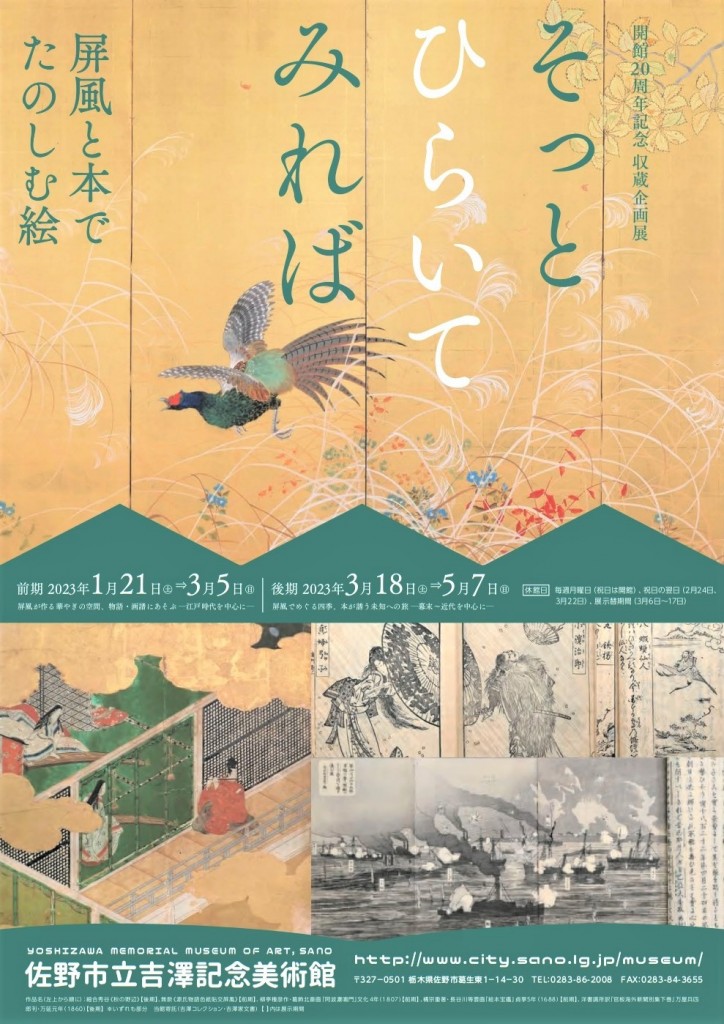
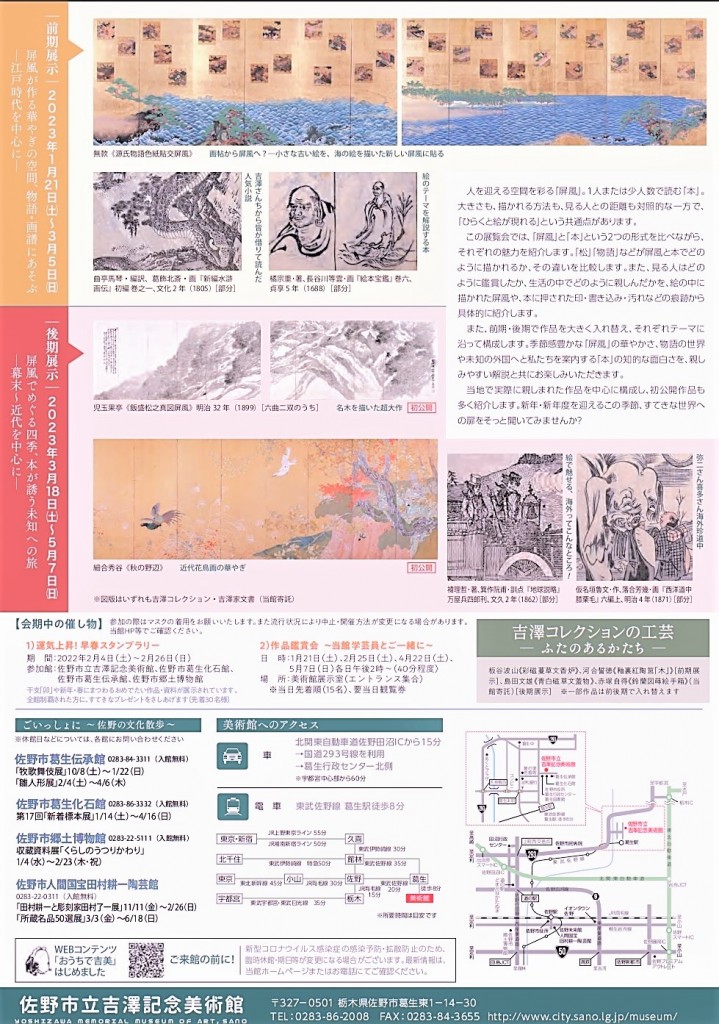
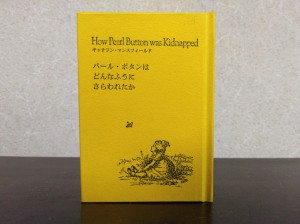
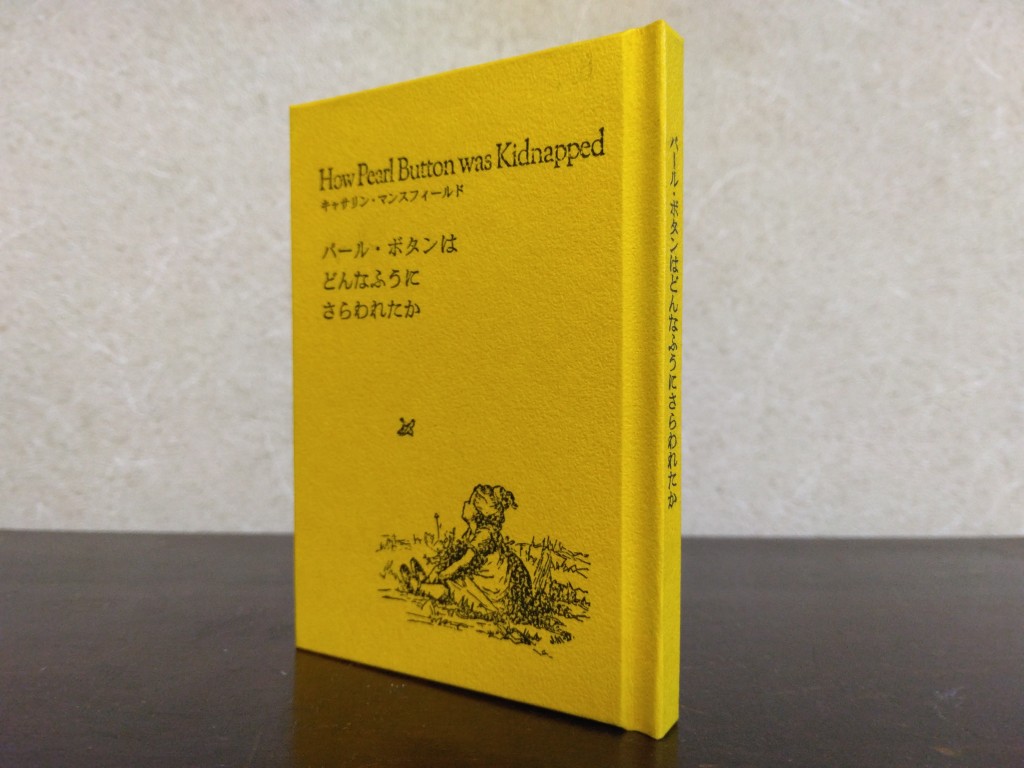
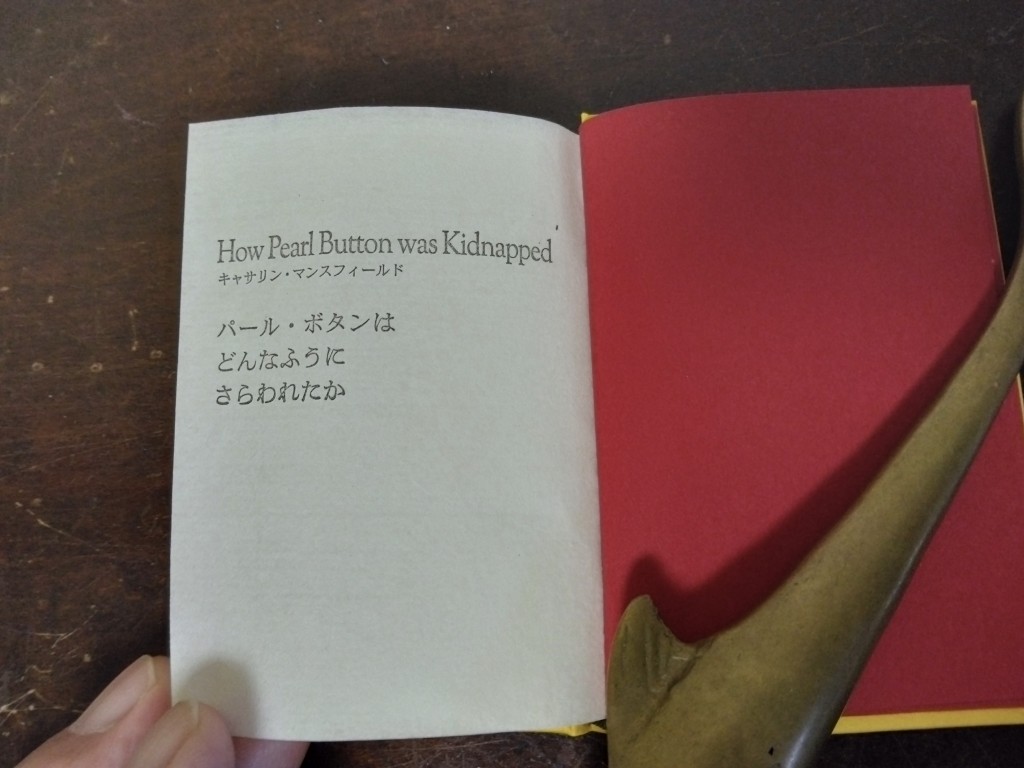
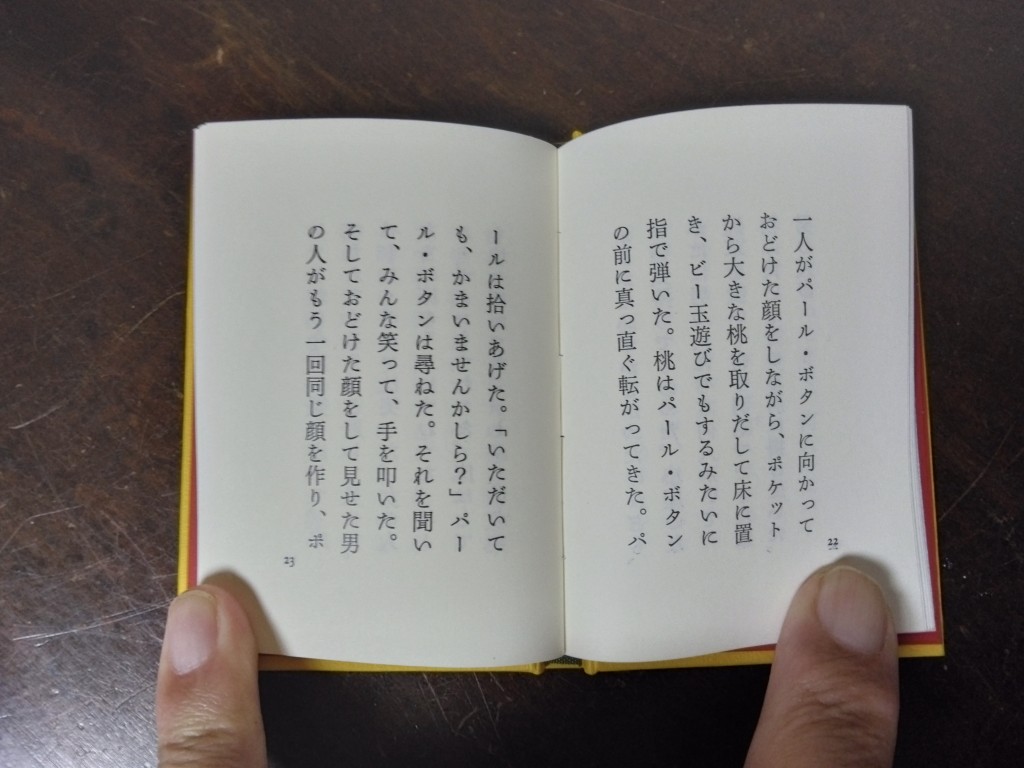 {
{ 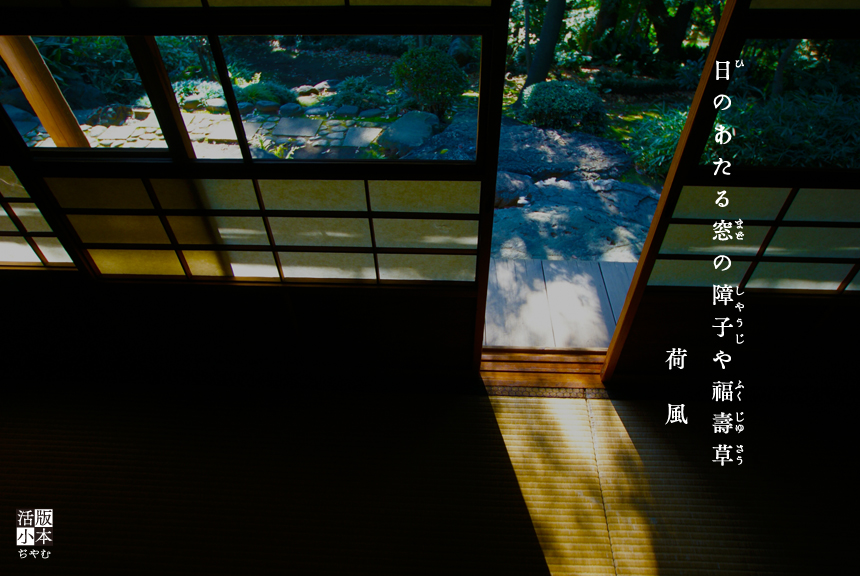
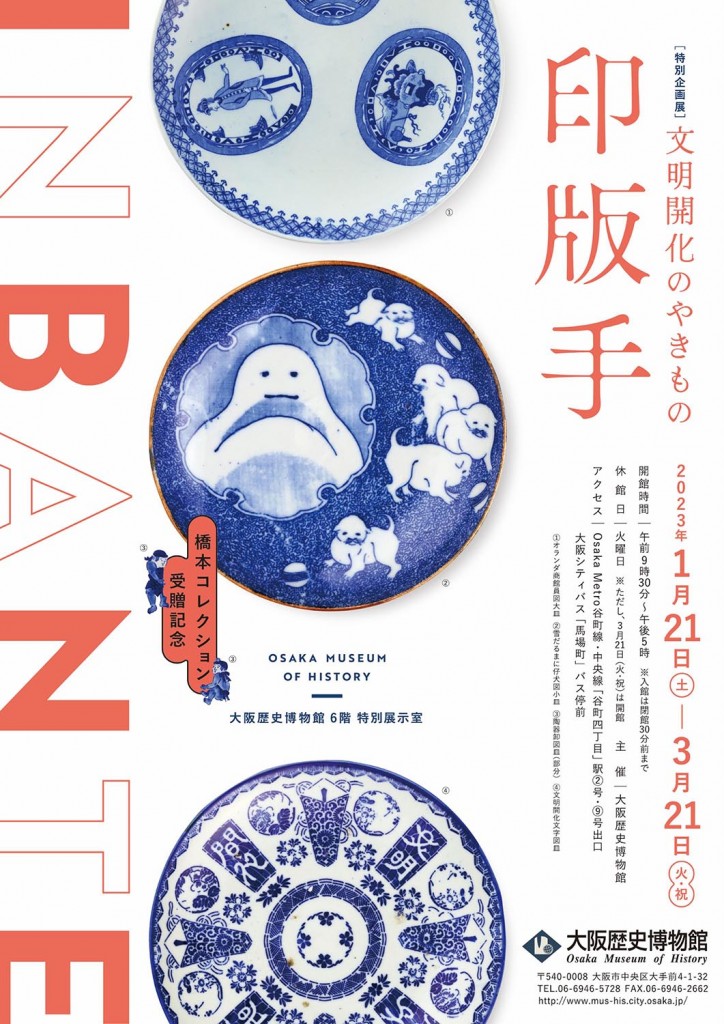

 文明開化文字図皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)
文明開化文字図皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈) オランダ商館員図大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)
オランダ商館員図大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈) 弁慶と牛若丸図横長隅切角皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)
弁慶と牛若丸図横長隅切角皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈) 猫じゃらし図隅入角大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)
猫じゃらし図隅入角大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)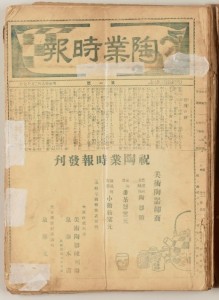
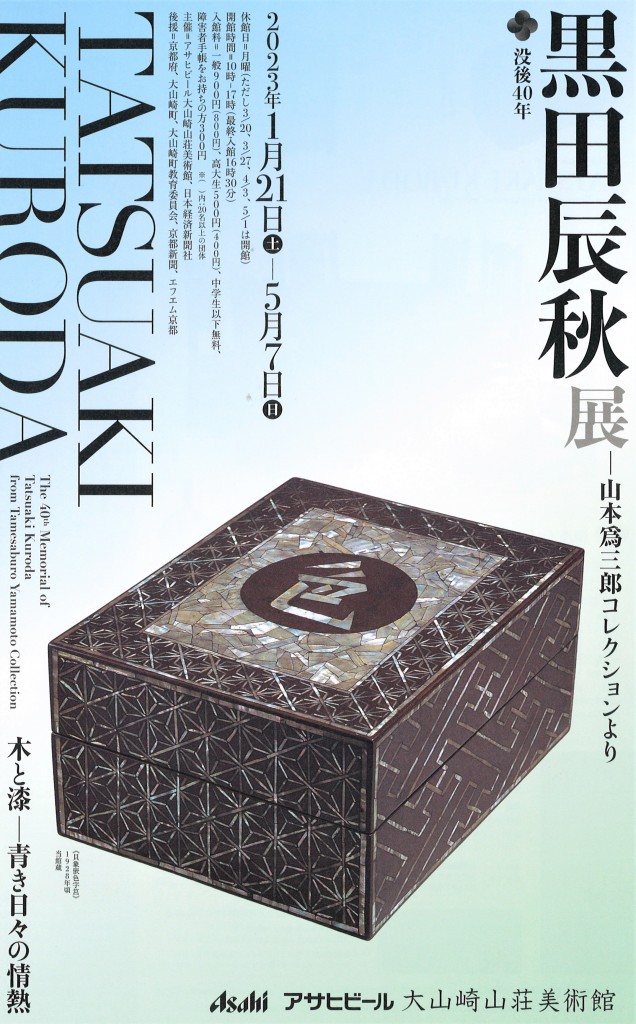
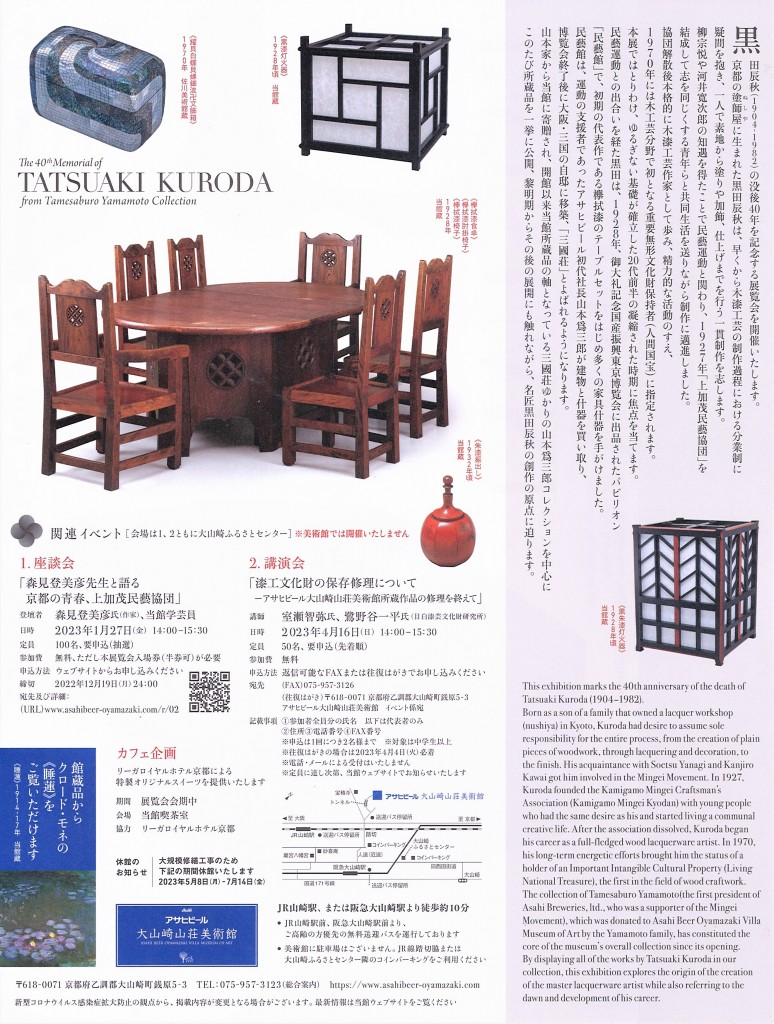



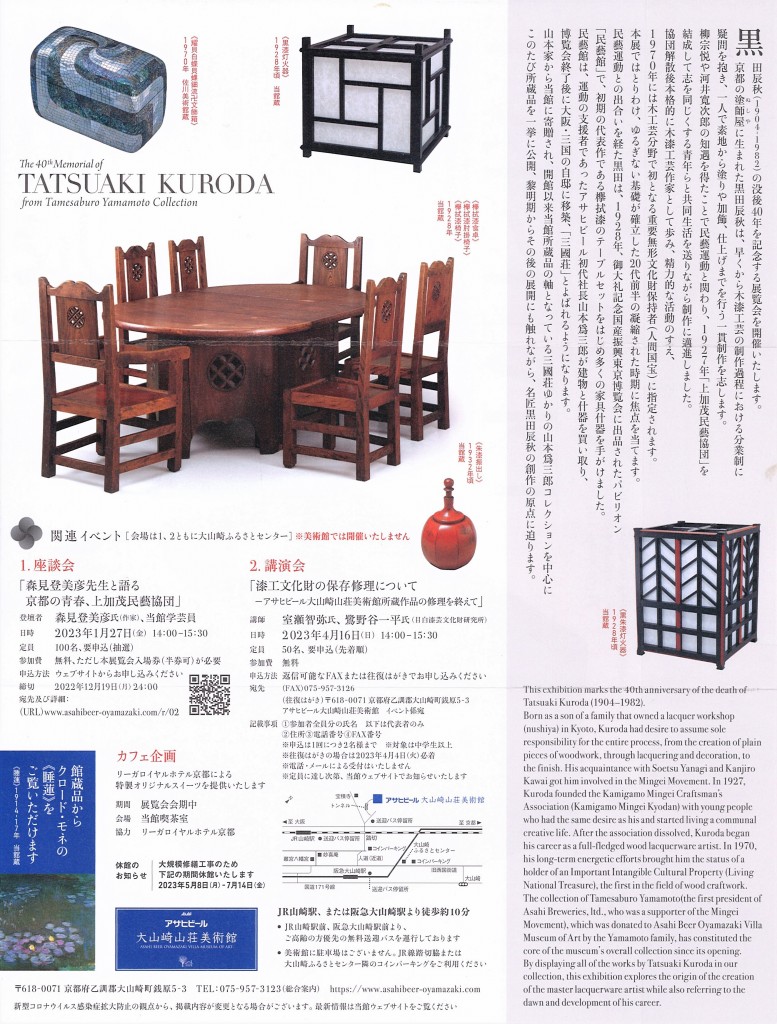
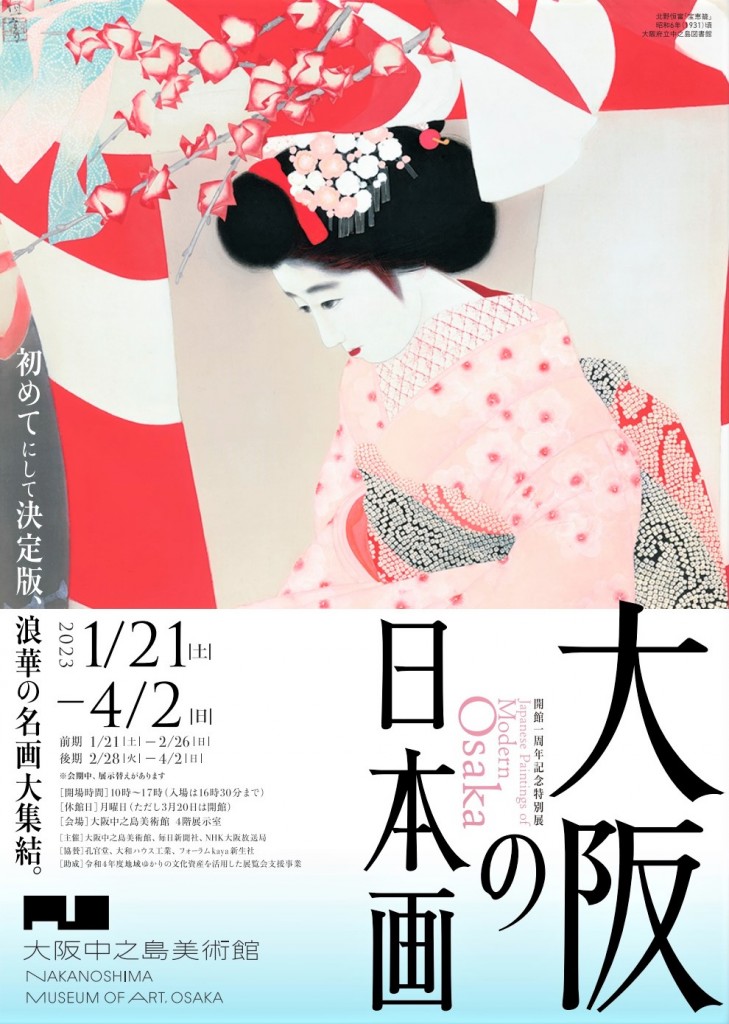
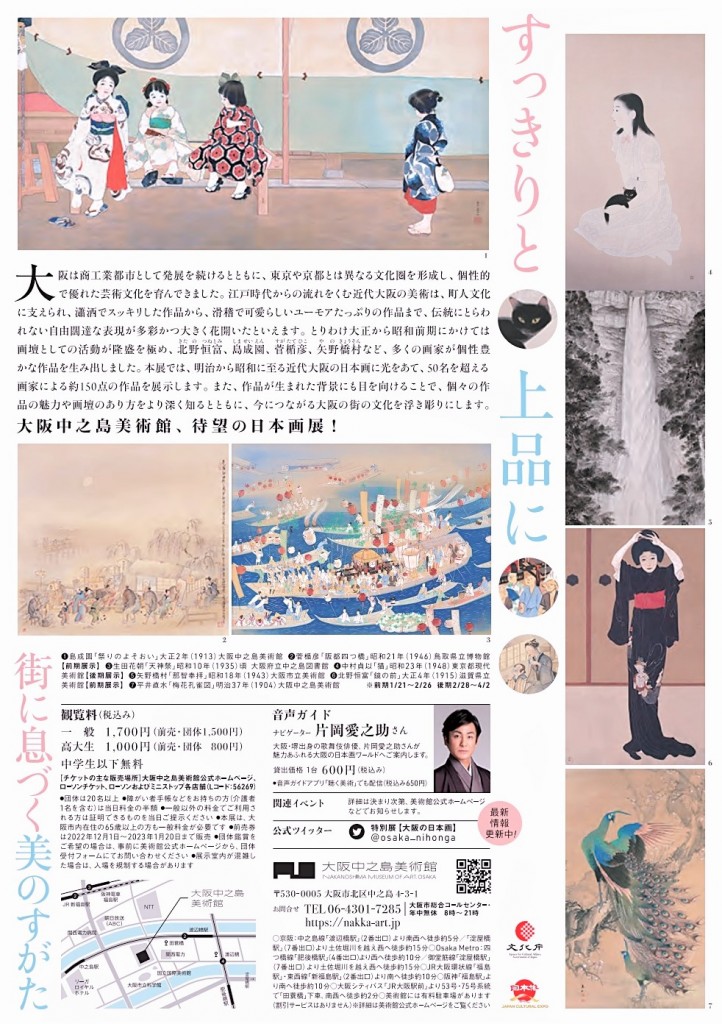
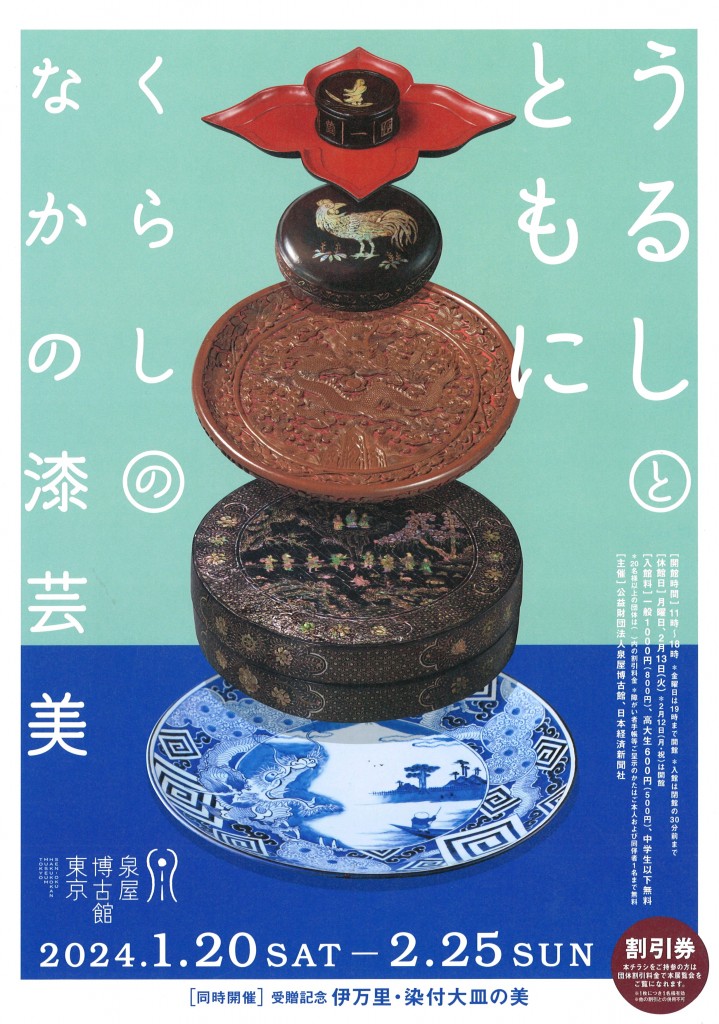





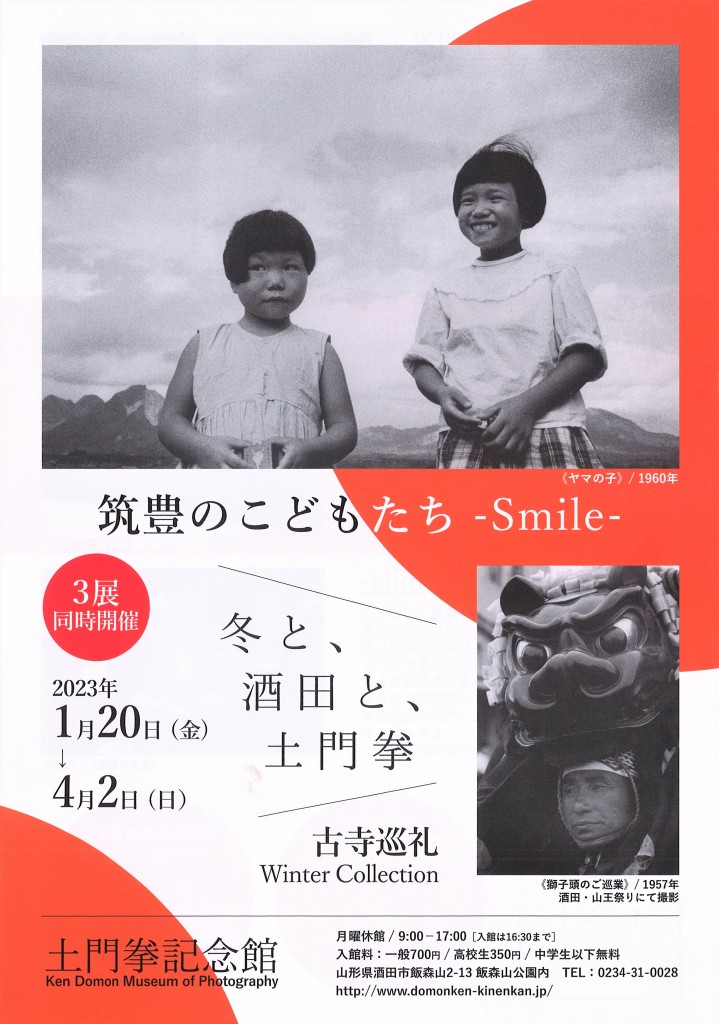
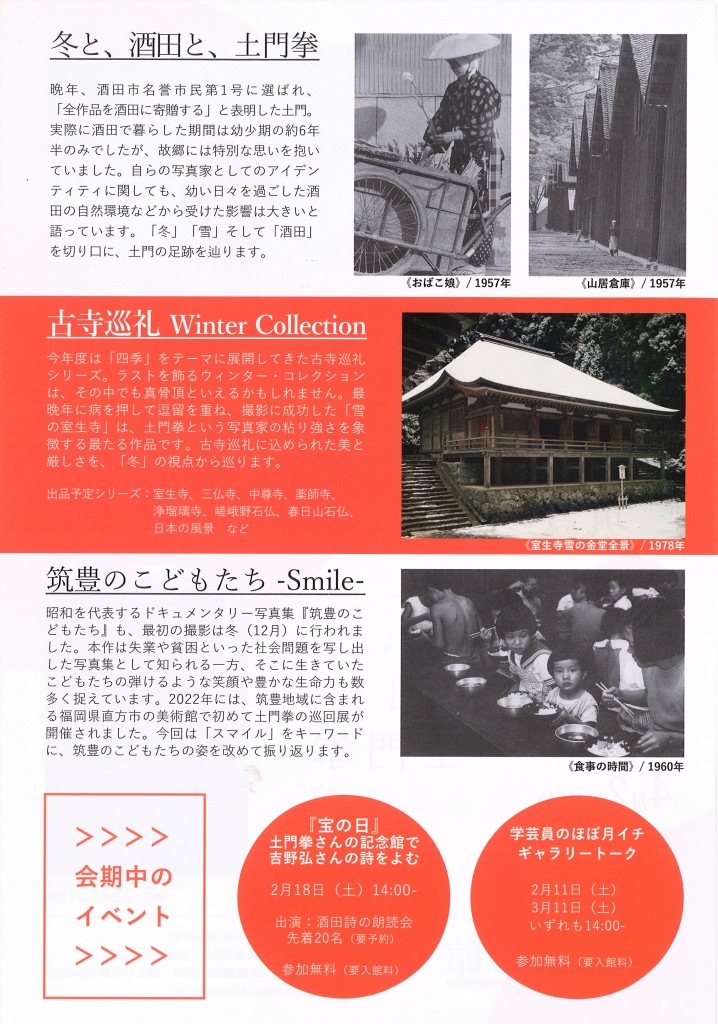
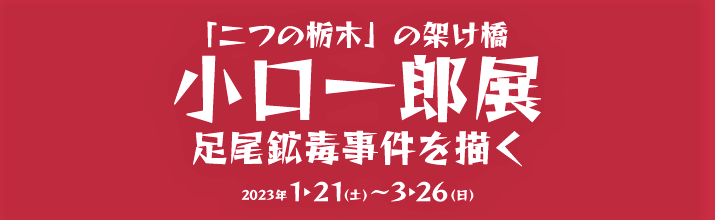
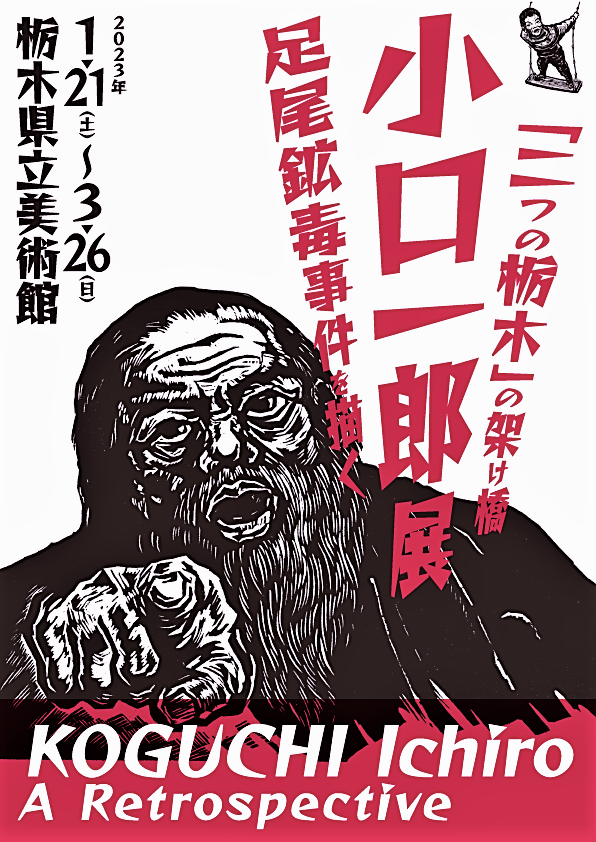
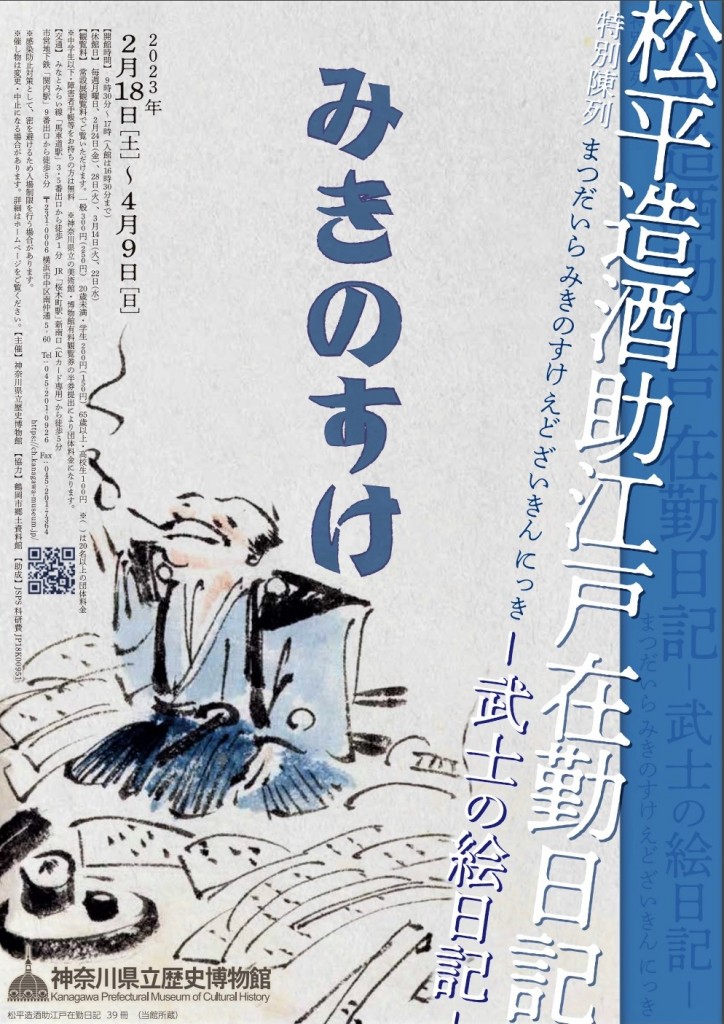
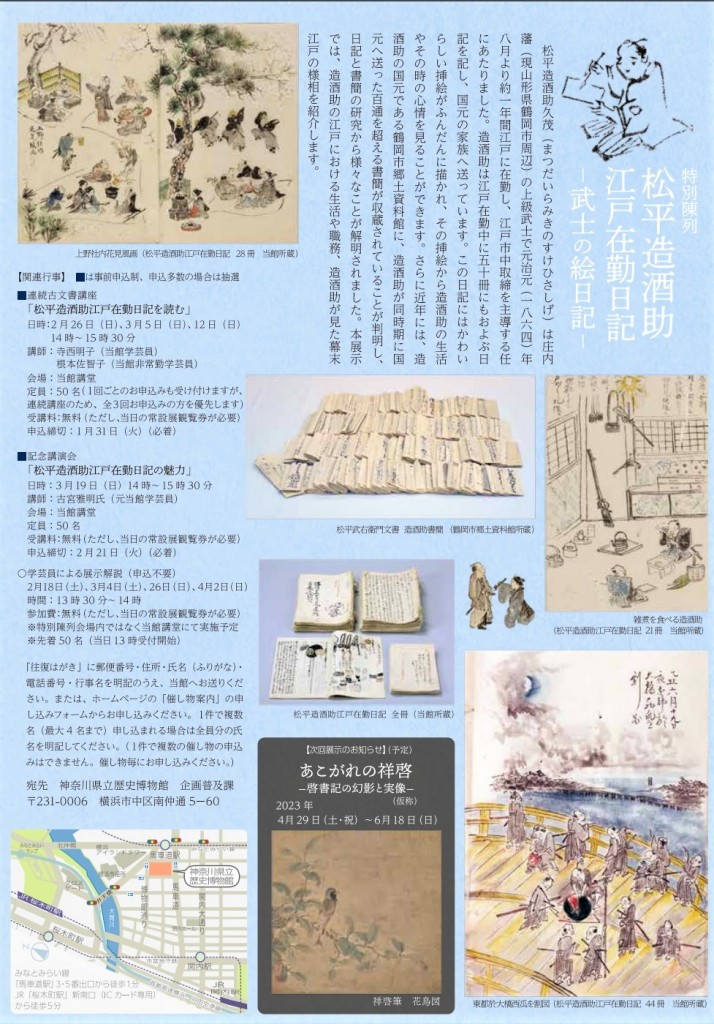
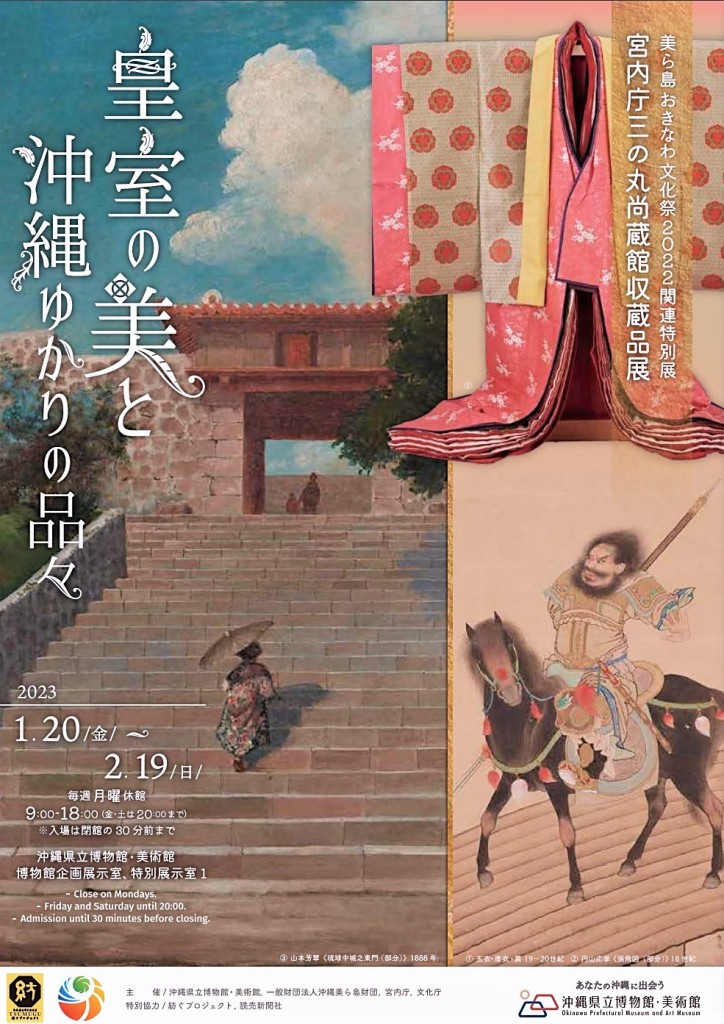

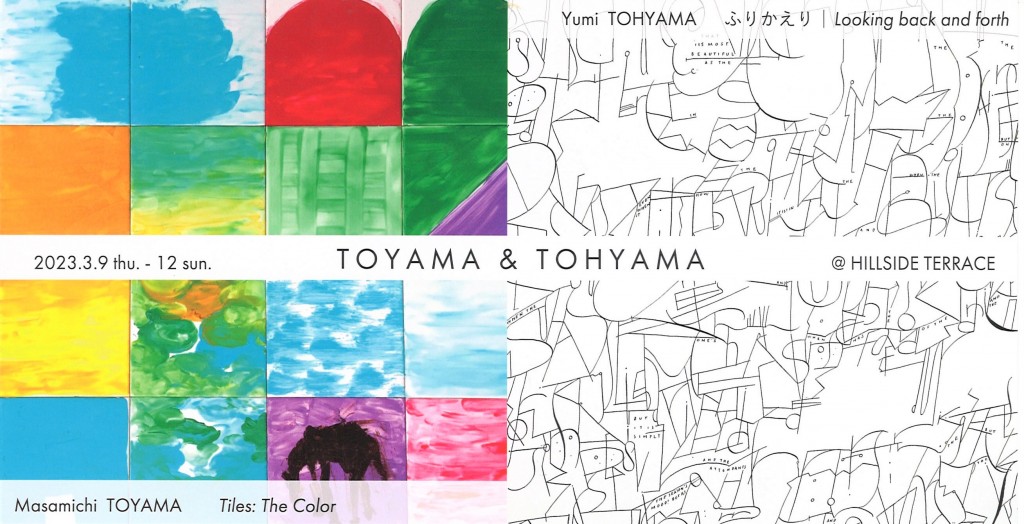 Toyama & Tohyama
Toyama & Tohyama